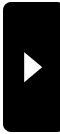2006年10月08日
はじめに
タイトル:「地上の楽園 または 神々の永遠の火」
著:冬野由記
原案:ジュール・ヴェルヌ
献辞と挨拶:
永遠の青春のなかに居るあなたへ
一九〇五年三月二四日、SFの父と呼ばれたジュール=ヴェルヌはフランスのアミヤンという町で永眠しました。それからすでに百年が経ちました。
ヴェルヌは、どのような百年を見ながら眠りについたのでしょうか。
わたくしたちは、どのような百年を振返ることができるでしょうか。
本作は、ヴェルヌ原作の ”LES INDES NOIRES”(一八八七年)に着想を得て、二十世紀、日本の産業を支えてきた炭坑と、そこで働き、暮らす人々を主人公にえがかれた物語です。
主な登場人物(予定なので変更などもありえます。ご了承ください)
日下 輝(くさか てらす): 本編の主人公。旧暁幌(あけほろ)炭坑で少年坑夫だった。
日下 亨(とおる): 輝の父。旧暁幌炭坑で随一の腕利きの坑夫だった。
日下 円(まどか): 輝の母。
星 直耀(ほし ただてる): 男爵。高名な鉱山技師。旧暁幌炭坑の所長。
月岡 瑛(つきおか あきら): 暁幌炭坑で少年坑夫だった輝の幼友達。
ネル: 謎の少女。
穂村十三(ほむら じゅうざ): 旧暁幌炭坑で石炭ガス処理にあたっていた坑夫。
石浜木綿(いしはま ゆう): 旧暁幌に暮らしていた未亡人。亨たちの隣人。
ソフィ=ナプホルト: 欧州からやってきた少女。考古学研究者。
レオン=ナプホルト: ソフィの父。高名な物理学、鉱物学者。
グスタフ=ライセンフェルト: ソフィの従兄。レオンの弟子。
アスプロス : 白い大梟(ふくろう)
時代
二十世紀初頭の日本
舞台
北海道 暁幌炭坑(架空の炭坑ですが、夕張をイメージしています)
本編は、次回から。お楽しみに。(明日にも第一回掲載の予定。がんばります)
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
著:冬野由記
原案:ジュール・ヴェルヌ
献辞と挨拶:
永遠の青春のなかに居るあなたへ
一九〇五年三月二四日、SFの父と呼ばれたジュール=ヴェルヌはフランスのアミヤンという町で永眠しました。それからすでに百年が経ちました。
ヴェルヌは、どのような百年を見ながら眠りについたのでしょうか。
わたくしたちは、どのような百年を振返ることができるでしょうか。
本作は、ヴェルヌ原作の ”LES INDES NOIRES”(一八八七年)に着想を得て、二十世紀、日本の産業を支えてきた炭坑と、そこで働き、暮らす人々を主人公にえがかれた物語です。
主な登場人物(予定なので変更などもありえます。ご了承ください)
日下 輝(くさか てらす): 本編の主人公。旧暁幌(あけほろ)炭坑で少年坑夫だった。
日下 亨(とおる): 輝の父。旧暁幌炭坑で随一の腕利きの坑夫だった。
日下 円(まどか): 輝の母。
星 直耀(ほし ただてる): 男爵。高名な鉱山技師。旧暁幌炭坑の所長。
月岡 瑛(つきおか あきら): 暁幌炭坑で少年坑夫だった輝の幼友達。
ネル: 謎の少女。
穂村十三(ほむら じゅうざ): 旧暁幌炭坑で石炭ガス処理にあたっていた坑夫。
石浜木綿(いしはま ゆう): 旧暁幌に暮らしていた未亡人。亨たちの隣人。
ソフィ=ナプホルト: 欧州からやってきた少女。考古学研究者。
レオン=ナプホルト: ソフィの父。高名な物理学、鉱物学者。
グスタフ=ライセンフェルト: ソフィの従兄。レオンの弟子。
アスプロス : 白い大梟(ふくろう)
時代
二十世紀初頭の日本
舞台
北海道 暁幌炭坑(架空の炭坑ですが、夕張をイメージしています)
本編は、次回から。お楽しみに。(明日にも第一回掲載の予定。がんばります)
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月09日
序:人間の分け前
<序:人間の分け前>
かつて、オリュンポスの神々と人間たちの間で、犠牲(神様へのお供え物。主として牛や羊などの動物が多い)の取り分を決める会合を行ったことがあった。
巨人族の生き残りのひとりであるプロメテウスは何かと人間に同情的で、彼には先々のことを見通す能力もあったので、人間にこんな入れ知恵をした。
「ひとつは肉を脂身でくるんでおきなさい。もうひとつは、骨を毛皮でおおっておきなさい。神々はきっと骨のほうを選ぶから」
プロメテウスは、人間たちのために、食べられる部分を取り分にしてやろうと知恵をひねったのである。
さて、会合の日、ゼウスは、ふたつの供え物を見て「脂身ばかりではかなわない」とばかりに(中身は見えないが、きっと肉や骨がくるまっているのだろうと)毛皮にくるまれた方を採った。
かくして、プロメテウスの見通したとおり、犠牲で神々をお祀りした後、皮と骨は燃やして神々に捧げ、肉と脂身は人間の取り分として、人間たちはこれを食すことができるようになったのである。
プロメテウスは、確かに先を見通した。その名のとおりに。
しかし、プロメテウスと人間たちは、はたして、この駆け引きに勝利したのか。彼らはゼウスを出し抜いたのか。
未来を決する権利も力も神々のものである。
骨も毛皮も朽ちることはない。しかし、肉や脂はやがて腐り、土に還る運命にある。
神々は、不老不死であり、もとより生きるために食べ物を求める必要はないのである。
神々は、その王たる全知全能のゼウスは、この会合において、あらためて神々の不老不死と、そして、人間が生きるために糧を要するということ、そのために生き物の命を奪わねばならないこと、そして、その人間自身がいつかは朽ち腐り、土に還らねばならないことを示したのだ。
遠謀と戦略において、ゼウスはプロメテウスを凌いでいたというほかはない。
かくして、永遠と至福は神々の、滅びと労苦は人間の分け前となったのである。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
かつて、オリュンポスの神々と人間たちの間で、犠牲(神様へのお供え物。主として牛や羊などの動物が多い)の取り分を決める会合を行ったことがあった。
巨人族の生き残りのひとりであるプロメテウスは何かと人間に同情的で、彼には先々のことを見通す能力もあったので、人間にこんな入れ知恵をした。
「ひとつは肉を脂身でくるんでおきなさい。もうひとつは、骨を毛皮でおおっておきなさい。神々はきっと骨のほうを選ぶから」
プロメテウスは、人間たちのために、食べられる部分を取り分にしてやろうと知恵をひねったのである。
さて、会合の日、ゼウスは、ふたつの供え物を見て「脂身ばかりではかなわない」とばかりに(中身は見えないが、きっと肉や骨がくるまっているのだろうと)毛皮にくるまれた方を採った。
かくして、プロメテウスの見通したとおり、犠牲で神々をお祀りした後、皮と骨は燃やして神々に捧げ、肉と脂身は人間の取り分として、人間たちはこれを食すことができるようになったのである。
プロメテウスは、確かに先を見通した。その名のとおりに。
しかし、プロメテウスと人間たちは、はたして、この駆け引きに勝利したのか。彼らはゼウスを出し抜いたのか。
未来を決する権利も力も神々のものである。
骨も毛皮も朽ちることはない。しかし、肉や脂はやがて腐り、土に還る運命にある。
神々は、不老不死であり、もとより生きるために食べ物を求める必要はないのである。
神々は、その王たる全知全能のゼウスは、この会合において、あらためて神々の不老不死と、そして、人間が生きるために糧を要するということ、そのために生き物の命を奪わねばならないこと、そして、その人間自身がいつかは朽ち腐り、土に還らねばならないことを示したのだ。
遠謀と戦略において、ゼウスはプロメテウスを凌いでいたというほかはない。
かくして、永遠と至福は神々の、滅びと労苦は人間の分け前となったのである。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月09日
プロローグ:炭坑を知っていますか
<プロローグ:炭坑を知っていますか>
炭坑を知っていますか?
知識として「炭坑」のことをご存知の方は多いでしょう。
ドラマや映画、テレビのドキュメンタリーなどで、かつての炭坑の賑わいや、厳しい坑夫の労働や暮らしを「画面の上に」観たという人は少なくないと思います。
でも、炭坑や炭鉱町の実物をその目で見た人、坑夫やトロッコや石炭を実際に見たという人は、今ではほとんど居ないでしょうね。
私が子供の頃は、日本のあちこちに炭坑があって、盛んに石炭を掘り出していました。私の住んでいた町の近くにも、大きな炭坑がいくつかあって、ボタ山(掘り出した石炭の屑を積み上げた山)をあちこちで見かけたものです。石炭を積み出すための鉄道のレールが炭坑から港まで縦横に走っていて、石炭を積んだおびただしい数の貨車が機関車に引かれてひっきりなしに運ばれていたのです。休日には、炭坑で働く人々や彼らの家族が街にあふれ、それは賑やかなものでした。
私は「炭坑」と書きましたが「炭鉱」という書き方もあります。「炭鉱」は石炭の鉱脈のことです。「炭坑」というと、その鉱脈から石炭を掘り出すために地中深く穴を掘って築いた「坑道」のことになります。海外には、穴を掘らなくても山の斜面などに剥き出しになった鉱脈から石炭を掘り出すことのできる炭鉱がたくさんあります。そういう掘り出し方を「露天掘り」と言います。でも、日本の炭鉱はほとんどが地中深くに埋もれているので、穴を掘り、坑道を縦横に築いて鉱脈にたどり着かなければなりません。ですから、日本の炭鉱のほとんどは「炭坑」だ、ということになります。
石炭は発展途上にあった日本の、産業を支える血液でした。
炭坑で働く人々は、その血液を産業界に、社会に、日々送り出していたのです。彼らの支えなくして、近代の日本はありえなかったでしょう。
日本の炭坑夫たちは、爆発や落盤の危険と隣り合わせの、深く危険な地の底で、そんな誇りとプライドを胸に秘めて、命がけで働いていたのです。
男たちだけではありません。女たちも、子供たちも、いっしょに汗まみれになって、坑道の奥深くで石炭を掘り出していたのです。
この物語の主人公は、百年ほども昔の、そんな「炭坑」と、そこで働く人々です。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
炭坑を知っていますか?
知識として「炭坑」のことをご存知の方は多いでしょう。
ドラマや映画、テレビのドキュメンタリーなどで、かつての炭坑の賑わいや、厳しい坑夫の労働や暮らしを「画面の上に」観たという人は少なくないと思います。
でも、炭坑や炭鉱町の実物をその目で見た人、坑夫やトロッコや石炭を実際に見たという人は、今ではほとんど居ないでしょうね。
私が子供の頃は、日本のあちこちに炭坑があって、盛んに石炭を掘り出していました。私の住んでいた町の近くにも、大きな炭坑がいくつかあって、ボタ山(掘り出した石炭の屑を積み上げた山)をあちこちで見かけたものです。石炭を積み出すための鉄道のレールが炭坑から港まで縦横に走っていて、石炭を積んだおびただしい数の貨車が機関車に引かれてひっきりなしに運ばれていたのです。休日には、炭坑で働く人々や彼らの家族が街にあふれ、それは賑やかなものでした。
私は「炭坑」と書きましたが「炭鉱」という書き方もあります。「炭鉱」は石炭の鉱脈のことです。「炭坑」というと、その鉱脈から石炭を掘り出すために地中深く穴を掘って築いた「坑道」のことになります。海外には、穴を掘らなくても山の斜面などに剥き出しになった鉱脈から石炭を掘り出すことのできる炭鉱がたくさんあります。そういう掘り出し方を「露天掘り」と言います。でも、日本の炭鉱はほとんどが地中深くに埋もれているので、穴を掘り、坑道を縦横に築いて鉱脈にたどり着かなければなりません。ですから、日本の炭鉱のほとんどは「炭坑」だ、ということになります。
石炭は発展途上にあった日本の、産業を支える血液でした。
炭坑で働く人々は、その血液を産業界に、社会に、日々送り出していたのです。彼らの支えなくして、近代の日本はありえなかったでしょう。
日本の炭坑夫たちは、爆発や落盤の危険と隣り合わせの、深く危険な地の底で、そんな誇りとプライドを胸に秘めて、命がけで働いていたのです。
男たちだけではありません。女たちも、子供たちも、いっしょに汗まみれになって、坑道の奥深くで石炭を掘り出していたのです。
この物語の主人公は、百年ほども昔の、そんな「炭坑」と、そこで働く人々です。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月09日
第一章:閉山 その1
<閉山 その1>
新しい世紀、二十世紀が明けて間のない、ある秋の午後。
北海道の暁幌(あけほろ)炭坑、朱鳥(あけどり)坑前の広場。広大な暁幌炭坑の中心である。
秋といっても、もう冬の顔をした風が広場のあちこちを通り抜けて行く。この季節、暁幌は北海道の内陸で、その上、小高い山々に囲まれた盆地だから、寒さの訪れるのもいっそう早い。
広場には多くの人々が神妙な様子で集まっている。
坑夫たち、その家族、事務方、街の人々、役人・・・。
こんなにもたくさんの人たちがここで働いていたのか、とあらためて思わせる。
広場は万余の人々でうめつくされていた。
暁幌炭坑の歴史は古い。正式に会社が設立されて、本格的な採掘が始まってからでも、もう半世紀の歴史を刻んでいる。今は使われていないが、江戸時代から小規模な採掘が行われていた古い坑道もある。
その半世紀の間、幾度かの枯渇の危機はあったものの、暁幌はそのたびに豊かな鉱脈を拓いて良質の石炭を産出しつづけてきたのだ。
世界の良質の石炭の多くは三億年ほど昔、地質年代で言うと「石炭紀」と名づけられた時代に繁茂していた植物が地中で炭化し、化石化したものだ。石炭紀というとジュラ紀とか白亜紀といった恐竜時代よりもはるか昔だ。
日本列島は、北海道も含めて、そのころは海だったから、常識的には良質の石炭鉱脈というものはないはずだ、ということになる。事実、この暁幌も含めて、日本の石炭鉱脈のほとんどは、たった数千万年前の若い層なのだ。
しかし、この地域の火山列島という特質が、激しい地殻変動から生ずる高熱と高圧によって、この若い植物の化石層を短期間で良質の石炭に変えた。
いわば、日本の石炭鉱脈は、もうれつな圧力鍋で作られた即席の石炭なのである。
その分、地中深くに埋もれた鉱脈を見つけ出して、それを掘り出すための坑道を築いてゆくのは、とても困難で危険な仕事だった。
この十数年の間、暁幌の鉱脈が遂に枯れたと思われたことが幾度かあったが、そのたびに、鉱脈の発見と坑道の建設によって危機を救ってきたのは、所長の星直耀(ほし ただてる)男爵と、彼のもとで経験とカンをはたらかせて困難な採掘に挑んできた暁幌叩き上げの坑夫、日下亨(くさか とおる)であった。
朱鳥坑前の広場の中央。広場をうめつくす群集の真中がぽっかりと空いていて、天幕が張ってある。 そこにたたずむ正装の紳士。彼こそ高名な鉱物学者にして鉱山技師、暁幌炭坑の所長、星男爵その人である。
彼が暁幌炭坑の所長に着任してからの十数年は、暁幌の黄金時代だったと言ってもよいだろう。良質の新しい鉱脈を次々と拓いて炭坑の命を保ったのみならず、坑道の改良や作業体制の見直し、設備の刷新などによって、事故は減り、坑夫の作業環境はおおいに改善された。結果として採炭量もみるみる向上していったから、はじめは彼の「改革」に眉をしかめ、設備投資を渋っていた株主連中もおおいに満足することになった。
彼はあらゆる意味でこの炭坑を支えてきた大黒柱であり、暁幌で働く者たち、坑夫はもとより事務員や経営者たちにとっても、そして、一時期は五万人以上にのぼる人口をかかえることになった暁幌の街でさまざまな商売を営む者たち、潤沢な税収にあずかった役場やそこで働く官吏たちにとっても、恩人というに相応しい人物なのである。
彼の前には白い布をかけられたテーブルがあり、その上には二つの箱が置かれている。
もうじきやって来るある瞬間、とても大切で、悲しい瞬間を、彼と彼を取り巻く群衆は待っているのだ。
来た。
遂にそのときが来た。
広場の後方、朱鳥坑のいくつかある縦坑のひとつ、野郎(やろう)縦坑の昇降機(リフト)がうなった。蒸気機関が激しく蒸気を噴出し、サイレンが鳴り響く。いつもなら冷たい耳障りな警笛を事故の知らせかと思うところだが、今日はわびしく、もの悲しく聞こえる。やがて、縦坑を昇降機が昇って来た。
昇降機が止まる。中からトロッコと、数名の坑夫が出て来る。
トロッコを先導するのは、星男爵の片腕として、暁幌を支えつづけてきたもうひとりの男。坑夫頭の日下亨だ。
いつもなら、幾筋ものレールをたくさんのトロッコがやかましい地響きを立てて往き来する広場、仕事を終え坑道から上がってくる坑夫や、これから坑道に降りる坑夫たちでごったがえす広場が、今は秋の風音さえ聴き取れるほどに静かだ。
その静寂の中を、一台のトロッコがレールをきしませながら人々のほうに押されてくる。
群集が道を空ける。
空いた人壁の間を抜けて、トロッコは広場の中央近くまでやってきて止まった。
日下はトロッコから石炭の塊をひとつ採り上げ、星の傍らに歩みよった。暁幌を支えてきたふたりが向き合う。
星が差し伸べた両手に、日下は石炭の塊をそっと置いた。
星はそれを箱のひとつにおさめながら周囲の鉱夫たちに語りかけ始めた。
「ここに、暁幌炭鉱が拓かれたとき最初に掘り出した記念の石炭があります。そして、これが、今日、掘り出した最後の石炭です。」
拓かれてから半世紀近くにわたって豊富で良質な石炭を産出してきた暁幌炭鉱は、遂に閉山のときを迎えたのだ。
この数年の間、いくども鉱脈が尽きたかと思わせたことがあったが、そのたびに星や日下たちの探査によって新しい炭層を見出してきた。しかし、ついに新しい炭層は発見できず、星をはじめ炭坑の責任者たちは閉山を決意したのだった。
「苦しいときも、愉しいときも、私たちは一緒でした。私たちは家族でした。暁幌は、暁幌炭坑は、そんな私たち家族の母でした。その母に、別れを告げる日が、とうとうやって来ました。」
星は箱の蓋を静かに閉じる。
「このふたつの石炭を、私たちは、私たち家族がこの母なる暁幌とともに生きた記念として大切に保管しましょう。今は、母を静かに眠らせ、見送りましょう。ありがとう、暁幌炭坑。どうか安らかに。そして、ありがとう、皆さん。ここで、皆さんと家族であったことはわたくしの誇りです。どうか、幸せに」
ここで幾年もともに過ごしてきた家族、暁幌の子たちは、今日をかぎりにちりじりに散って行くのだ。このまま他の炭坑に移るものもあれば、近隣の町や農場に新たな仕事を求めて去ってゆく者もあるだろう。それでも、彼らはみな、暁幌の子たち、家族なのだと、誰もが思った。
広場を吹きぬけた秋の風が天幕をはたいて、ぱたぱたと音をたてた。
たった今、この瞬間、炭坑(やま)は閉じられたのだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
新しい世紀、二十世紀が明けて間のない、ある秋の午後。
北海道の暁幌(あけほろ)炭坑、朱鳥(あけどり)坑前の広場。広大な暁幌炭坑の中心である。
秋といっても、もう冬の顔をした風が広場のあちこちを通り抜けて行く。この季節、暁幌は北海道の内陸で、その上、小高い山々に囲まれた盆地だから、寒さの訪れるのもいっそう早い。
広場には多くの人々が神妙な様子で集まっている。
坑夫たち、その家族、事務方、街の人々、役人・・・。
こんなにもたくさんの人たちがここで働いていたのか、とあらためて思わせる。
広場は万余の人々でうめつくされていた。
暁幌炭坑の歴史は古い。正式に会社が設立されて、本格的な採掘が始まってからでも、もう半世紀の歴史を刻んでいる。今は使われていないが、江戸時代から小規模な採掘が行われていた古い坑道もある。
その半世紀の間、幾度かの枯渇の危機はあったものの、暁幌はそのたびに豊かな鉱脈を拓いて良質の石炭を産出しつづけてきたのだ。
世界の良質の石炭の多くは三億年ほど昔、地質年代で言うと「石炭紀」と名づけられた時代に繁茂していた植物が地中で炭化し、化石化したものだ。石炭紀というとジュラ紀とか白亜紀といった恐竜時代よりもはるか昔だ。
日本列島は、北海道も含めて、そのころは海だったから、常識的には良質の石炭鉱脈というものはないはずだ、ということになる。事実、この暁幌も含めて、日本の石炭鉱脈のほとんどは、たった数千万年前の若い層なのだ。
しかし、この地域の火山列島という特質が、激しい地殻変動から生ずる高熱と高圧によって、この若い植物の化石層を短期間で良質の石炭に変えた。
いわば、日本の石炭鉱脈は、もうれつな圧力鍋で作られた即席の石炭なのである。
その分、地中深くに埋もれた鉱脈を見つけ出して、それを掘り出すための坑道を築いてゆくのは、とても困難で危険な仕事だった。
この十数年の間、暁幌の鉱脈が遂に枯れたと思われたことが幾度かあったが、そのたびに、鉱脈の発見と坑道の建設によって危機を救ってきたのは、所長の星直耀(ほし ただてる)男爵と、彼のもとで経験とカンをはたらかせて困難な採掘に挑んできた暁幌叩き上げの坑夫、日下亨(くさか とおる)であった。
朱鳥坑前の広場の中央。広場をうめつくす群集の真中がぽっかりと空いていて、天幕が張ってある。 そこにたたずむ正装の紳士。彼こそ高名な鉱物学者にして鉱山技師、暁幌炭坑の所長、星男爵その人である。
彼が暁幌炭坑の所長に着任してからの十数年は、暁幌の黄金時代だったと言ってもよいだろう。良質の新しい鉱脈を次々と拓いて炭坑の命を保ったのみならず、坑道の改良や作業体制の見直し、設備の刷新などによって、事故は減り、坑夫の作業環境はおおいに改善された。結果として採炭量もみるみる向上していったから、はじめは彼の「改革」に眉をしかめ、設備投資を渋っていた株主連中もおおいに満足することになった。
彼はあらゆる意味でこの炭坑を支えてきた大黒柱であり、暁幌で働く者たち、坑夫はもとより事務員や経営者たちにとっても、そして、一時期は五万人以上にのぼる人口をかかえることになった暁幌の街でさまざまな商売を営む者たち、潤沢な税収にあずかった役場やそこで働く官吏たちにとっても、恩人というに相応しい人物なのである。
彼の前には白い布をかけられたテーブルがあり、その上には二つの箱が置かれている。
もうじきやって来るある瞬間、とても大切で、悲しい瞬間を、彼と彼を取り巻く群衆は待っているのだ。
来た。
遂にそのときが来た。
広場の後方、朱鳥坑のいくつかある縦坑のひとつ、野郎(やろう)縦坑の昇降機(リフト)がうなった。蒸気機関が激しく蒸気を噴出し、サイレンが鳴り響く。いつもなら冷たい耳障りな警笛を事故の知らせかと思うところだが、今日はわびしく、もの悲しく聞こえる。やがて、縦坑を昇降機が昇って来た。
昇降機が止まる。中からトロッコと、数名の坑夫が出て来る。
トロッコを先導するのは、星男爵の片腕として、暁幌を支えつづけてきたもうひとりの男。坑夫頭の日下亨だ。
いつもなら、幾筋ものレールをたくさんのトロッコがやかましい地響きを立てて往き来する広場、仕事を終え坑道から上がってくる坑夫や、これから坑道に降りる坑夫たちでごったがえす広場が、今は秋の風音さえ聴き取れるほどに静かだ。
その静寂の中を、一台のトロッコがレールをきしませながら人々のほうに押されてくる。
群集が道を空ける。
空いた人壁の間を抜けて、トロッコは広場の中央近くまでやってきて止まった。
日下はトロッコから石炭の塊をひとつ採り上げ、星の傍らに歩みよった。暁幌を支えてきたふたりが向き合う。
星が差し伸べた両手に、日下は石炭の塊をそっと置いた。
星はそれを箱のひとつにおさめながら周囲の鉱夫たちに語りかけ始めた。
「ここに、暁幌炭鉱が拓かれたとき最初に掘り出した記念の石炭があります。そして、これが、今日、掘り出した最後の石炭です。」
拓かれてから半世紀近くにわたって豊富で良質な石炭を産出してきた暁幌炭鉱は、遂に閉山のときを迎えたのだ。
この数年の間、いくども鉱脈が尽きたかと思わせたことがあったが、そのたびに星や日下たちの探査によって新しい炭層を見出してきた。しかし、ついに新しい炭層は発見できず、星をはじめ炭坑の責任者たちは閉山を決意したのだった。
「苦しいときも、愉しいときも、私たちは一緒でした。私たちは家族でした。暁幌は、暁幌炭坑は、そんな私たち家族の母でした。その母に、別れを告げる日が、とうとうやって来ました。」
星は箱の蓋を静かに閉じる。
「このふたつの石炭を、私たちは、私たち家族がこの母なる暁幌とともに生きた記念として大切に保管しましょう。今は、母を静かに眠らせ、見送りましょう。ありがとう、暁幌炭坑。どうか安らかに。そして、ありがとう、皆さん。ここで、皆さんと家族であったことはわたくしの誇りです。どうか、幸せに」
ここで幾年もともに過ごしてきた家族、暁幌の子たちは、今日をかぎりにちりじりに散って行くのだ。このまま他の炭坑に移るものもあれば、近隣の町や農場に新たな仕事を求めて去ってゆく者もあるだろう。それでも、彼らはみな、暁幌の子たち、家族なのだと、誰もが思った。
広場を吹きぬけた秋の風が天幕をはたいて、ぱたぱたと音をたてた。
たった今、この瞬間、炭坑(やま)は閉じられたのだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月09日
第一章:閉山 その2
<閉山 その2>
「さようなら」
「元気で」
「ありがとう」
「また会おうね。」
「きっと」
月並みな、短い、でも忘れがたい言葉たちがあちこちで交わされる。
人々は互いに挨拶を交わしながら別れを惜しんだ。
広場の中央では、星男爵のもとに会社の幹部や役場の主だった人々、町の有力者たちが入れ替わり立ち代り挨拶に訪れている。
そんな喧騒も半刻もするとおさまり、広場を埋め尽くしていた人々も三々五々散って行った。星は、そんな人々から挨拶を送られ、挨拶を返しながら広場の中央に佇んでいた。
「星さん」
振り返るとかたわらに馴染んだ顔があった。最後の石炭を運んできた坑夫頭の日下亨だ。息子の輝(てらす)を連れている。
「日下さん・・・」
星は、日下をいつもこう呼び、日下には自分を名前で呼ばせた。経営者と坑夫という間ではあったが、日下を部下とか従業員というよりも優秀なパートナーと感じていたからだ。実際、暁幌の現場で培ってきた日下の経験とカンには驚かされることが少なくなかった。星は、むしろ、日下を暁幌の先輩とみなし敬意をもって接してきたのだ。
星は、日下の傍らで帽子をとって自分を見上げている男の子に微笑んだ。
輝(てらす)。今年で十二歳だったか、十三だったか、父親の亨とともに炭坑(やま)に入るようになって一年くらいか。面構えはもう立派な坑夫だな。暁幌炭坑がもっと続いていれば、父親のように優秀な坑夫になって、星の片腕にもなってくれたことだろう。しかし・・・
「あなたたちはまだ残るのかね。あなたほどの腕ならどこの炭坑(やま)でも優遇されるはずだ。紹介状が必要ならいつでも・・・」
「星さん。俺はまだあきらめていませんよ。暁幌はまだ死んじゃいない」
星は日下のカンを信じてきた。事実、今まで幾度もあきらめかけたときに、日下は新しい炭層を探り当ててきた。今も信じている。信じたい。が、今度ばかりは悲観的にならざるをえない。あれだけ徹底的に探査したのだ。
星の表情を見て日下が笑いながら言った。
「いや。星さん。あんたは今度もあきらめが早すぎますよ。いつも言ってるでしょう。頭が良すぎるんですよ、あんたは。俺達よりも目は良く見える。だが、鼻は利かん。でしょう。」
この頑固者に、今は何を言っても無駄だろう。
「暁幌に残るんだね。」
「暁幌は、俺達のお袋なんですよ。お袋はちょいと病気で寝込んじゃいるが、ちゃんと診てやればまた元気になるんです。」
「そうか。がんばりたまえ。いい知らせを待っているよ。」
「そう遠くない日に、いいお知らせができると思いますよ。それまで、元気で待っていてください。また星さんとはご一緒したいと思ってるんです。暁幌がお袋なら、あんたはお袋の恩人なんですからね。」
星は日下に手を差し出した。日下はちょっとためらったが、黒く煤けたままの手で星の手を握り返した。
「ありがとう。この黒い煤こそ、ぼくらの勲章だ。ありがとう」
掌に刻印された黒い勲章の形が滲んで揺れた。その上に涙がひとしずく落ちた。
無言でふたりを見つめていた輝が、星にほほえんでみせた。
広場を見下ろす小高い丘の上に人影があった。広場で別れを惜しんでいる人々の中に、その人影に気付いている者はひとりも居ない。
白い粗末な着物をはおって、長い杖を持った、背の高い頑健そうな老人が、すっくと立って閉山の儀式を見下ろしている。
長く真っ白な髪と髭が、丘を走り抜けてゆく秋風にひとさし舞った。
白い老人は眼下の広場をするどい眼光でひとにらみすると踵を返し、丘の裏手、中腹に残っている古い坑道跡から地下に向かった。
坑道に入ると薄暗い片隅に向かって声をかけた。
「行くぞ。ネル。ここにはもう用はない。」
坑道脇の水溜りに顔を映して遊んでいた白い影が立ち上がって老人を振り返った。幼い女の子。老人と同じような白い粗末なシャツをまとっている。長く、黒い髪。白い肌と白いシャツに映えて、黒髪と瞳がひどく目立つ。年のころは十歳くらいだろうか。
白い少女は何かの歌を口ずさみながら愉しげに白い老人に従う。
ふたつの白い影が古びた坑道の奥に消えていったその後に、何かが羽ばたいた。
風音だったかもしれないが、大きな白い影が宙を舞ったように見えた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「さようなら」
「元気で」
「ありがとう」
「また会おうね。」
「きっと」
月並みな、短い、でも忘れがたい言葉たちがあちこちで交わされる。
人々は互いに挨拶を交わしながら別れを惜しんだ。
広場の中央では、星男爵のもとに会社の幹部や役場の主だった人々、町の有力者たちが入れ替わり立ち代り挨拶に訪れている。
そんな喧騒も半刻もするとおさまり、広場を埋め尽くしていた人々も三々五々散って行った。星は、そんな人々から挨拶を送られ、挨拶を返しながら広場の中央に佇んでいた。
「星さん」
振り返るとかたわらに馴染んだ顔があった。最後の石炭を運んできた坑夫頭の日下亨だ。息子の輝(てらす)を連れている。
「日下さん・・・」
星は、日下をいつもこう呼び、日下には自分を名前で呼ばせた。経営者と坑夫という間ではあったが、日下を部下とか従業員というよりも優秀なパートナーと感じていたからだ。実際、暁幌の現場で培ってきた日下の経験とカンには驚かされることが少なくなかった。星は、むしろ、日下を暁幌の先輩とみなし敬意をもって接してきたのだ。
星は、日下の傍らで帽子をとって自分を見上げている男の子に微笑んだ。
輝(てらす)。今年で十二歳だったか、十三だったか、父親の亨とともに炭坑(やま)に入るようになって一年くらいか。面構えはもう立派な坑夫だな。暁幌炭坑がもっと続いていれば、父親のように優秀な坑夫になって、星の片腕にもなってくれたことだろう。しかし・・・
「あなたたちはまだ残るのかね。あなたほどの腕ならどこの炭坑(やま)でも優遇されるはずだ。紹介状が必要ならいつでも・・・」
「星さん。俺はまだあきらめていませんよ。暁幌はまだ死んじゃいない」
星は日下のカンを信じてきた。事実、今まで幾度もあきらめかけたときに、日下は新しい炭層を探り当ててきた。今も信じている。信じたい。が、今度ばかりは悲観的にならざるをえない。あれだけ徹底的に探査したのだ。
星の表情を見て日下が笑いながら言った。
「いや。星さん。あんたは今度もあきらめが早すぎますよ。いつも言ってるでしょう。頭が良すぎるんですよ、あんたは。俺達よりも目は良く見える。だが、鼻は利かん。でしょう。」
この頑固者に、今は何を言っても無駄だろう。
「暁幌に残るんだね。」
「暁幌は、俺達のお袋なんですよ。お袋はちょいと病気で寝込んじゃいるが、ちゃんと診てやればまた元気になるんです。」
「そうか。がんばりたまえ。いい知らせを待っているよ。」
「そう遠くない日に、いいお知らせができると思いますよ。それまで、元気で待っていてください。また星さんとはご一緒したいと思ってるんです。暁幌がお袋なら、あんたはお袋の恩人なんですからね。」
星は日下に手を差し出した。日下はちょっとためらったが、黒く煤けたままの手で星の手を握り返した。
「ありがとう。この黒い煤こそ、ぼくらの勲章だ。ありがとう」
掌に刻印された黒い勲章の形が滲んで揺れた。その上に涙がひとしずく落ちた。
無言でふたりを見つめていた輝が、星にほほえんでみせた。
広場を見下ろす小高い丘の上に人影があった。広場で別れを惜しんでいる人々の中に、その人影に気付いている者はひとりも居ない。
白い粗末な着物をはおって、長い杖を持った、背の高い頑健そうな老人が、すっくと立って閉山の儀式を見下ろしている。
長く真っ白な髪と髭が、丘を走り抜けてゆく秋風にひとさし舞った。
白い老人は眼下の広場をするどい眼光でひとにらみすると踵を返し、丘の裏手、中腹に残っている古い坑道跡から地下に向かった。
坑道に入ると薄暗い片隅に向かって声をかけた。
「行くぞ。ネル。ここにはもう用はない。」
坑道脇の水溜りに顔を映して遊んでいた白い影が立ち上がって老人を振り返った。幼い女の子。老人と同じような白い粗末なシャツをまとっている。長く、黒い髪。白い肌と白いシャツに映えて、黒髪と瞳がひどく目立つ。年のころは十歳くらいだろうか。
白い少女は何かの歌を口ずさみながら愉しげに白い老人に従う。
ふたつの白い影が古びた坑道の奥に消えていったその後に、何かが羽ばたいた。
風音だったかもしれないが、大きな白い影が宙を舞ったように見えた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月14日
第二章:手紙 その1
<第二章:手紙 その1>
星男爵の屋敷は札幌市の郊外にある。
華族の屋敷といってもそんなに豪壮なものではない。木造洋館には違いないが、札幌では珍しいということでもない。敷地も建物も、彼の地位と名声からすれば、むしろ質素なものかもしれない。もっとも、執事に数人の使用人、女中も居れば庭師も居て、彼の屋敷に寄宿して大学に通う書生も居るのだから、質素などといったら一般市民にも本人にも失礼というものだろう。
星直耀。男爵。爵位を頂戴しているのだから上流階級にはちがいない。もっとも、彼の名声はその爵位ゆえではない。
星男爵は札幌の大学で教鞭をとるかたわら、鉱物や鉱山の研究に携わる高名な鉱物学者なのである。そして、彼の名声と地位は、彼が単なる研究者ではなく、その知識と技術と財力を北海道の産業育成に供したことによって確立された。
高名な学者にして北海道有数の実業家。それが「星男爵」という名前に世間が付した見出しである。
星家は士族であった。たいした家柄ではない。維新の時も、きわだった功績をあげたわけではない。ただ、星家は学術の家であった。お家芸で保ってきた家である。そのお家芸とは、平たく言えば「山師」の技術である。鉱山開発や金属の精錬法、あるいは山林の管理。そういった方面の技術やノウハウを伝え、受け継ぎ、現場の奉行として主君に仕えてきた家なのである。だから、維新の前後にも、先代の当主は新政府からその技術とノウハウを見込まれて活躍の場を与えられ、爵位も頂戴することができたのである。
先代の当主も、代々の当主と同じく技術の練磨や新しい技術の吸収には熱心だった。彼は息子を欧州に留学させ、最新の技術を身につけさせようとした。息子は優秀で、欧州でも研究者としての名声を勝ち取って帰って来たのである。
息子は星家を受け継ぐと、東京の地所も屋敷も捨てて、開拓の熱気に沸き立つ北海道に移り住み、知識、技術、財力、人脈のすべてを注ぎ込んで、あちこちで炭坑や鉱山の開発と運営に取り組んだのである。
それが星直耀男爵である。日本という新興国が今日のような繁栄を築き上げることができたのは、彼のような男が居たからだ。
さて、夏の終わりの、ある土曜の朝、星男爵邸に一通の手紙が届いた。
執事が運んできた手紙の差出人を確認した男爵は、思わず椅子から立ちあがり上を向いて目を閉じた。執事は主人の閉じた目から涙がひとすじ流れるのを見て驚いたという。
懐かしい文字たち。
「暁幌」「朱鳥」そして「日下亨」。
何年になる? 四年? いや、もうじき五年だ。
そうか、五年経ったのだ。あの時、彼らと最後の挨拶を交わしてから。
手紙ということは、何か知らせか。
よい知らせだといいが。
亨は字は読めたが、書くのは苦手だと言っていた。
苦労して書いたんだな。練習したのだろうか。
封筒の宛名も差出人も随分と上手に書いたものだ。
いや、もしかしたら輝に書かせたのかも知れない。
そうか、きっとそうだ。
輝も、今ではすっかり立派な若者になっているに違いない。
あ、もしかしたら嫁さんをもらうのか。
あの日、あの時、父親に似ていつもむっつりしていた輝が、笑って見送ってくれた。
ありありと思いだす。
封を切って手紙を読んだ星は、今度は眉を寄せて思案にふけった。
手紙には短く、こう綴られていたのだ。
前略
御知ラセ致シタキコトガアリマス。
御多忙トハ存ジマスガ、急ギ暁幌ニ御出戴キタク。
御予定量リカネマスガ、明日ヨリ、夕刻、息子ヲ暁幌駅ニ御迎ニ遣リマス。
御会イデキルコトヲ心待ニシテオリマス。
草々
五年前、炭坑(やま)を閉めたときの思い出がよみがえってきた。
広場に集まった暁幌の子たち。
別れを惜しむ人々。
坑夫頭として星の片腕だった日下亨。そして、息子の輝。
閉山の日、多くの坑夫が他所の炭坑や近隣の農場に散っていったが、彼は家族とともに暁幌に残ると言っていた。
そうか、まだ暁幌に居たのか。
「あきらめない」
日下はそう言った。
「そう遠くない日によい知らせをする」
とも言った。そして、もう五年経ってしまった。
手紙の様子からは、輝の嫁取りとか、そういう話題ではなさそうだ。
短く、まるで電報のような文面。
日下がこんな具合に「知らせたいこと」といえば新炭層発見のことしかないはずだ。
しかし、鉱山技師としての星の理性と常識は「そんなはずはない」と言う。閉山前にさんざん探査したが見つからなかったのだ。
でも、もし日下が炭層を発見したのだとしたら、いや、炭層の存在を示す確かな証拠だけでも見つけたのだとしたら、彼の性格から言って、こんな風に先ず僕に知らせを寄越すだろう。そして、知らせを寄越す以上、曖昧なきざしや不確かな証拠であるはずはない。
星は身体が熱くなるのを感じた。
こんなに血沸き踊る気分は久しぶりだ。そうさ、まさに五年ぶりだ。暁幌以来、この五年というもの、こんなにわくわくしたことはなかった。
今日は土曜か、週末だな。輝に駅まで何度も足を運ばせるのはまずいな。
星は大きく息を吸い込むと執事を呼んだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
星男爵の屋敷は札幌市の郊外にある。
華族の屋敷といってもそんなに豪壮なものではない。木造洋館には違いないが、札幌では珍しいということでもない。敷地も建物も、彼の地位と名声からすれば、むしろ質素なものかもしれない。もっとも、執事に数人の使用人、女中も居れば庭師も居て、彼の屋敷に寄宿して大学に通う書生も居るのだから、質素などといったら一般市民にも本人にも失礼というものだろう。
星直耀。男爵。爵位を頂戴しているのだから上流階級にはちがいない。もっとも、彼の名声はその爵位ゆえではない。
星男爵は札幌の大学で教鞭をとるかたわら、鉱物や鉱山の研究に携わる高名な鉱物学者なのである。そして、彼の名声と地位は、彼が単なる研究者ではなく、その知識と技術と財力を北海道の産業育成に供したことによって確立された。
高名な学者にして北海道有数の実業家。それが「星男爵」という名前に世間が付した見出しである。
星家は士族であった。たいした家柄ではない。維新の時も、きわだった功績をあげたわけではない。ただ、星家は学術の家であった。お家芸で保ってきた家である。そのお家芸とは、平たく言えば「山師」の技術である。鉱山開発や金属の精錬法、あるいは山林の管理。そういった方面の技術やノウハウを伝え、受け継ぎ、現場の奉行として主君に仕えてきた家なのである。だから、維新の前後にも、先代の当主は新政府からその技術とノウハウを見込まれて活躍の場を与えられ、爵位も頂戴することができたのである。
先代の当主も、代々の当主と同じく技術の練磨や新しい技術の吸収には熱心だった。彼は息子を欧州に留学させ、最新の技術を身につけさせようとした。息子は優秀で、欧州でも研究者としての名声を勝ち取って帰って来たのである。
息子は星家を受け継ぐと、東京の地所も屋敷も捨てて、開拓の熱気に沸き立つ北海道に移り住み、知識、技術、財力、人脈のすべてを注ぎ込んで、あちこちで炭坑や鉱山の開発と運営に取り組んだのである。
それが星直耀男爵である。日本という新興国が今日のような繁栄を築き上げることができたのは、彼のような男が居たからだ。
さて、夏の終わりの、ある土曜の朝、星男爵邸に一通の手紙が届いた。
執事が運んできた手紙の差出人を確認した男爵は、思わず椅子から立ちあがり上を向いて目を閉じた。執事は主人の閉じた目から涙がひとすじ流れるのを見て驚いたという。
懐かしい文字たち。
「暁幌」「朱鳥」そして「日下亨」。
何年になる? 四年? いや、もうじき五年だ。
そうか、五年経ったのだ。あの時、彼らと最後の挨拶を交わしてから。
手紙ということは、何か知らせか。
よい知らせだといいが。
亨は字は読めたが、書くのは苦手だと言っていた。
苦労して書いたんだな。練習したのだろうか。
封筒の宛名も差出人も随分と上手に書いたものだ。
いや、もしかしたら輝に書かせたのかも知れない。
そうか、きっとそうだ。
輝も、今ではすっかり立派な若者になっているに違いない。
あ、もしかしたら嫁さんをもらうのか。
あの日、あの時、父親に似ていつもむっつりしていた輝が、笑って見送ってくれた。
ありありと思いだす。
封を切って手紙を読んだ星は、今度は眉を寄せて思案にふけった。
手紙には短く、こう綴られていたのだ。
前略
御知ラセ致シタキコトガアリマス。
御多忙トハ存ジマスガ、急ギ暁幌ニ御出戴キタク。
御予定量リカネマスガ、明日ヨリ、夕刻、息子ヲ暁幌駅ニ御迎ニ遣リマス。
御会イデキルコトヲ心待ニシテオリマス。
草々
五年前、炭坑(やま)を閉めたときの思い出がよみがえってきた。
広場に集まった暁幌の子たち。
別れを惜しむ人々。
坑夫頭として星の片腕だった日下亨。そして、息子の輝。
閉山の日、多くの坑夫が他所の炭坑や近隣の農場に散っていったが、彼は家族とともに暁幌に残ると言っていた。
そうか、まだ暁幌に居たのか。
「あきらめない」
日下はそう言った。
「そう遠くない日によい知らせをする」
とも言った。そして、もう五年経ってしまった。
手紙の様子からは、輝の嫁取りとか、そういう話題ではなさそうだ。
短く、まるで電報のような文面。
日下がこんな具合に「知らせたいこと」といえば新炭層発見のことしかないはずだ。
しかし、鉱山技師としての星の理性と常識は「そんなはずはない」と言う。閉山前にさんざん探査したが見つからなかったのだ。
でも、もし日下が炭層を発見したのだとしたら、いや、炭層の存在を示す確かな証拠だけでも見つけたのだとしたら、彼の性格から言って、こんな風に先ず僕に知らせを寄越すだろう。そして、知らせを寄越す以上、曖昧なきざしや不確かな証拠であるはずはない。
星は身体が熱くなるのを感じた。
こんなに血沸き踊る気分は久しぶりだ。そうさ、まさに五年ぶりだ。暁幌以来、この五年というもの、こんなにわくわくしたことはなかった。
今日は土曜か、週末だな。輝に駅まで何度も足を運ばせるのはまずいな。
星は大きく息を吸い込むと執事を呼んだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月14日
第二章:手紙 その2
<第二章:手紙 その2>
「急で申し訳ないが、旅支度を頼む。明日朝一番の汽車で発つから急いで頼む・・・そうだな・・・三日程度で済むだろうが・・・遅くとも来週末には帰るよ。いや、連れは無い。正装も要らんよ。あまりかさばらないようにしてくれ。それから、来週の予定がいくつかあったな。・・・ああ、念のため断りを入れておいてくれ。行けないかも知れん。格別、行きたくもないが・・・断り状は書いておくから、月曜にでも届けておいてくれればいい。なぁに、どれもたいした用件じゃない。学会や商工会の会合やなんかだ。・・・いや、切符はいいよ。明日、駅で買う。いやぁ、久しぶりの旅行だ」
執事に旅支度を指示して、会合に出られない旨の断り状を何通かしたためた星は、軽い昼食を済ませると、暁幌で仕事をしていた頃の記録や写真をながめて過ごした。懐かしさと期待や不安がいっしょくたになって、星は身体中に、現場で一心に働いていた頃の活力がよみがえってくるのを感じていた。
ところが、そんな星のほてった身体に水を浴びせるようなことが起きた。
午後の便で、一通の奇妙な手紙が届いたのだ。
サキノテガミハハヤガテンニテ
オコシイタダカナクテヨクナリマシタ
読みにくい。
「先の手紙(の内容)は早合点にて(したがって、暁幌には)お越しいただかなくてよくなりました」
ということらしい。
今度こそ本当に電報のような文面だが、問題は内容だ。
早合点?
知らせたいことが新炭層の発見だったとしたら・・・
やはり亨の早合点だったというのか。
だから、もう来なくてもよいと。
星は、取り戻しかけていた活力が急速にしぼんでゆくのを感じた。
「なんてこった」
やはり、という思いもある。
新炭層など、いまさら出るはずがない。
一方で失望も大きい。
自分の目には見えなくても、日下亨には嗅ぎ取ることができた。
つい先ほどまで、それを信じ、期待して、明日の旅を楽しみにしていたのだ。
星は、執事を呼ぼうとして立ち上がった。
彼には無駄な仕事をさせてしまった。断り状も、まだ間に合うだろう。
しかし、机の上に置かれた封筒と便箋が目に入ったときに、彼のカンが囁いた。
「何かおかしいぞ。」
何かがちぐはぐだ。
彼は気持ちを落ち着かせると、午前と午後の二通の手紙を手にとって見くらべた。
どちらも消印は暁幌。日付も同じ。
午前の方。白い封筒に、飾り気はないが白い便箋が二枚。文面は短いが、一応「前略」と起こしている。あえて二枚封入しているのも礼に適っている。字は、輝が書いたのだろうが、ペンを使った丁寧な書きぶりで漢字と仮名だ。
午後の方。古びた封筒が黄ばんでいる。宛名は誰かに書いてもらったのか、手馴れた事務的な字面だ。便箋は・・・便箋じゃない、何かの古い紙を切り取った感じだ。鉛筆で、字を書きなれない者が仮名だけで綴っている。こちらは亨が急いで書いたという可能性もなくはないが、亨はぶきっちょでも乱暴な手紙を書くような性格ではあるまい。それに、こんな取り消しの手紙を書くくらいなら、本当に電報で追伸すればよいのだ。
この手紙は誰が書いた?
誰かが星の暁幌行きを妨害しようとしている?
この考えに思い至ったとき、星にふたたび活力がよみがえってきた。
日下亨たちは新しい炭層を発見したに違いない。
そして、何者かが、五年にわたる彼らの労苦に横槍を入れようとしている。
「こいつは面白くなってきたぞ」
結局、二通目の手紙は、星の好奇心をかえってかきたてることになったのである。
「行かねばならない。そして、用心しなければならない」
念のため、彼は、家人にも周囲にも行く先をはっきりとは告げないことにしたのだが、そのことが、後に彼を窮地に陥れることになる。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「急で申し訳ないが、旅支度を頼む。明日朝一番の汽車で発つから急いで頼む・・・そうだな・・・三日程度で済むだろうが・・・遅くとも来週末には帰るよ。いや、連れは無い。正装も要らんよ。あまりかさばらないようにしてくれ。それから、来週の予定がいくつかあったな。・・・ああ、念のため断りを入れておいてくれ。行けないかも知れん。格別、行きたくもないが・・・断り状は書いておくから、月曜にでも届けておいてくれればいい。なぁに、どれもたいした用件じゃない。学会や商工会の会合やなんかだ。・・・いや、切符はいいよ。明日、駅で買う。いやぁ、久しぶりの旅行だ」
執事に旅支度を指示して、会合に出られない旨の断り状を何通かしたためた星は、軽い昼食を済ませると、暁幌で仕事をしていた頃の記録や写真をながめて過ごした。懐かしさと期待や不安がいっしょくたになって、星は身体中に、現場で一心に働いていた頃の活力がよみがえってくるのを感じていた。
ところが、そんな星のほてった身体に水を浴びせるようなことが起きた。
午後の便で、一通の奇妙な手紙が届いたのだ。
サキノテガミハハヤガテンニテ
オコシイタダカナクテヨクナリマシタ
読みにくい。
「先の手紙(の内容)は早合点にて(したがって、暁幌には)お越しいただかなくてよくなりました」
ということらしい。
今度こそ本当に電報のような文面だが、問題は内容だ。
早合点?
知らせたいことが新炭層の発見だったとしたら・・・
やはり亨の早合点だったというのか。
だから、もう来なくてもよいと。
星は、取り戻しかけていた活力が急速にしぼんでゆくのを感じた。
「なんてこった」
やはり、という思いもある。
新炭層など、いまさら出るはずがない。
一方で失望も大きい。
自分の目には見えなくても、日下亨には嗅ぎ取ることができた。
つい先ほどまで、それを信じ、期待して、明日の旅を楽しみにしていたのだ。
星は、執事を呼ぼうとして立ち上がった。
彼には無駄な仕事をさせてしまった。断り状も、まだ間に合うだろう。
しかし、机の上に置かれた封筒と便箋が目に入ったときに、彼のカンが囁いた。
「何かおかしいぞ。」
何かがちぐはぐだ。
彼は気持ちを落ち着かせると、午前と午後の二通の手紙を手にとって見くらべた。
どちらも消印は暁幌。日付も同じ。
午前の方。白い封筒に、飾り気はないが白い便箋が二枚。文面は短いが、一応「前略」と起こしている。あえて二枚封入しているのも礼に適っている。字は、輝が書いたのだろうが、ペンを使った丁寧な書きぶりで漢字と仮名だ。
午後の方。古びた封筒が黄ばんでいる。宛名は誰かに書いてもらったのか、手馴れた事務的な字面だ。便箋は・・・便箋じゃない、何かの古い紙を切り取った感じだ。鉛筆で、字を書きなれない者が仮名だけで綴っている。こちらは亨が急いで書いたという可能性もなくはないが、亨はぶきっちょでも乱暴な手紙を書くような性格ではあるまい。それに、こんな取り消しの手紙を書くくらいなら、本当に電報で追伸すればよいのだ。
この手紙は誰が書いた?
誰かが星の暁幌行きを妨害しようとしている?
この考えに思い至ったとき、星にふたたび活力がよみがえってきた。
日下亨たちは新しい炭層を発見したに違いない。
そして、何者かが、五年にわたる彼らの労苦に横槍を入れようとしている。
「こいつは面白くなってきたぞ」
結局、二通目の手紙は、星の好奇心をかえってかきたてることになったのである。
「行かねばならない。そして、用心しなければならない」
念のため、彼は、家人にも周囲にも行く先をはっきりとは告げないことにしたのだが、そのことが、後に彼を窮地に陥れることになる。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月14日
第三章:暁幌へ その1
<暁幌へ>
日曜日の早朝、札幌を出た星男爵は、始発の急行で苫小牧に向った。
駅でも列車の中でも、彼は周囲に気を配り、目立たぬように気をつけた。
稚拙とはいえ、あんな手紙の小細工をする輩が居るのだ。誰かが自分を見張っているかもしれない。もっとも、軽い緊張感は快いものだった。星は、生まれて初めての探偵気分を楽しんでいたともいえる。第一「敵」が居るとしたら、星の行く先はとうに分かっているはずだ。
苫小牧から、暁幌行きに乗り換える。かつて、人や石炭を運ぶために一日に何本も通っていた「暁幌線」も、今では午前と午後二本ずつになっていた。午後の便ということもあるのだろうが、車内にもほとんど乗客の姿はない。
老人が幾人かと、幼い子供を連れた母親らしき女性、そして、大きな荷物を傍らに置いた行商人らしい男がひとり・・・。誰もが押し黙って、ばらばらに座っている。車両の端で老人が煙草をくゆらせている。列車が走りながらガタガタとたてる音の合間に時おり子供がたてる短い声が、暗い車内をかえって沈み込ませる。
これが、あの暁幌線か。
夕刻近く、終点の暁幌に着いた。
星は、幾人かの乗客の後から、ゆっくりとホームに降りた。機関車がゆっくりと蒸気を吹き出す音が何かの余韻のようにホームの上を流れてゆく。
車窓から眺めた近隣の様子も寂しいかぎりだったが、駅に降り立った星はいいようのない寂しさに襲われた。かつて、大量の良質の石炭を掘り出し、運び出すために幾万の人々で賑わっていたはずの暁幌の街はすっかりさびれていた。
「街」はもはやそこには無かった。あるのは、かつて立派な目抜き通りだった、だだっ広い人気の無い道の両脇に、かろうじてへばりついている集落だ。何軒かの商店が、廃屋同然の空き家の間に挟まって細々と営業している。
夏だというのに風が冷たい。あの秋の日の冷たい風を思い出す。
暗いな。雲が出てきた。一雨来るか。
駅舎は、古くなってはいたが、まだ立派なものだ。洋風のしっかりした造りで、ちょっとした都会の駅にも負けない規模と設備を持っている。プラットホームも五路線分残っている。ただ、今でも使われているのは一路線分、上り下り兼用の一本だけなのだろう。残りのホームも線路も使われている形跡が無い。レールの上を赤茶けた錆が覆っている。駅舎や設備だけが五年前そのままに残っていることが、かえって今の寂れ方を物語っている。
ホームの改札近くに少年がひとり、ぽつんと立っているのが見える。地味な上着をはおって、帽子を手にもってこちらを見つめている。ホームには他に人影はない。一緒に降りた乗客たちは、いつのまにか駅を出て、それぞれが集落の中に散っていったとみえる。
星は、少年のほうにゆっくりと歩いた。
「星男爵でいらっしゃいますね」
「よくわかったね。君は、輝(てらす)くんだね。」
「はい。男爵様。あ、お荷物を」
星は鞄を少年に預けた。
「五年前にお目にかかっていますし、男爵様はお変わりになっていませんから。本当に、遠いところを、よくお出でくださいました。でも、こんなに早くお出でになるとは思っていませんでした。手紙はいつ?」
「昨日の朝だよ。お父さんの手紙を・・・書いたのは君かな?」
「はい。ぼくが代筆しました。父が、そのほうがよいと言うものですから。じゃあ、男爵様は、本当にすぐにお出でになったんですね。父も喜びます。ありがとうございます」
「お父さんの手紙を読んだら、居ても立ってもいられなくなってね。で、二通目はお父さんが書いたのかな」
「いえ・・・お出ししたのは一通ですが・・・何か?」
「いや、何でもない。私の勘違いだ。ところで・・・」
「はい。男爵様」
「その『男爵様』というのはどうも苦手なんだ。『星』でいいよ」
「はい。ありがとうございます。お疲れでしょう。一息してから行かれますか?」
「君は疲れているのかね?」
「いえ。父が『所長さんに無理はさせるな』と・・・」
「所長さん・・・か。お父さんにとっては、何もかもあの頃のままなんだな。私なら大丈夫だよ。まだ、若い者には負けんさ。お父さんにひとこと言ってやらなけりゃあな。『私だってあの頃のままだ。人を年寄り扱いするな』ってね。すぐに行こう。」
「はい。では、すぐに行きましょう。ご案内します。」
輝と星は改札を出て駅のホールに入った。
かつて、暁幌炭坑が盛んだった頃には、モダンな建築として街にやって来た人々や出発する人々の熱気を包んでいたこの丸天井も、煤けたストーブの残骸のように感じられる。
「今の住まいは、どこら辺かね?」
輝はちょっと怪訝な顔をしたが、すぐに納得したといった顔になって言った。
「朱鳥(あけどり)坑、野郎(やろう)縦坑・・・坑内です」
星は立ち止った。
「何だって? 街じゃないのか。君らは坑内で暮らしてるのか?」
人気のない球形のホールに星の驚いた声が響いた。教会堂のようだ。
「一息してからになさいますか?」
「ふむ。いや・・・すぐに行こう。一雨来そうだしな。君も帽子をかぶりたまえ。風が冷たくなってきた。さあ、行こう」
「はい」
輝がにっこりと笑った。あのときの笑顔そのままに。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
日曜日の早朝、札幌を出た星男爵は、始発の急行で苫小牧に向った。
駅でも列車の中でも、彼は周囲に気を配り、目立たぬように気をつけた。
稚拙とはいえ、あんな手紙の小細工をする輩が居るのだ。誰かが自分を見張っているかもしれない。もっとも、軽い緊張感は快いものだった。星は、生まれて初めての探偵気分を楽しんでいたともいえる。第一「敵」が居るとしたら、星の行く先はとうに分かっているはずだ。
苫小牧から、暁幌行きに乗り換える。かつて、人や石炭を運ぶために一日に何本も通っていた「暁幌線」も、今では午前と午後二本ずつになっていた。午後の便ということもあるのだろうが、車内にもほとんど乗客の姿はない。
老人が幾人かと、幼い子供を連れた母親らしき女性、そして、大きな荷物を傍らに置いた行商人らしい男がひとり・・・。誰もが押し黙って、ばらばらに座っている。車両の端で老人が煙草をくゆらせている。列車が走りながらガタガタとたてる音の合間に時おり子供がたてる短い声が、暗い車内をかえって沈み込ませる。
これが、あの暁幌線か。
夕刻近く、終点の暁幌に着いた。
星は、幾人かの乗客の後から、ゆっくりとホームに降りた。機関車がゆっくりと蒸気を吹き出す音が何かの余韻のようにホームの上を流れてゆく。
車窓から眺めた近隣の様子も寂しいかぎりだったが、駅に降り立った星はいいようのない寂しさに襲われた。かつて、大量の良質の石炭を掘り出し、運び出すために幾万の人々で賑わっていたはずの暁幌の街はすっかりさびれていた。
「街」はもはやそこには無かった。あるのは、かつて立派な目抜き通りだった、だだっ広い人気の無い道の両脇に、かろうじてへばりついている集落だ。何軒かの商店が、廃屋同然の空き家の間に挟まって細々と営業している。
夏だというのに風が冷たい。あの秋の日の冷たい風を思い出す。
暗いな。雲が出てきた。一雨来るか。
駅舎は、古くなってはいたが、まだ立派なものだ。洋風のしっかりした造りで、ちょっとした都会の駅にも負けない規模と設備を持っている。プラットホームも五路線分残っている。ただ、今でも使われているのは一路線分、上り下り兼用の一本だけなのだろう。残りのホームも線路も使われている形跡が無い。レールの上を赤茶けた錆が覆っている。駅舎や設備だけが五年前そのままに残っていることが、かえって今の寂れ方を物語っている。
ホームの改札近くに少年がひとり、ぽつんと立っているのが見える。地味な上着をはおって、帽子を手にもってこちらを見つめている。ホームには他に人影はない。一緒に降りた乗客たちは、いつのまにか駅を出て、それぞれが集落の中に散っていったとみえる。
星は、少年のほうにゆっくりと歩いた。
「星男爵でいらっしゃいますね」
「よくわかったね。君は、輝(てらす)くんだね。」
「はい。男爵様。あ、お荷物を」
星は鞄を少年に預けた。
「五年前にお目にかかっていますし、男爵様はお変わりになっていませんから。本当に、遠いところを、よくお出でくださいました。でも、こんなに早くお出でになるとは思っていませんでした。手紙はいつ?」
「昨日の朝だよ。お父さんの手紙を・・・書いたのは君かな?」
「はい。ぼくが代筆しました。父が、そのほうがよいと言うものですから。じゃあ、男爵様は、本当にすぐにお出でになったんですね。父も喜びます。ありがとうございます」
「お父さんの手紙を読んだら、居ても立ってもいられなくなってね。で、二通目はお父さんが書いたのかな」
「いえ・・・お出ししたのは一通ですが・・・何か?」
「いや、何でもない。私の勘違いだ。ところで・・・」
「はい。男爵様」
「その『男爵様』というのはどうも苦手なんだ。『星』でいいよ」
「はい。ありがとうございます。お疲れでしょう。一息してから行かれますか?」
「君は疲れているのかね?」
「いえ。父が『所長さんに無理はさせるな』と・・・」
「所長さん・・・か。お父さんにとっては、何もかもあの頃のままなんだな。私なら大丈夫だよ。まだ、若い者には負けんさ。お父さんにひとこと言ってやらなけりゃあな。『私だってあの頃のままだ。人を年寄り扱いするな』ってね。すぐに行こう。」
「はい。では、すぐに行きましょう。ご案内します。」
輝と星は改札を出て駅のホールに入った。
かつて、暁幌炭坑が盛んだった頃には、モダンな建築として街にやって来た人々や出発する人々の熱気を包んでいたこの丸天井も、煤けたストーブの残骸のように感じられる。
「今の住まいは、どこら辺かね?」
輝はちょっと怪訝な顔をしたが、すぐに納得したといった顔になって言った。
「朱鳥(あけどり)坑、野郎(やろう)縦坑・・・坑内です」
星は立ち止った。
「何だって? 街じゃないのか。君らは坑内で暮らしてるのか?」
人気のない球形のホールに星の驚いた声が響いた。教会堂のようだ。
「一息してからになさいますか?」
「ふむ。いや・・・すぐに行こう。一雨来そうだしな。君も帽子をかぶりたまえ。風が冷たくなってきた。さあ、行こう」
「はい」
輝がにっこりと笑った。あのときの笑顔そのままに。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月14日
第三章:暁幌へ その2
<暁幌へ その2>
日下輝は、父親の亨に似て、頑健そうな身体つきの立派な少年に育っていた。
あれから五年だとすると、今は十六、七才か。あのまま暁幌が続いていたら、とうに腕のよい坑夫になっているころだ。班長くらいにはなっていて、どこかの現場を任せられるだろう。
考え深そうな目とどこか優しい顔立ち、落ち着いた物腰は母親に似たのだろう。なかなか好い男ぶりだ。もし札幌の星邸に住まわせて学校にでも通わせたら、女中たちや近隣の若い娘たちが放ってはおくまい。そのうち、よい嫁さんでも世話をしてやらなけりゃならんな。
若い者には負けないと言ったものの、星は、駅から炭坑跡がある丘陵に向うゆるい上り坂を三十分ほど歩いたところで少々疲れてきた。
むかしは、いや、五年前はこんなことはなかった。都会生活ですっかり身体がなまってしまったようだ。
小雨が降り出した。思ったとおりだ。
「雨宿りがてら、少し休みましょう」
輝はそう言うと、道の脇の針葉樹の下に入った。
助け舟を出してくれたんだな。
「すまんね。雨が降り出してしまった。以前は、もっと早く登れたんだが・・・」
「いいえ。男爵・・・星さんは、ちっとも遅くありませんよ」
「ありがとう。それにしても・・・」
星は、一息つきながら周囲の景色をながめて胸を衝かれた。
このあたりは、もう炭坑の構内だったあたりだ。
かつて、あちこちの坑道から運び出した石炭を運ぶトロッコや列車がひっきりなしに走りまわり、いたるところに鉄路が敷かれ、地面は炭塵や石炭の屑に覆われて真っ黒になっていた。それが、今は、緑なす草原と耕作地に変貌している。
「緑の大地・・・か。五年でこうなってしまうのか。美しい・・・のかも知れないが、寂しいな」
「はい。年々石炭の痕跡が消えてゆきます。町に出かけたりして、このあたりを通るときは、ぼくも寂しい気分になります」
星は大きく伸びをすると、歩き始めた。
「ありがとう。疲れは取れたよ。待っていても雨は止まんだろう。行こう。朱鳥はもうすぐだろう。それに、ここでじっとしていると、気が滅入りそうだ」
「はい」
ほどなく、ふたりは朱鳥坑前の広場にやってきた。
五年前、万余の人々で埋めつくされていた別れの舞台も、今は古代の劇場跡の遺跡か廃墟のようだ。広場の先の、少し小高くなったあたりに、昇降機を動かしていた蒸気機関の名残が見える。野郎縦坑だ。
「縦坑を降りるのかい? まさか、昇降機は使えないだろうが」
「梯子があるんです」
「なるほど」
縦坑の入口で、輝は持っていたランプに灯りを点けた。
「安全灯は要らんだろうね」
星がにやりと笑って言った。輝も笑った。
安全灯というのは炭坑内での爆発事故を防ぐために工夫されたランプである。かつて、炭坑では、照明のためのランプの裸火が炭層から発生するガスに引火して起こる爆発事故が頻繁に起こった。一八一五年、英国の王立研究所所長だったデーヴィーが、ランプの炎を円筒形の金網で覆った安全灯の開発に成功した。炎を網で覆うことで金網を通るガスが冷却され、引火しにくくなるのだ。以来、安全灯の普及と改良によって、ランプによる爆発事故は減っていったのである。
もっとも、普及にはかなりの期間がかかった。暁幌には、星が所長として暁幌にやってきてからやっと普及した。それ以前には、ある程度ガスが坑内に溜まったころを見計らって、ガス処理担当の坑夫が、松明を持って坑内をはいずりながら小規模な爆発を人為的に起こすことでガスを解消し、大きな爆発を防ぐといった乱暴な方法をとっていたこともあった。ガスは空気よりも軽いので、天井付近に溜まっていくから、ガスの量が少ないうちに、早めに火をつけて散らしてしまえば大きな爆発にはならないのだ。しかし、一歩間違えれば自ら爆発の犠牲者となる。命がけの仕事だった。
ふたりは、梯子を降り始めた。ひとつの梯子は十五メートルほどだ。これが、小さな踊り場ごとに架けられていて、下まではざっと二十ほどの梯子を下らなければならない。かつて昇降機脇にあった非常用の梯子だが、これが、今は唯一の通り道というわけだ。
星は奇妙なことに気がついた。
輝が、踊り場で梯子を乗り換えるたびに、何か警戒するようにランプを差し出して、下の方を確かめているのだ。あの奇妙な手紙のこともあって、星はあたりに気を配りながら暁幌までやって来たのだったが、暁幌について輝に会ってからは、すっかり不安と用心を忘れていた。しかし、輝の様子からは、彼のほうが何かを警戒しているように見える。
半分ほど縦坑を下ったあたりで、下のほうから何か奇妙な音が聴こえてきた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
日下輝は、父親の亨に似て、頑健そうな身体つきの立派な少年に育っていた。
あれから五年だとすると、今は十六、七才か。あのまま暁幌が続いていたら、とうに腕のよい坑夫になっているころだ。班長くらいにはなっていて、どこかの現場を任せられるだろう。
考え深そうな目とどこか優しい顔立ち、落ち着いた物腰は母親に似たのだろう。なかなか好い男ぶりだ。もし札幌の星邸に住まわせて学校にでも通わせたら、女中たちや近隣の若い娘たちが放ってはおくまい。そのうち、よい嫁さんでも世話をしてやらなけりゃならんな。
若い者には負けないと言ったものの、星は、駅から炭坑跡がある丘陵に向うゆるい上り坂を三十分ほど歩いたところで少々疲れてきた。
むかしは、いや、五年前はこんなことはなかった。都会生活ですっかり身体がなまってしまったようだ。
小雨が降り出した。思ったとおりだ。
「雨宿りがてら、少し休みましょう」
輝はそう言うと、道の脇の針葉樹の下に入った。
助け舟を出してくれたんだな。
「すまんね。雨が降り出してしまった。以前は、もっと早く登れたんだが・・・」
「いいえ。男爵・・・星さんは、ちっとも遅くありませんよ」
「ありがとう。それにしても・・・」
星は、一息つきながら周囲の景色をながめて胸を衝かれた。
このあたりは、もう炭坑の構内だったあたりだ。
かつて、あちこちの坑道から運び出した石炭を運ぶトロッコや列車がひっきりなしに走りまわり、いたるところに鉄路が敷かれ、地面は炭塵や石炭の屑に覆われて真っ黒になっていた。それが、今は、緑なす草原と耕作地に変貌している。
「緑の大地・・・か。五年でこうなってしまうのか。美しい・・・のかも知れないが、寂しいな」
「はい。年々石炭の痕跡が消えてゆきます。町に出かけたりして、このあたりを通るときは、ぼくも寂しい気分になります」
星は大きく伸びをすると、歩き始めた。
「ありがとう。疲れは取れたよ。待っていても雨は止まんだろう。行こう。朱鳥はもうすぐだろう。それに、ここでじっとしていると、気が滅入りそうだ」
「はい」
ほどなく、ふたりは朱鳥坑前の広場にやってきた。
五年前、万余の人々で埋めつくされていた別れの舞台も、今は古代の劇場跡の遺跡か廃墟のようだ。広場の先の、少し小高くなったあたりに、昇降機を動かしていた蒸気機関の名残が見える。野郎縦坑だ。
「縦坑を降りるのかい? まさか、昇降機は使えないだろうが」
「梯子があるんです」
「なるほど」
縦坑の入口で、輝は持っていたランプに灯りを点けた。
「安全灯は要らんだろうね」
星がにやりと笑って言った。輝も笑った。
安全灯というのは炭坑内での爆発事故を防ぐために工夫されたランプである。かつて、炭坑では、照明のためのランプの裸火が炭層から発生するガスに引火して起こる爆発事故が頻繁に起こった。一八一五年、英国の王立研究所所長だったデーヴィーが、ランプの炎を円筒形の金網で覆った安全灯の開発に成功した。炎を網で覆うことで金網を通るガスが冷却され、引火しにくくなるのだ。以来、安全灯の普及と改良によって、ランプによる爆発事故は減っていったのである。
もっとも、普及にはかなりの期間がかかった。暁幌には、星が所長として暁幌にやってきてからやっと普及した。それ以前には、ある程度ガスが坑内に溜まったころを見計らって、ガス処理担当の坑夫が、松明を持って坑内をはいずりながら小規模な爆発を人為的に起こすことでガスを解消し、大きな爆発を防ぐといった乱暴な方法をとっていたこともあった。ガスは空気よりも軽いので、天井付近に溜まっていくから、ガスの量が少ないうちに、早めに火をつけて散らしてしまえば大きな爆発にはならないのだ。しかし、一歩間違えれば自ら爆発の犠牲者となる。命がけの仕事だった。
ふたりは、梯子を降り始めた。ひとつの梯子は十五メートルほどだ。これが、小さな踊り場ごとに架けられていて、下まではざっと二十ほどの梯子を下らなければならない。かつて昇降機脇にあった非常用の梯子だが、これが、今は唯一の通り道というわけだ。
星は奇妙なことに気がついた。
輝が、踊り場で梯子を乗り換えるたびに、何か警戒するようにランプを差し出して、下の方を確かめているのだ。あの奇妙な手紙のこともあって、星はあたりに気を配りながら暁幌までやって来たのだったが、暁幌について輝に会ってからは、すっかり不安と用心を忘れていた。しかし、輝の様子からは、彼のほうが何かを警戒しているように見える。
半分ほど縦坑を下ったあたりで、下のほうから何か奇妙な音が聴こえてきた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月14日
第三章:暁幌へ その3
<暁幌へ その3>
「誰か上がって来ます」
踊り場に立った輝が言った。
続いて踊り場に着いた星が下のほうに注意を向けて首を傾げた。
「口笛のようだが・・・」
口笛だ。何か民謡のような、単調だが耳なじみのよい節だ。
輝がほっとしたような声で嬉しそうに言った。
「ああ。アキラ。瑛ですよ」
「瑛?」
「月岡(つきおか)瑛(あきら)です」
「とにかく、ここで待とう。坑は上り優先だからな」
「はい」
輝は下に向って呼びかけた。
「おおい。アキラーッ」
口笛が止んだ。そして、すぐに下から明るい声が響いた。
「テラス? 輝かぁ。よかったぁ。今行くよぉ」
ぎしぎしと梯子がきしむ音がする。ぐいぐいと上って来るのだろう。坑道の底がほの明るくなってきたかと思うと、元気のよい人影が、ふたりの待っている踊り場に飛びあがってきた。
「輝ぅ! 小屋まで行ったら『居ない』っていうんでがっかりして帰るとこだったんだ。ここで会えてよかったよ。っと・・・ええっと」
ここまでいっきにしゃべってから、瑛は輝のかたわらの人影に気付いた。
「星さんだよ。瑛」
「星さん・・・って男爵様!? じゃ迎えに行ったお客様って・・・」
「思い出したよ。月岡瑛くん。日下家に居た、あの、歌のうまい子だろう」
星は思い出した。
月岡瑛。陽気で、歌や昔話の好きな利発な子供だった。早くに両親を落盤事故で失い、日下亨が親代わりになった。輝と瑛は日下家で兄弟のように育ったのだ。
「こいつはお見逸れ・・・、失礼いたしました。男爵様!」
「ははは。『男爵様』はやめてくれ。『星』でいいよ。そう輝くんにも言ったんだ」
「お目にかかれて光栄です。こりゃあ、素敵な新聞だ。苫小牧の連中にも知らせてやらなくちゃあ。男爵・・・星さんがいらしたと聞いたら喜びますよ。みんな、あなたを忘れはしませんから」
「うれしいね。だが・・・すまないが、今回は、つまり『おしのび』なんだ。ちょっと仕事がらみでね。また近いうちに来るから、そのときには皆のところにも顔を出すよ」
「了解いたしました。こう見えても口は堅いんですよ。でも、次にいらっしゃるときはきっと」
「ああ、ぼくも皆を忘れたりしたことはないよ。今は苫小牧に居るのかい?」
「はい。農場で働いてます。苫小牧あたりには、昔の仲間がけっこう居るんですよ。農場とか、漁師やってるのも居ます」
このまま話がはずみそうだな。
「瑛。ぼくに用だって?」
「あ。そうだ。祭りがあるんだ。苫小牧で。たまには出てこないか? ぼくも歌うんだ」
「だめだよ。今日は星さんと、親父と大事な話があるんだ」
「来週だよ。来週。星さんもいかがですか? 皆にも会えますよ。来週まではいらっしゃらないんですか?」
「残念だな。週末前には帰らなけりゃならないんだ」
「それは残念です。で、輝。来週だよ。出て来いよ」
「わかった。行くよ」
「約束だぞ。ここだけの話、お前に会いたがってる娘っこがわんさと居るんだ」
「冗談はよせよ」
「輝が来るぞって言って、来なけりゃ俺がとっちめられるってことさ。約束だぞ」
「わかった。約束するよ」
「じゃ。ええっと、星さん。お会いできて、本当に嬉しかったです。また、近いうちに是非いらしてください」
瑛は星に深々とお辞儀すると、ぐいぐいと梯子を上って行った。
「そうか、彼は苫小牧の農場で働いているのか」
「瑛も言ってましたけど、苫小牧には、暁幌で働いていた人たちがずいぶんと住んでいます。他所の炭坑(やま)に移ったものも多いですけど、瑛なんかは、暁幌からあまり離れたくないんですよ」
「せっかく炭坑夫として磨いた腕や経験がもったいないな」
「暁幌はいい炭坑(やま)だったんですよ。できれば、星さんとまた一緒にやりたいんです。父もそうです」
「暁幌がまた・・・お父さんの用事というのも、そのことと関係があるのかな?」
「それは・・・父からお話したほうが」
「わかった。そうだな、帰りに時間があったら苫小牧にも寄ってみよう」
「みんな喜びますよ。きっと」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「誰か上がって来ます」
踊り場に立った輝が言った。
続いて踊り場に着いた星が下のほうに注意を向けて首を傾げた。
「口笛のようだが・・・」
口笛だ。何か民謡のような、単調だが耳なじみのよい節だ。
輝がほっとしたような声で嬉しそうに言った。
「ああ。アキラ。瑛ですよ」
「瑛?」
「月岡(つきおか)瑛(あきら)です」
「とにかく、ここで待とう。坑は上り優先だからな」
「はい」
輝は下に向って呼びかけた。
「おおい。アキラーッ」
口笛が止んだ。そして、すぐに下から明るい声が響いた。
「テラス? 輝かぁ。よかったぁ。今行くよぉ」
ぎしぎしと梯子がきしむ音がする。ぐいぐいと上って来るのだろう。坑道の底がほの明るくなってきたかと思うと、元気のよい人影が、ふたりの待っている踊り場に飛びあがってきた。
「輝ぅ! 小屋まで行ったら『居ない』っていうんでがっかりして帰るとこだったんだ。ここで会えてよかったよ。っと・・・ええっと」
ここまでいっきにしゃべってから、瑛は輝のかたわらの人影に気付いた。
「星さんだよ。瑛」
「星さん・・・って男爵様!? じゃ迎えに行ったお客様って・・・」
「思い出したよ。月岡瑛くん。日下家に居た、あの、歌のうまい子だろう」
星は思い出した。
月岡瑛。陽気で、歌や昔話の好きな利発な子供だった。早くに両親を落盤事故で失い、日下亨が親代わりになった。輝と瑛は日下家で兄弟のように育ったのだ。
「こいつはお見逸れ・・・、失礼いたしました。男爵様!」
「ははは。『男爵様』はやめてくれ。『星』でいいよ。そう輝くんにも言ったんだ」
「お目にかかれて光栄です。こりゃあ、素敵な新聞だ。苫小牧の連中にも知らせてやらなくちゃあ。男爵・・・星さんがいらしたと聞いたら喜びますよ。みんな、あなたを忘れはしませんから」
「うれしいね。だが・・・すまないが、今回は、つまり『おしのび』なんだ。ちょっと仕事がらみでね。また近いうちに来るから、そのときには皆のところにも顔を出すよ」
「了解いたしました。こう見えても口は堅いんですよ。でも、次にいらっしゃるときはきっと」
「ああ、ぼくも皆を忘れたりしたことはないよ。今は苫小牧に居るのかい?」
「はい。農場で働いてます。苫小牧あたりには、昔の仲間がけっこう居るんですよ。農場とか、漁師やってるのも居ます」
このまま話がはずみそうだな。
「瑛。ぼくに用だって?」
「あ。そうだ。祭りがあるんだ。苫小牧で。たまには出てこないか? ぼくも歌うんだ」
「だめだよ。今日は星さんと、親父と大事な話があるんだ」
「来週だよ。来週。星さんもいかがですか? 皆にも会えますよ。来週まではいらっしゃらないんですか?」
「残念だな。週末前には帰らなけりゃならないんだ」
「それは残念です。で、輝。来週だよ。出て来いよ」
「わかった。行くよ」
「約束だぞ。ここだけの話、お前に会いたがってる娘っこがわんさと居るんだ」
「冗談はよせよ」
「輝が来るぞって言って、来なけりゃ俺がとっちめられるってことさ。約束だぞ」
「わかった。約束するよ」
「じゃ。ええっと、星さん。お会いできて、本当に嬉しかったです。また、近いうちに是非いらしてください」
瑛は星に深々とお辞儀すると、ぐいぐいと梯子を上って行った。
「そうか、彼は苫小牧の農場で働いているのか」
「瑛も言ってましたけど、苫小牧には、暁幌で働いていた人たちがずいぶんと住んでいます。他所の炭坑(やま)に移ったものも多いですけど、瑛なんかは、暁幌からあまり離れたくないんですよ」
「せっかく炭坑夫として磨いた腕や経験がもったいないな」
「暁幌はいい炭坑(やま)だったんですよ。できれば、星さんとまた一緒にやりたいんです。父もそうです」
「暁幌がまた・・・お父さんの用事というのも、そのことと関係があるのかな?」
「それは・・・父からお話したほうが」
「わかった。そうだな、帰りに時間があったら苫小牧にも寄ってみよう」
「みんな喜びますよ。きっと」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月14日
第三章:暁幌へ その4
<暁幌へ その4>
ふたりは、また梯子を下りはじめた。
最後の梯子を下りると、広い坑道にたどり着いた。
ここから、朱鳥坑を奥へ進む。
「君らが住んでいるのは、もしかしたら、この先にあった管理棟かい?」
「はい。管理棟が、今はぼくらの家です」
「あそこなら、水場も換気口もあるし、たしかに住居としても十分だが・・・」
この坑道も、かつてはいたるところに炭層があったし、あちこちに小さな小屋や倉庫、管理棟などがあったのだが、今はがらんとした洞穴のようになっている。そう、かつては、馬も炭坑内の重要な運搬手段だったから、厩だってあった。ランプの明かりくらいでは天井が見えないくらい広いところだってある。
今は日下家の住まいとなっている旧管理棟に向かう道すがら、輝は相変わらずランプを前後にかざしながら何かを気にかけている。
星は思い切って聞いてみた。
「何か気になるのかい? 他に誰か居るのかね?」
盗賊の類が、廃坑などを隠れ家にしていることは、ままあることだ。
「いえ。後でお話しますけど、何だか・・・」
そのとき、彼らの頭上でかすかに何かの気配がした。
「危ない!」
輝がとっさに星を壁際に押した。
「おっと・・・」
ドスン。
坑道の中ほどに何かが落ちた。
ぱらぱらと小石と砂が壁をつたって星たちの頭に降ってくる。
ふたりは、しばらく壁際でじっと息を殺していた。
静かだ。先ほど感じられた気配ももう感じない。
輝はゆっくりと壁から離れると、手にしたランプを頭上に、それから坑道の中央に向けた。
人の頭ほどもある大きな石が坑道の中ほどに落ちている。
あたりの様子から、これが、さっき彼らの頭上に落ちてきたものに違いない。
「だいぶ・・・壁や天井が緩んでいるとみえる。こんなものが落ちてくるなんて・・・」
「落ちた?」
「輝君?」
「落ちたんでしょうか」
「どういう意味かね?」
「自然に落ちたんなら、あんな風にぼくらに向かって・・・」
「向かって? そうか・・・小石は壁際をつたって落ちてきた・・・あの石は坑道の真ん中に向かって・・・」
「飛んできたように思えました。ぼくには・・・」
「輝君。さっきの話だが・・・この坑道に、他に誰か居るのかね。そんな気配や、何か怪しいことでも起きているのかね?」
「わかりません。ただ・・・このところ、なんだか誰かに見られているような、見張られているような感じなんです。坑道の奥で灯りらしいものがチラチラするのを見たこともありました。ぼくら以外に、ここに居る者なんて居ないはずなんですけど」
「これまでにも、こんなことがあったのかね?」
「いいえ。気配や灯りはありましたけど、何かを仕掛けてきたのは初めてです」
「仕掛けてきた・・・か。お父さんは何と言ってるんだね」
「父は、気のせいだろうと・・・」
「すると、あの手紙もそうかな」
「手紙? ですか? そういえば、二通目の手紙とかおっしゃいましたね」
「ここで長話というのも気味が悪いな。まずは急ごう」
「そうですね」
ふたりは先を急いだ。
今度は、輝だけでなく、星も前後に気を配りながら、黙って歩き続けた。
あの手紙の件といい、今回の落石といい、どうやら星が暁幌に来ることを喜ばない何者かが居るらしいことは確かだ。今の落石は脅しだろうか? それとも、星の命を狙ったものなのだろうか?
前方に灯りが見えてきた。
チラチラしていない。落ち着いた、暖かい灯りだ。
かつて管理棟だった日下家の小屋の灯りだった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
ふたりは、また梯子を下りはじめた。
最後の梯子を下りると、広い坑道にたどり着いた。
ここから、朱鳥坑を奥へ進む。
「君らが住んでいるのは、もしかしたら、この先にあった管理棟かい?」
「はい。管理棟が、今はぼくらの家です」
「あそこなら、水場も換気口もあるし、たしかに住居としても十分だが・・・」
この坑道も、かつてはいたるところに炭層があったし、あちこちに小さな小屋や倉庫、管理棟などがあったのだが、今はがらんとした洞穴のようになっている。そう、かつては、馬も炭坑内の重要な運搬手段だったから、厩だってあった。ランプの明かりくらいでは天井が見えないくらい広いところだってある。
今は日下家の住まいとなっている旧管理棟に向かう道すがら、輝は相変わらずランプを前後にかざしながら何かを気にかけている。
星は思い切って聞いてみた。
「何か気になるのかい? 他に誰か居るのかね?」
盗賊の類が、廃坑などを隠れ家にしていることは、ままあることだ。
「いえ。後でお話しますけど、何だか・・・」
そのとき、彼らの頭上でかすかに何かの気配がした。
「危ない!」
輝がとっさに星を壁際に押した。
「おっと・・・」
ドスン。
坑道の中ほどに何かが落ちた。
ぱらぱらと小石と砂が壁をつたって星たちの頭に降ってくる。
ふたりは、しばらく壁際でじっと息を殺していた。
静かだ。先ほど感じられた気配ももう感じない。
輝はゆっくりと壁から離れると、手にしたランプを頭上に、それから坑道の中央に向けた。
人の頭ほどもある大きな石が坑道の中ほどに落ちている。
あたりの様子から、これが、さっき彼らの頭上に落ちてきたものに違いない。
「だいぶ・・・壁や天井が緩んでいるとみえる。こんなものが落ちてくるなんて・・・」
「落ちた?」
「輝君?」
「落ちたんでしょうか」
「どういう意味かね?」
「自然に落ちたんなら、あんな風にぼくらに向かって・・・」
「向かって? そうか・・・小石は壁際をつたって落ちてきた・・・あの石は坑道の真ん中に向かって・・・」
「飛んできたように思えました。ぼくには・・・」
「輝君。さっきの話だが・・・この坑道に、他に誰か居るのかね。そんな気配や、何か怪しいことでも起きているのかね?」
「わかりません。ただ・・・このところ、なんだか誰かに見られているような、見張られているような感じなんです。坑道の奥で灯りらしいものがチラチラするのを見たこともありました。ぼくら以外に、ここに居る者なんて居ないはずなんですけど」
「これまでにも、こんなことがあったのかね?」
「いいえ。気配や灯りはありましたけど、何かを仕掛けてきたのは初めてです」
「仕掛けてきた・・・か。お父さんは何と言ってるんだね」
「父は、気のせいだろうと・・・」
「すると、あの手紙もそうかな」
「手紙? ですか? そういえば、二通目の手紙とかおっしゃいましたね」
「ここで長話というのも気味が悪いな。まずは急ごう」
「そうですね」
ふたりは先を急いだ。
今度は、輝だけでなく、星も前後に気を配りながら、黙って歩き続けた。
あの手紙の件といい、今回の落石といい、どうやら星が暁幌に来ることを喜ばない何者かが居るらしいことは確かだ。今の落石は脅しだろうか? それとも、星の命を狙ったものなのだろうか?
前方に灯りが見えてきた。
チラチラしていない。落ち着いた、暖かい灯りだ。
かつて管理棟だった日下家の小屋の灯りだった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月22日
第四章:発見 その1
<発見 その1>
かつて管理棟だった小屋の窓から、人間の灯りがゆったりともれている。
小屋の横から、ふわっと光の絨毯が押し出されたように見えた。小屋の戸口が開いたのだ。光の絨毯の上に、しっかりした足取りで人影が立った。
「日下さん!」
「所長さん。星さん・・・お待ちしてましたよ」
「私が今日着くと?」
「え? あぁ。ははは。お声が聞こえたものでね。わたしの耳も鼻も、まだまだ利きますんでね。所長さんのお声も変わらない」
「なるほど。そりゃそうだ。今の坑内なら、人声なんかはつつぬけだな」
「そのうち、脇に立ってるやつと話すにも声を張りあげなくっちゃならなくなりますよ。昔みたいにね」
星が手を差し出した。日下がその手を握り返した。
「この手もすっかりきれいになっちまいましたがね。なぁに、また、すぐに煤だらけにしてみせまさぁね」
星は日下の手を握ったまま、日下の目をじっと見た。
「そうか。ついに見つけたのかね。そうかもしれないと・・・」
「まぁ、話は中で。それに、まず晩飯にしませんか? ちょっと早いが・・・食事は」
「まだだよ。ここまで雨の中を歩いてきたので、実はすっかり腹ペコでね」
「雨?」
日下は、星を小屋の中に招きいれながらつぶやいた。
「そうか。『上』は雨か・・・」
「父さん。ぼくも話があるんだ」
「輝(てらす)。ついさっき、瑛(あきら)がお前を訪ねてきたぞ」
「縦坑で会ったよ。来週の祭りに誘ってくれたんだ」
「あいつは・・・どうやら『上』のほうが性に合ってるんだろうな」
「私も、そうかも知れんよ」
「わたしらのほうが変わってるんでしょうがね、所長さん。でも、わたしらは、暁幌から離れるわけにはいかないんですよ。暁幌が、お袋さんが生きている限りはね。でも、この際、言わせていただきますがね、わたしらの暁幌を素晴らしいお袋さんにしてくれたのは、所長さん、あんたなんですよ。言ってみれば、わたしらを変わり者にしたのは、他でもない、所長さん、あんたですよ」
日下が笑った。
「お帰り。ようこそ、いらっしゃい。お久しぶりですね。さぁ、こちらですよ」
日下亨の妻、輝の母、円(まどか)が三人を食卓に誘(いざな)った。
かつての管理棟は、今ではすっかり快適な住居に改装されていた。
水場からポンプでくみ上げる水は上質の地下水だったし、換気口からは新鮮な空気が常に供給されている。亨が「上」と呼んでいる地上の風雨も、ここにはやって来ない。地下の坑道が、採掘現場だったころは、いろいろなものが生み出す熱気が坑内に澱んで、暑苦しい過酷な環境だったが、今は、一年を通して気温や湿度が安定した蔵の中のようになっている。強いて言えば、灯りがいつも必要な点が不便といえば不便だったが、他の点では、地上以上に健康的で快適な環境だと言っていいかもしれない。
星は、日下家で円の手料理を存分に味わった。
「まだ旬じゃないので、今日は干物を使ったんですけど。もう少し寒い時期になったら刺身でもおいしくいただけるんですよ」
苫小牧で採れる、大きなハマグリを思わせるホッキ貝の干物を炊き込んだ飯は、干物とはいえ、貝の旨みを十分に味わうことができた。地元で採れた野菜と鮭を、近くの牧場から朝仕入れてきた牛乳で煮込んだだけの鍋もうまかった。
食後、星が持参した紅茶を淹れて、四人は、昔話に花を咲かせながらしばらく寛いだ。
「さて。そろそろ本題に入りたいんだが・・・その前に、確かめたいことがあるんだ」
星が、口火を切った。
「確かめたいこと?」
「私は、君からの手紙を一昨日受け取った」
星は、最初に届いた手紙を取り出してテーブルの上に置いた。それから、もう一通の手紙を並べて置いた。
「君が出したのは一通だね。君の手紙の後で、これが届いた」
日下は、その手紙を取って文面を見た。
「なんだ・・・こりゃあ。わたしが出したもんじゃないですよ」
「『来なくていい』とある。君は、誰かに、私を招いたことを話したかね?」
「いいえ。このことは・・・まず、あなたにお知らせして、確かめていただかなけりゃなりませんから。誰にも言いやしませんよ。まだ秘密なんです。 輝? お前、誰かに話したりしたか?」
「いいえ。誰にも」
「誰かが、今回のことを知っている。そして、それを邪魔しようとしているんだ」
「いったい・・・誰が」
「輝くん。君も、お父さんに伝えておくことがあるんじゃないか」
「何だ?」
「星さんをお連れする途中、縦坑からここに向かう途中、あの三叉路のあたりで、何者かが岩を投げ落としたんだ」
「投げ落とした? 落ちてきたんじゃないのか?」
「いや。日下さん。あれは、人為的に投げ落とされたんだと思うよ。輝くんが私を壁際に押してくれたから助かったが、危ないところだった」
「何ですって!」
「父さん。前から言ってるように、この坑内には、ぼくら以外に誰か居るんだよ。この変な手紙も、岩も、もしかしたら」
「とにかく・・・日下さん。君の『知らせたいこと』を他の誰かも知っている。私を招いたことも。そして、その『誰か』は、このことを不愉快に思っている。これだけは確かだよ。 ・・・で、その『誰か』を怒らせたことっていうのは『新炭層発見』なんだね」
日下は座りなおして、ゆっくりと言った。
「そうです。だから、星さん、あなたをお呼びしました」
「どこにあった。どの程度の炭層なんだね。採掘はどのくらい・・・」
星が腰を浮かせた。
「まぁ、待ってください。順を追ってお話しますから」
「すまん。どうも、僕のほうが熱が入ってしまったな」
「正確に言うと、発見したのは炭層ではなく、炭層が、それも良質の炭層があるという証拠です」
「証拠?」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
かつて管理棟だった小屋の窓から、人間の灯りがゆったりともれている。
小屋の横から、ふわっと光の絨毯が押し出されたように見えた。小屋の戸口が開いたのだ。光の絨毯の上に、しっかりした足取りで人影が立った。
「日下さん!」
「所長さん。星さん・・・お待ちしてましたよ」
「私が今日着くと?」
「え? あぁ。ははは。お声が聞こえたものでね。わたしの耳も鼻も、まだまだ利きますんでね。所長さんのお声も変わらない」
「なるほど。そりゃそうだ。今の坑内なら、人声なんかはつつぬけだな」
「そのうち、脇に立ってるやつと話すにも声を張りあげなくっちゃならなくなりますよ。昔みたいにね」
星が手を差し出した。日下がその手を握り返した。
「この手もすっかりきれいになっちまいましたがね。なぁに、また、すぐに煤だらけにしてみせまさぁね」
星は日下の手を握ったまま、日下の目をじっと見た。
「そうか。ついに見つけたのかね。そうかもしれないと・・・」
「まぁ、話は中で。それに、まず晩飯にしませんか? ちょっと早いが・・・食事は」
「まだだよ。ここまで雨の中を歩いてきたので、実はすっかり腹ペコでね」
「雨?」
日下は、星を小屋の中に招きいれながらつぶやいた。
「そうか。『上』は雨か・・・」
「父さん。ぼくも話があるんだ」
「輝(てらす)。ついさっき、瑛(あきら)がお前を訪ねてきたぞ」
「縦坑で会ったよ。来週の祭りに誘ってくれたんだ」
「あいつは・・・どうやら『上』のほうが性に合ってるんだろうな」
「私も、そうかも知れんよ」
「わたしらのほうが変わってるんでしょうがね、所長さん。でも、わたしらは、暁幌から離れるわけにはいかないんですよ。暁幌が、お袋さんが生きている限りはね。でも、この際、言わせていただきますがね、わたしらの暁幌を素晴らしいお袋さんにしてくれたのは、所長さん、あんたなんですよ。言ってみれば、わたしらを変わり者にしたのは、他でもない、所長さん、あんたですよ」
日下が笑った。
「お帰り。ようこそ、いらっしゃい。お久しぶりですね。さぁ、こちらですよ」
日下亨の妻、輝の母、円(まどか)が三人を食卓に誘(いざな)った。
かつての管理棟は、今ではすっかり快適な住居に改装されていた。
水場からポンプでくみ上げる水は上質の地下水だったし、換気口からは新鮮な空気が常に供給されている。亨が「上」と呼んでいる地上の風雨も、ここにはやって来ない。地下の坑道が、採掘現場だったころは、いろいろなものが生み出す熱気が坑内に澱んで、暑苦しい過酷な環境だったが、今は、一年を通して気温や湿度が安定した蔵の中のようになっている。強いて言えば、灯りがいつも必要な点が不便といえば不便だったが、他の点では、地上以上に健康的で快適な環境だと言っていいかもしれない。
星は、日下家で円の手料理を存分に味わった。
「まだ旬じゃないので、今日は干物を使ったんですけど。もう少し寒い時期になったら刺身でもおいしくいただけるんですよ」
苫小牧で採れる、大きなハマグリを思わせるホッキ貝の干物を炊き込んだ飯は、干物とはいえ、貝の旨みを十分に味わうことができた。地元で採れた野菜と鮭を、近くの牧場から朝仕入れてきた牛乳で煮込んだだけの鍋もうまかった。
食後、星が持参した紅茶を淹れて、四人は、昔話に花を咲かせながらしばらく寛いだ。
「さて。そろそろ本題に入りたいんだが・・・その前に、確かめたいことがあるんだ」
星が、口火を切った。
「確かめたいこと?」
「私は、君からの手紙を一昨日受け取った」
星は、最初に届いた手紙を取り出してテーブルの上に置いた。それから、もう一通の手紙を並べて置いた。
「君が出したのは一通だね。君の手紙の後で、これが届いた」
日下は、その手紙を取って文面を見た。
「なんだ・・・こりゃあ。わたしが出したもんじゃないですよ」
「『来なくていい』とある。君は、誰かに、私を招いたことを話したかね?」
「いいえ。このことは・・・まず、あなたにお知らせして、確かめていただかなけりゃなりませんから。誰にも言いやしませんよ。まだ秘密なんです。 輝? お前、誰かに話したりしたか?」
「いいえ。誰にも」
「誰かが、今回のことを知っている。そして、それを邪魔しようとしているんだ」
「いったい・・・誰が」
「輝くん。君も、お父さんに伝えておくことがあるんじゃないか」
「何だ?」
「星さんをお連れする途中、縦坑からここに向かう途中、あの三叉路のあたりで、何者かが岩を投げ落としたんだ」
「投げ落とした? 落ちてきたんじゃないのか?」
「いや。日下さん。あれは、人為的に投げ落とされたんだと思うよ。輝くんが私を壁際に押してくれたから助かったが、危ないところだった」
「何ですって!」
「父さん。前から言ってるように、この坑内には、ぼくら以外に誰か居るんだよ。この変な手紙も、岩も、もしかしたら」
「とにかく・・・日下さん。君の『知らせたいこと』を他の誰かも知っている。私を招いたことも。そして、その『誰か』は、このことを不愉快に思っている。これだけは確かだよ。 ・・・で、その『誰か』を怒らせたことっていうのは『新炭層発見』なんだね」
日下は座りなおして、ゆっくりと言った。
「そうです。だから、星さん、あなたをお呼びしました」
「どこにあった。どの程度の炭層なんだね。採掘はどのくらい・・・」
星が腰を浮かせた。
「まぁ、待ってください。順を追ってお話しますから」
「すまん。どうも、僕のほうが熱が入ってしまったな」
「正確に言うと、発見したのは炭層ではなく、炭層が、それも良質の炭層があるという証拠です」
「証拠?」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月23日
第四章:発見 その2
「石炭ガスです」
日下は、石炭ガスが噴出している場所を見つけた、というのだ。
確かに、石炭ガスは炭層存在の確かな証拠と言える。石炭ガスが噴出しているということは、その岩壁の向こうに炭層があるということになる。
「どこで見つけたんだね」
「この朱鳥坑の奥です。炭坑(やま)を閉める前に、所長さんと一緒にあちこち試掘したり、調査したでしょう。覚えてますか?」
「もちろん覚えてるよ。皆、必死で探したんだ」
「八号試掘坑の奥ですよ」
「何だって。あそこは、君とさんざん調べたはずじゃ・・・」
「そうなんです。わたしも、ガスを見つけたときは驚きましたよ。もう、この五年かけて円や輝と、随分あちこち調べてまわりましたから。それが、試しに八号を少し掘ってみたら・・・『なんで、あの時もう少し』って思いましたね」
「疑うわけじゃないが・・・残存ガスじゃないんだね」
「確かですよ。しっかり噴き出してます。間違いなく、あの奥に、しっかりした炭層があるはずです。それも、すぐのところですよ。でなけりゃ、星さんをお呼びしたりしません。発破を一回かければ、すぐ炭層までたどり着けます。あんたが見えたら・・・」
「君は・・・私に・・・新炭層の発見に立ち合わせてくれるって言うのか。そのために、私を呼んでくれたのか・・・」
日下が、にやりと笑ってみせた。
星は、身体が熱くなるのを感じた。
この男は、すさまじい執念で新炭層を探しあてた。並大抵の苦労ではなかったはずだ。日下亨だけじゃない、妻の円や、まだ若い息子の輝も一緒に、家族でがんばって、やっと見つけたのだ。そして、いよいよ炭層発見という段取りになって、その発見の感動と栄誉をともに分かつために、星をわざわざ呼んだというのだ。その五年の間、星はというと暁幌を離れ、札幌でのんびりと暮らしていたのだ。この栄誉をともに受ける権利が、この私にあるというのか・・・。
「星さん。八号は、ここからすぐですよ。発破は明日として、ガスを、ちゃんと見ておきたいでしょう?」
「君の経験とカンは信じているよ。耳も鼻も昔どおりなんだろう。それに・・・たのもしい跡継ぎも一緒にがんばったんだ」
「でも、星さん。あんたは、その頭と知識であらゆることをつなぎ合わせて、きちんと納得しておきたいはずですよ。でなきゃ、今夜の寝つきが悪いはずだ。昔どおりの『所長さん』ならね」
今度は、星が大笑いした。
「まったく、そのとおりだよ。食後の散歩にちょうどいい。行こう」
三人は簡単な身づくろいをして、八号試掘坑に向かうことにした。円は小屋に残り、三人が帰ってきたら、おそらく催されるであろう、ささやかな酒宴と軽い夜食の準備をしながら待つことにした。
今日のところは、石炭ガスの噴出を確認して、現場の状態を確認し、明日の発破のあたりをつけるにとどめる。日下のカンは確かなものだが、炭層の状態を推定し、どこにどんな発破をかければいいか、そのあたりは、星の技術と、暁幌時代に調べ上げた過去から閉山にいたるまでの全ての炭層や地質構造の知識がものを言う。
亨はツルハシとロープを持った。輝が、脚立と安全灯を手にした。
「安全灯が要るかね?」
「念のためですよ。今日のところは必要ないはずですが。星さん、申し訳ありませんが、そこの鉤棒と、お持ちになったステッキをお願いします」
「ステッキは要らんよ」
「護身用ですよ。ツルハシや鉤棒は、狭いところでは使いにくいでしょう」
「そうだったな。万一のこともある。しかし、奥さんをひとりで小屋に残して大丈夫かね」
「円は大丈夫ですよ。それに、どうやら『誰か』は、わたしらが憎いんじゃない。わたしらが、坑の奥で動き回るのが目障りだということのようですからね。わたしらが注意すれば大丈夫でしょう」
「なるほど。しかし、今日は、早く行って、早く帰ろう」
三人は、八号坑に向けて朱鳥坑を奥へ向かった。
星も、疲れはすっかり回復したし、何よりも「新炭層」と「新暁幌」の実現が確かな手ごたえで近づきつつあることが、彼の足取りを軽くしている。
「所長さん、いや、新暁幌が始まれば、旧暁幌の事実上の経営者で、新炭層の発見者になるあなたは、きっと社長になるでしょう。いや、遠慮されることはありませんよ。あんたでなくて、誰がここを仕切るって言うんです・・・星さん、さっきも言いましたけど、わたしらは朱鳥に腰を据えて、あちこちを調べて回りました」
「しらみつぶしに暁幌じゅうを・・・かい?」
「いいえ。あてずっぽうに調べていったわけじゃないんですよ。星さんが暁幌にいらしてから、わたしは随分と勉強させてもらいました。何度か枯れたと思われたときも、一緒に炭層を探りあてて、それで、あなたとご一緒させていただいてる間に、わかったことがあります」
「私も君に教わったことが随分とあるよ。これは世辞でもなんでもないが、君は、私の師匠だったんだよ」
「それは、買いかぶりすぎですよ。つまり・・・わたしが言いたいのは、わたしらがカンと経験であたりをつける。あなたは、それこそ、わたしらからすれば、まるで関係ないようなところの調査結果や、もう枯れてしまった昔の炭層の記録やらを、もうそれこそ書類の山を眺めて、図面を引く。あなたの図面とわたしらのカンが、最初は関係ないように見える。それが、どこかでこう、その、うまく言えんのですが・・・」
「交差するときに・・・」
「そうです。その、ピンと来て、つながるんですよ。そうすると、きっと見つかった。わたしらは『なんだ、この所長先生はわかってたんだな』って感心したもんです」
「私は、君らが『ピンと来た』ときにはホッとしたもんだよ。間違ってなかったということに確信というか、安心できるのは、そのときなんだ」
「星さん。わたしらには、筋道ってのはわからない、いや、見えないんですよ。経験とかカンとか言いますけどね、わたしもよく鼻とか耳とか言いますけど、違うんですよ、身体が覚えてたり、身体の中から何かが言うんです。言うっていっても言葉じゃないんですがね。だから、若い者にも、ことばで教えるってことがどうもできない。そんなたいそうな事じゃなくてもね、坑内に向かう準備とか、ツルハシを使うコツとか、注意事項とか、そんな当たり前みたいなことどもにしたってそうです。身体で覚えてもらうしかない。もちろん、手順書とか規則とかって言葉もありますけどね。言葉で伝えても伝えた感じがしない。そもそも、わたしにしたところで、言葉で何か教わったとか、覚えたとかじゃないんですよ」
「私には筋道しか見えない。だから、君らの実感が『そうだ』って言ってくれないと不安でしょうがない」
「で、そこなんですよ。あなたの筋道には無駄がない。そのことは、わたしは随分経験したから、それこそ身体で納得してますよ。でも、あなたには確信がない。わたしらのカンってやつは、無駄が多い。やってみなけりゃわからい・・・ってことでね。でも、こうやってりゃ必ず見つかるって確信だけはある。それから、筋道ってのは、たぶん、間違いなく、きちんとやれば大体のところまでは、ちゃんと見える。この『間違いなくきちんとやる』のが難しいんでしょうがね。で、カンは、すごく利くやつと利かないやつが居る。だから、結局、結果なんですよね。やってみなけりゃわからない」
「つまり、かつて、私と一緒に暁幌で探査を繰り返した。その経験が少しは役に立ったということかな。君も、何かを参考に筋道を立ててみた、ということかな」
「そうなんですよ。カンだけであてずっぽうに調べたわけじゃないんですよ。ご一緒したときに教わった探査の手順や、それこそ昔の炭層や採掘の記録、それに、あなたがいらしてからの調査記録は、あの管理棟に残ってましたから、随分参考にさせてもらいました」
「それで、あたりをつけながら調べたんだね」
「はい。二年前からは、資料調べはもっぱら輝にやらせましたがね。それでも、暁幌じゅう調べて、つい、この春までは、炭層の兆しさえ見つかりませんでした」
「そうか。その間、私は札幌で・・・」
「星さんは、ここぞって時にお呼びしようと思ってたんですよ。それまでは、わたしらで頑張ろうってね。で、輝が閉山前の記録を調べてて、あたりの付け方を変えてみようって言うんですよ。試掘しようとしたんだから、わたしらにはわからないが、何か『筋道』があったはずだ、あきらめた理由もあるはずだが、いったん最初の『筋道』に戻ってみようってね」
「輝君が・・・」
輝は黙々と二人の前を歩いている。おそらくは星の体力を気遣ってのことだろうが、時折、振り返って二人の様子を確認しながら、安全灯で周囲を注意深く確認しつつ先導している。
「それで、八号試掘坑ですよ。大当たりでした。いや、筋道はあったはずなんですよね。でも、五年前、なぜか八号ではあたしらのカンとあなたの筋道が・・・」
「交差しなかった・・・か」
「星さん」
「ん?」
「学問ってやつは、わたしらのような仕事にも必要です。わたしはね、つくづくそう思いましたよ」
「君の言う『筋道』を使える、カンも利く、そんな坑夫が必要だね。これからは、そういう時代だよ。学問は、職業や階層に関係なく、誰にだって身に付ける権利がある。いや、身に付けるべきだと思うよ。農夫だって、漁夫だって同じだよ。変な言い方かもしれないが、それが役に立つかどうかは関係ないんだと、私は思うよ。そうだな、学問で得た知識が、直接何かに役立つかどうかは問題じゃなくて、学問を通して何かを探求する『筋道』を経験することが、その人の仕事や人生に、きっと、厚みとか人格を授けてくれる。それが、たとえば、もっと深いカンや新しい成果の肥やしになる・・・」
「輝をどう思われますか」
「新暁幌ができたら・・・彼には私の近くで頑張ってもらおう。私がこれまで学んできた技術や知識を彼に受け継いでもらうよ。それから、時機をみてになるが、彼にはどこかで数年は学問に専念できるように考えてみよう」
「ありがとうございます」
八号試掘坑。
閉山前、朱鳥坑の奥に何箇所か試掘のためにいくつか横坑を掘って、新炭層の探査を行った。そのひとつだ。しかし、五年前は、これらの試掘坑からは、新炭層存在の根拠は見出せなかったのだ。
「ここです・・・が・・・」
やや狭くなった行き止まりだ。目の前に岩壁が立ちはだかっている。五年前の行き止まりから、日下たちが少し掘り進んでいるが、ここが現在の八号最奥ということになる。
日下が首を傾げた。
輝は、安全灯を上に向けて岩壁の天井あたりをにらみつけている。
星もあたりを見回して鼻を鳴らした。
おかしい。
石炭ガスの気配がしないのだ。
石炭ガスは無味無臭というが、経験をつんだ坑夫には微妙な臭いや気配でそれとわかる。しかし、星にも、日下にも、その気配が感じられない。
やはり残存ガスだったのか・・・最後の一パーセント残っていた疑念が一瞬、星の頭をかすめたが、すぐに星の身体が言った。
日下が間違うはずはない。
「輝。ランプを」
「星さん、その鉤棒を・・・」
星は鉤棒を輝に渡した。
輝は、安全灯の蓋を開けて、鉤棒の先に下げた。鉤棒を岩壁の天井のほうへ差し上げる。
石炭ガスがわずかでも漏れていれば、岩壁のどこかに青い炎が見えるか、安全灯の周囲でパチパチと反応が起きるはずだ。
しかし・・・何の反応もない。
「ばかな。そんなはずはない。確かにガスは出ていた。そんな・・・」
日下は岩壁を叩いた。
星は言葉もない。ただ、何か納得できない。こんな結末は筋が通らない。違うか?
しばらく鉤棒先の安全灯で岩壁を照らし続けていた輝が安全灯を降ろしながら言った。
「ちょっと待ってください」
輝は持ってきた脚立を壁に立てると、ツルハシと安全灯を持って壁の上方に上っていった。そして、壁面に安全灯を近づけて注意深く観察していた。
「やっぱり・・・」
「輝君! どうかしたかね」
輝がツルハシの先で壁の一部を軽くつついた。と、途端に、
シュッ!
と、何かが噴き出した。
「あ」
日下と星が同時に声を上げた。
ガスの臭いだ。
輝が下りてきた。
安全灯の蓋を取り、鉤棒で差し上げる。
ボッ!
岩壁の天井近くに青い炎が噴き出した。
「やった!」
石炭ガスは確かに存在した。そして、その勢いは、この壁の向こうに炭層が存在することを確かに示している。
「ご納得がいきましたか?」
日下が笑った。
「もちろんだよ。こいつは素晴らしい。しかし・・・五年前、このすぐ手前まで来てたのに何故・・・」
「まぁ・・・そんなものですよ。人間のすることですからね。それにしても・・・なぜ塞がってたんでしょうね。おかしなこともあるもんだ」
「塞がっていたんじゃありません。塞がれていたんです」
輝が白い塊を見せた。
「何だね、これは・・・」
「漆喰でしょう。これで、ガスの穴を塞いだやつが居ます。しかも・・・ご丁寧に、漆喰の上に炭塵まで撒いてごまかしてました。一部が白く残ってて・・・それで変だと思ったんで・・・」
「件の『誰か』だな」
星が目を細めた。
日下が、その目を見ながら笑った。
「どうします。どうやら、やつらは、我々が新炭層を発見しては、よほど都合が悪いらしい。用心のため、発破はしばらく待ちますか?」
「実はね。あの二通目の手紙以来、何だか闘志が湧いてきてね。これで覚悟が決まったよ」
「だと思いました。そういう目をされましたから」
三人は、岩壁や周辺の状態を確認し、ロープで簡単な計測をして、発破の段取りを確認してから帰路についた。今度は、星と日下が先を歩いた。談笑しながら歩く二人の後を、輝はときおり安全灯をかざして背後の様子を確認しながら進む。
今日、一日の間にいろいろなことがあった。
はっきりしたことがいくつかある。
いよいよ暁幌が再生することになる、ということ。
それから、「誰か」の存在と、その明確な悪意の存在。
そして、我々がその悪意と闘うことになる、ということだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
日下は、石炭ガスが噴出している場所を見つけた、というのだ。
確かに、石炭ガスは炭層存在の確かな証拠と言える。石炭ガスが噴出しているということは、その岩壁の向こうに炭層があるということになる。
「どこで見つけたんだね」
「この朱鳥坑の奥です。炭坑(やま)を閉める前に、所長さんと一緒にあちこち試掘したり、調査したでしょう。覚えてますか?」
「もちろん覚えてるよ。皆、必死で探したんだ」
「八号試掘坑の奥ですよ」
「何だって。あそこは、君とさんざん調べたはずじゃ・・・」
「そうなんです。わたしも、ガスを見つけたときは驚きましたよ。もう、この五年かけて円や輝と、随分あちこち調べてまわりましたから。それが、試しに八号を少し掘ってみたら・・・『なんで、あの時もう少し』って思いましたね」
「疑うわけじゃないが・・・残存ガスじゃないんだね」
「確かですよ。しっかり噴き出してます。間違いなく、あの奥に、しっかりした炭層があるはずです。それも、すぐのところですよ。でなけりゃ、星さんをお呼びしたりしません。発破を一回かければ、すぐ炭層までたどり着けます。あんたが見えたら・・・」
「君は・・・私に・・・新炭層の発見に立ち合わせてくれるって言うのか。そのために、私を呼んでくれたのか・・・」
日下が、にやりと笑ってみせた。
星は、身体が熱くなるのを感じた。
この男は、すさまじい執念で新炭層を探しあてた。並大抵の苦労ではなかったはずだ。日下亨だけじゃない、妻の円や、まだ若い息子の輝も一緒に、家族でがんばって、やっと見つけたのだ。そして、いよいよ炭層発見という段取りになって、その発見の感動と栄誉をともに分かつために、星をわざわざ呼んだというのだ。その五年の間、星はというと暁幌を離れ、札幌でのんびりと暮らしていたのだ。この栄誉をともに受ける権利が、この私にあるというのか・・・。
「星さん。八号は、ここからすぐですよ。発破は明日として、ガスを、ちゃんと見ておきたいでしょう?」
「君の経験とカンは信じているよ。耳も鼻も昔どおりなんだろう。それに・・・たのもしい跡継ぎも一緒にがんばったんだ」
「でも、星さん。あんたは、その頭と知識であらゆることをつなぎ合わせて、きちんと納得しておきたいはずですよ。でなきゃ、今夜の寝つきが悪いはずだ。昔どおりの『所長さん』ならね」
今度は、星が大笑いした。
「まったく、そのとおりだよ。食後の散歩にちょうどいい。行こう」
三人は簡単な身づくろいをして、八号試掘坑に向かうことにした。円は小屋に残り、三人が帰ってきたら、おそらく催されるであろう、ささやかな酒宴と軽い夜食の準備をしながら待つことにした。
今日のところは、石炭ガスの噴出を確認して、現場の状態を確認し、明日の発破のあたりをつけるにとどめる。日下のカンは確かなものだが、炭層の状態を推定し、どこにどんな発破をかければいいか、そのあたりは、星の技術と、暁幌時代に調べ上げた過去から閉山にいたるまでの全ての炭層や地質構造の知識がものを言う。
亨はツルハシとロープを持った。輝が、脚立と安全灯を手にした。
「安全灯が要るかね?」
「念のためですよ。今日のところは必要ないはずですが。星さん、申し訳ありませんが、そこの鉤棒と、お持ちになったステッキをお願いします」
「ステッキは要らんよ」
「護身用ですよ。ツルハシや鉤棒は、狭いところでは使いにくいでしょう」
「そうだったな。万一のこともある。しかし、奥さんをひとりで小屋に残して大丈夫かね」
「円は大丈夫ですよ。それに、どうやら『誰か』は、わたしらが憎いんじゃない。わたしらが、坑の奥で動き回るのが目障りだということのようですからね。わたしらが注意すれば大丈夫でしょう」
「なるほど。しかし、今日は、早く行って、早く帰ろう」
三人は、八号坑に向けて朱鳥坑を奥へ向かった。
星も、疲れはすっかり回復したし、何よりも「新炭層」と「新暁幌」の実現が確かな手ごたえで近づきつつあることが、彼の足取りを軽くしている。
「所長さん、いや、新暁幌が始まれば、旧暁幌の事実上の経営者で、新炭層の発見者になるあなたは、きっと社長になるでしょう。いや、遠慮されることはありませんよ。あんたでなくて、誰がここを仕切るって言うんです・・・星さん、さっきも言いましたけど、わたしらは朱鳥に腰を据えて、あちこちを調べて回りました」
「しらみつぶしに暁幌じゅうを・・・かい?」
「いいえ。あてずっぽうに調べていったわけじゃないんですよ。星さんが暁幌にいらしてから、わたしは随分と勉強させてもらいました。何度か枯れたと思われたときも、一緒に炭層を探りあてて、それで、あなたとご一緒させていただいてる間に、わかったことがあります」
「私も君に教わったことが随分とあるよ。これは世辞でもなんでもないが、君は、私の師匠だったんだよ」
「それは、買いかぶりすぎですよ。つまり・・・わたしが言いたいのは、わたしらがカンと経験であたりをつける。あなたは、それこそ、わたしらからすれば、まるで関係ないようなところの調査結果や、もう枯れてしまった昔の炭層の記録やらを、もうそれこそ書類の山を眺めて、図面を引く。あなたの図面とわたしらのカンが、最初は関係ないように見える。それが、どこかでこう、その、うまく言えんのですが・・・」
「交差するときに・・・」
「そうです。その、ピンと来て、つながるんですよ。そうすると、きっと見つかった。わたしらは『なんだ、この所長先生はわかってたんだな』って感心したもんです」
「私は、君らが『ピンと来た』ときにはホッとしたもんだよ。間違ってなかったということに確信というか、安心できるのは、そのときなんだ」
「星さん。わたしらには、筋道ってのはわからない、いや、見えないんですよ。経験とかカンとか言いますけどね、わたしもよく鼻とか耳とか言いますけど、違うんですよ、身体が覚えてたり、身体の中から何かが言うんです。言うっていっても言葉じゃないんですがね。だから、若い者にも、ことばで教えるってことがどうもできない。そんなたいそうな事じゃなくてもね、坑内に向かう準備とか、ツルハシを使うコツとか、注意事項とか、そんな当たり前みたいなことどもにしたってそうです。身体で覚えてもらうしかない。もちろん、手順書とか規則とかって言葉もありますけどね。言葉で伝えても伝えた感じがしない。そもそも、わたしにしたところで、言葉で何か教わったとか、覚えたとかじゃないんですよ」
「私には筋道しか見えない。だから、君らの実感が『そうだ』って言ってくれないと不安でしょうがない」
「で、そこなんですよ。あなたの筋道には無駄がない。そのことは、わたしは随分経験したから、それこそ身体で納得してますよ。でも、あなたには確信がない。わたしらのカンってやつは、無駄が多い。やってみなけりゃわからい・・・ってことでね。でも、こうやってりゃ必ず見つかるって確信だけはある。それから、筋道ってのは、たぶん、間違いなく、きちんとやれば大体のところまでは、ちゃんと見える。この『間違いなくきちんとやる』のが難しいんでしょうがね。で、カンは、すごく利くやつと利かないやつが居る。だから、結局、結果なんですよね。やってみなけりゃわからない」
「つまり、かつて、私と一緒に暁幌で探査を繰り返した。その経験が少しは役に立ったということかな。君も、何かを参考に筋道を立ててみた、ということかな」
「そうなんですよ。カンだけであてずっぽうに調べたわけじゃないんですよ。ご一緒したときに教わった探査の手順や、それこそ昔の炭層や採掘の記録、それに、あなたがいらしてからの調査記録は、あの管理棟に残ってましたから、随分参考にさせてもらいました」
「それで、あたりをつけながら調べたんだね」
「はい。二年前からは、資料調べはもっぱら輝にやらせましたがね。それでも、暁幌じゅう調べて、つい、この春までは、炭層の兆しさえ見つかりませんでした」
「そうか。その間、私は札幌で・・・」
「星さんは、ここぞって時にお呼びしようと思ってたんですよ。それまでは、わたしらで頑張ろうってね。で、輝が閉山前の記録を調べてて、あたりの付け方を変えてみようって言うんですよ。試掘しようとしたんだから、わたしらにはわからないが、何か『筋道』があったはずだ、あきらめた理由もあるはずだが、いったん最初の『筋道』に戻ってみようってね」
「輝君が・・・」
輝は黙々と二人の前を歩いている。おそらくは星の体力を気遣ってのことだろうが、時折、振り返って二人の様子を確認しながら、安全灯で周囲を注意深く確認しつつ先導している。
「それで、八号試掘坑ですよ。大当たりでした。いや、筋道はあったはずなんですよね。でも、五年前、なぜか八号ではあたしらのカンとあなたの筋道が・・・」
「交差しなかった・・・か」
「星さん」
「ん?」
「学問ってやつは、わたしらのような仕事にも必要です。わたしはね、つくづくそう思いましたよ」
「君の言う『筋道』を使える、カンも利く、そんな坑夫が必要だね。これからは、そういう時代だよ。学問は、職業や階層に関係なく、誰にだって身に付ける権利がある。いや、身に付けるべきだと思うよ。農夫だって、漁夫だって同じだよ。変な言い方かもしれないが、それが役に立つかどうかは関係ないんだと、私は思うよ。そうだな、学問で得た知識が、直接何かに役立つかどうかは問題じゃなくて、学問を通して何かを探求する『筋道』を経験することが、その人の仕事や人生に、きっと、厚みとか人格を授けてくれる。それが、たとえば、もっと深いカンや新しい成果の肥やしになる・・・」
「輝をどう思われますか」
「新暁幌ができたら・・・彼には私の近くで頑張ってもらおう。私がこれまで学んできた技術や知識を彼に受け継いでもらうよ。それから、時機をみてになるが、彼にはどこかで数年は学問に専念できるように考えてみよう」
「ありがとうございます」
八号試掘坑。
閉山前、朱鳥坑の奥に何箇所か試掘のためにいくつか横坑を掘って、新炭層の探査を行った。そのひとつだ。しかし、五年前は、これらの試掘坑からは、新炭層存在の根拠は見出せなかったのだ。
「ここです・・・が・・・」
やや狭くなった行き止まりだ。目の前に岩壁が立ちはだかっている。五年前の行き止まりから、日下たちが少し掘り進んでいるが、ここが現在の八号最奥ということになる。
日下が首を傾げた。
輝は、安全灯を上に向けて岩壁の天井あたりをにらみつけている。
星もあたりを見回して鼻を鳴らした。
おかしい。
石炭ガスの気配がしないのだ。
石炭ガスは無味無臭というが、経験をつんだ坑夫には微妙な臭いや気配でそれとわかる。しかし、星にも、日下にも、その気配が感じられない。
やはり残存ガスだったのか・・・最後の一パーセント残っていた疑念が一瞬、星の頭をかすめたが、すぐに星の身体が言った。
日下が間違うはずはない。
「輝。ランプを」
「星さん、その鉤棒を・・・」
星は鉤棒を輝に渡した。
輝は、安全灯の蓋を開けて、鉤棒の先に下げた。鉤棒を岩壁の天井のほうへ差し上げる。
石炭ガスがわずかでも漏れていれば、岩壁のどこかに青い炎が見えるか、安全灯の周囲でパチパチと反応が起きるはずだ。
しかし・・・何の反応もない。
「ばかな。そんなはずはない。確かにガスは出ていた。そんな・・・」
日下は岩壁を叩いた。
星は言葉もない。ただ、何か納得できない。こんな結末は筋が通らない。違うか?
しばらく鉤棒先の安全灯で岩壁を照らし続けていた輝が安全灯を降ろしながら言った。
「ちょっと待ってください」
輝は持ってきた脚立を壁に立てると、ツルハシと安全灯を持って壁の上方に上っていった。そして、壁面に安全灯を近づけて注意深く観察していた。
「やっぱり・・・」
「輝君! どうかしたかね」
輝がツルハシの先で壁の一部を軽くつついた。と、途端に、
シュッ!
と、何かが噴き出した。
「あ」
日下と星が同時に声を上げた。
ガスの臭いだ。
輝が下りてきた。
安全灯の蓋を取り、鉤棒で差し上げる。
ボッ!
岩壁の天井近くに青い炎が噴き出した。
「やった!」
石炭ガスは確かに存在した。そして、その勢いは、この壁の向こうに炭層が存在することを確かに示している。
「ご納得がいきましたか?」
日下が笑った。
「もちろんだよ。こいつは素晴らしい。しかし・・・五年前、このすぐ手前まで来てたのに何故・・・」
「まぁ・・・そんなものですよ。人間のすることですからね。それにしても・・・なぜ塞がってたんでしょうね。おかしなこともあるもんだ」
「塞がっていたんじゃありません。塞がれていたんです」
輝が白い塊を見せた。
「何だね、これは・・・」
「漆喰でしょう。これで、ガスの穴を塞いだやつが居ます。しかも・・・ご丁寧に、漆喰の上に炭塵まで撒いてごまかしてました。一部が白く残ってて・・・それで変だと思ったんで・・・」
「件の『誰か』だな」
星が目を細めた。
日下が、その目を見ながら笑った。
「どうします。どうやら、やつらは、我々が新炭層を発見しては、よほど都合が悪いらしい。用心のため、発破はしばらく待ちますか?」
「実はね。あの二通目の手紙以来、何だか闘志が湧いてきてね。これで覚悟が決まったよ」
「だと思いました。そういう目をされましたから」
三人は、岩壁や周辺の状態を確認し、ロープで簡単な計測をして、発破の段取りを確認してから帰路についた。今度は、星と日下が先を歩いた。談笑しながら歩く二人の後を、輝はときおり安全灯をかざして背後の様子を確認しながら進む。
今日、一日の間にいろいろなことがあった。
はっきりしたことがいくつかある。
いよいよ暁幌が再生することになる、ということ。
それから、「誰か」の存在と、その明確な悪意の存在。
そして、我々がその悪意と闘うことになる、ということだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月24日
第四章:発見 その3
<発見 その3>
日下家に戻った彼らは、円とともに小さな酒宴を張った。明朝は発破をかけて、いよいよ、待ちに待った、彼らにとって五年越しの念願だった新炭層との対面となるに違いない。話題は当然、発破の段取りから始まって、暁幌炭坑の再開の準備などが語られた。もっとも、炭層の規模や状態はまだわからない。ただ、旧暁幌の経験から言っても、また、今日確認した石炭ガスの状態から言っても、規模、品質ともに、おそらく、旧暁幌の株主たちや有力な投資家たちをして事業再開に踏み切らせるだけのものではあるに違いない。
気になるのは、ここまで彼らの活動を、とくに星の来訪を妨げようとした者の存在だ。とくに輝は、ずっとそれが気にかかるようだった。
「競合者というわけでは・・・ないだろうな」
星が、考えながら言った。
「競合者なら、彼らが先に事業化を進めていたはずです。先に発見したんですから」
輝がすぐに応じた。
「しかし、ここには、われわれが居座っていたからな」
亨は、自分たちの存在が競合者の邪魔になったのではないかとと言う。
「事業化となれば、何といっても『黒ダイヤ』だからね。仮に、少々頑固な者たちが邪魔になったとしても・・・実業家というものは、そんなものは恐れないものだよ。たいがいの実業家は、金ずくでも、金が利かないなら、力ずくでも、あらゆる方法を使って排除しようとする。残念なことにね・・・ただ、今回のように、初手からこそこそした怪しげな方法は採らないものだ。今回のは、何か犯罪めいた臭いがするよ」
「だとすると、思惑が読めない分やっかいですな」
「廃坑跡なんかは、よく盗賊の類が隠れ家にすることもあるらしい。なぁに、炭層が出てくれば、地元の警察を動かして、いちど徹底的に、坑内の隅々まで捜索させればいい。明らかに妨害工作はあったし、あやうく危害を加えられたかも知れなかったんだ、警察はちゃんとやってくれるさ」
現状では、妨害者の正体については想像するしかない。まずは炭層の確認だ。彼らは、酒宴をそこそこにきりあげて床に就いた。
翌朝、やや遅めの朝食をすませた星と日下家の親子は、発破の準備と弁当や飲み水をととのえて八号試掘坑に向かった。
今回は、円も同行する。円は、若い頃には亨とともに坑内に入り、亨の仕事を手伝ったものだ。亨にとっては、この五年間の炭層探しにあっても、輝とともに信頼の置ける助手であり続けた。これから行う発破作業や、その後に行うことになるであろう試掘のことを考えると、今日は一家全員で出かけるべきだと、亨が判断したのだ。もっとも、亨にしてみれば、これまで苦労を分かちあった伴侶にも、新炭層発見の現場に立ち合わせてやりたいというのが、一番の理由だったろう。
八号坑に着いたところで、亨が輝に指示した。
「安全灯を・・・」
輝が、安全灯の蓋を開き、鉤棒でガスの噴出孔近くにかざした。
ボッ!
昨夜と同じ勢いで青い炎が燃え上がった。
「今回は塞ぐ暇がなかったと見える・・・いや、諦めたかな」
星が亨に確認しながら発破を仕掛ける場所を指示し、輝と円がてきぱきと作業を進める。
「まったく・・・この三人だけでも相当な仕事ができるなぁ。小さな炭坑なら従業員は不要じゃないかね?」
星が笑いながら冗談を言う。皆、楽しくて仕方ないのだ。
「さあ、準備完了だ。始めるぞ」
全員が壁から離れ、ずっと後方の岩陰に身を隠して、ヘルメットをかぶり、顔を覆って耳を塞いだ。そして・・・
轟音と振動が彼らの周りをつつんだ。粉塵が巻き上がり、突風が彼らを一瞬壁に押し付け、はるか後方に向かって奔り過ぎた。しばし、舞い散った砂粒が、ヘルメットや服の上から彼らを地吹雪のように襲った。
静かになった。が、粉塵が舞い上がって、安全灯で照らしても、しばらくは周囲の様子は確認できない。彼らは、粉塵がおさまるのを待った。
「どうやら・・・おさまったな。行こう・・・首尾はどうかな」
四人は、八号坑の最奥に向かった。
安全灯をかかげて先頭を歩いていた輝が振り向いて叫んだ。
「父さん! 星さん! あれを・・・」
そこにあったのは、炭層を露出した壁面ではなかった。
彼らを迎えたのは、巨大な洞穴。
いたるところに炭層が走っている巨大なホールだった。
「おい! こりゃあ、まずいぞ!」
亨が洞穴を見て叫んだ。
「あ? いや・・・八号坑の先に他所の炭坑なんかないはずだが・・・じゃあ、なんで坑道があるんだ?」
「日下さん! これは坑道じゃない。天然の洞穴だよ。いやぁ・・・しかし、確かに大きな坑道のようだなぁ」
八号坑の先にあったもの。それは、天然の坑道ともいうべき巨大な洞穴だった。
四人は発破で開いた門をまたぎ、ゆっくりと宮殿のような洞穴に足を踏み入れた。
「あんた。あちこちに・・・あの青黒い帯はみんな炭層じゃないの?」
「そうだ。まるで龍が何匹も壁を走ってるみたいだな。夢を見てるみたいだ」
近くの炭層に輝がツルハシを振るった。
高い音がホールに響いた。
「見てください。余計な炭塵はほとんど出ないし、きれいに青光りしてる」
輝が、採れたばかりの石炭を星と亨に渡した。
「旧暁幌に劣らない・・・上質の瀝青炭だな。こいつはすごい」
「どのくらいの広さがあるんでしょうね・・・ここは」
「わからんが・・・とにかく、炭層をいくつかまとめて発見したようなものだよ。これは・・・本当にすごい」
ゴロゴロ・・・ゴロゴロ・・・
遠雷のような音が、時おり聞こえてくる。
「あぁ? トロッコ? やっぱり・・・ここはどこか他所の・・・」
「いや、違う・・・あれは・・・たぶん、水の音だ・・・そうか、ここには地下水脈があるに違いない」
「地下水脈?」
「そうだよ、日下さん。地下水があちこちで川のように流れを作っているに違いない。確か、この近くには暁幌湖があったな。どうやら、この大洞穴は、いい炭層に恵まれているだけでなく、豊富な水源も有しているということらしい。ここは確かに地下だが・・・この様子なら、露天掘り同然で存分に石炭を採ることができるぞ。これなら、たいした期間をかけずに暁幌も再開できるよ」
「なんてこった。五年間待って、蓋を開けてみたら、お袋さん・・・暁幌は、坑道も水場も万端ととのえて、わたしらを待っていてくれたっていうわけですね・・・」
感激のあまり、洞穴の入り口近くにたたずんでいた四人は、大発見の喜びも手伝ったのだろう、少し大胆になっていた。弁当と飲み水も持参している。発破は順調だったから、時間も十分にある。四人は、洞穴の奥に向かって小旅行を敢行するすることにした。どこか適当なところまで探検して、そこで昼食を採り、それから戻ろうというのである。もっとも、長年、地下で入り組んだ坑内を歩き回って探査を続けてきたのである。洞穴の広いところを無理せず進む分には、道に迷うような気遣いはない。
奥へ進めば進むほど、この大洞穴には驚かされるばかりだった。
その広さは、今日の小旅行くらいではつかみきれないほど広い。炭層もいたるところに走っている。
こぶりなホールのようになっているところで、彼らは昼食を採ることにした。
「星さん。この中に街を作ることだってできそうですよ。露天掘りとおっしゃいましたよね。だったら、ここに街を作っちまったほうが早い」
「ははは。確かに、君らは五年間坑内で暮らしてきたしね。それに、どうやら地下というのも健康には好いらしい。君らを見ればわかる」
昼食後、一息入れたところで、彼らは帰路に就くことにした。今日は、星も同行しているから、輝も道に迷うような経路はとっていない。来た道を順を追って引き返すまでのことだ。
広めのホールを進んでいるときのことだ。輝は、何かが高い天井の方から頭上に降ってくるような気配を感じた。が、一瞬のことでかわすことができなかった。
バサッ
何かが安全灯をかかげた輝の手をはたいたように感じた。
安全灯が地面に落ち、カラカラと音を立ててどこかに転がっていった。
あたりは、一瞬のうちに完全な暗闇になった。もう、何の気配も無い。
「輝! お前、俺たちを迷子にする気か!」
亨が叫んだ。
輝はすぐには答えなかった。
あれは何だ?
人じゃない。
でも、ぼくの手を・・・いや、安全灯を狙った。
何のため? ぼくらを迷子にするためだ。
何だ。あれは。
「何かが・・・いえ。大丈夫です。ちゃんと道はわかります」
輝が先頭に立ち、星と円が続き、亨が殿(しんがり)をつとめる形で、それぞれ前を行く者の服をつかんでゆっくりと進んだ。
読者の皆さんは、夜、山中を歩いたことはあるだろうか?
あるいは、濃い霧の中、林や山を歩いたことはあるだろうか?
見通しが悪いとき、山や森林では、目に頼ろうとすると道を間違える。そういうときは、目に頼ることをやめて、足に任せる。足に神経を集中させれば、案外と「道」をたどることができるものだ。もちろん、それは十分な経験を積んだ「足」あってのことだが。
小旅行が、ちょっとした冒険になってしまった。しかし、四人は絶望どころか、まったく悲観していなかった。ちょっと余計な時間がかかったが、八号坑まで戻れないなどということは毛ほども考えていなかったのである。しかし・・・
輝が足を止めた。
「どうした。道が違ったのか?」
亨が殿から声をかけた。
「いえ。道は合っているはずなんです」
「『はず』だと?」
「ここが・・・ここが八号のはずなんです」
「何だと」
「無いんです。入り口が・・・今朝、発破で開けたはずの門が!」
道に迷った?
いや、そうじゃない。
あの『誰か』だ。
妨害者がついに牙をむいたのだ。
閉じ込められたのだ。ぼくらは。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
日下家に戻った彼らは、円とともに小さな酒宴を張った。明朝は発破をかけて、いよいよ、待ちに待った、彼らにとって五年越しの念願だった新炭層との対面となるに違いない。話題は当然、発破の段取りから始まって、暁幌炭坑の再開の準備などが語られた。もっとも、炭層の規模や状態はまだわからない。ただ、旧暁幌の経験から言っても、また、今日確認した石炭ガスの状態から言っても、規模、品質ともに、おそらく、旧暁幌の株主たちや有力な投資家たちをして事業再開に踏み切らせるだけのものではあるに違いない。
気になるのは、ここまで彼らの活動を、とくに星の来訪を妨げようとした者の存在だ。とくに輝は、ずっとそれが気にかかるようだった。
「競合者というわけでは・・・ないだろうな」
星が、考えながら言った。
「競合者なら、彼らが先に事業化を進めていたはずです。先に発見したんですから」
輝がすぐに応じた。
「しかし、ここには、われわれが居座っていたからな」
亨は、自分たちの存在が競合者の邪魔になったのではないかとと言う。
「事業化となれば、何といっても『黒ダイヤ』だからね。仮に、少々頑固な者たちが邪魔になったとしても・・・実業家というものは、そんなものは恐れないものだよ。たいがいの実業家は、金ずくでも、金が利かないなら、力ずくでも、あらゆる方法を使って排除しようとする。残念なことにね・・・ただ、今回のように、初手からこそこそした怪しげな方法は採らないものだ。今回のは、何か犯罪めいた臭いがするよ」
「だとすると、思惑が読めない分やっかいですな」
「廃坑跡なんかは、よく盗賊の類が隠れ家にすることもあるらしい。なぁに、炭層が出てくれば、地元の警察を動かして、いちど徹底的に、坑内の隅々まで捜索させればいい。明らかに妨害工作はあったし、あやうく危害を加えられたかも知れなかったんだ、警察はちゃんとやってくれるさ」
現状では、妨害者の正体については想像するしかない。まずは炭層の確認だ。彼らは、酒宴をそこそこにきりあげて床に就いた。
翌朝、やや遅めの朝食をすませた星と日下家の親子は、発破の準備と弁当や飲み水をととのえて八号試掘坑に向かった。
今回は、円も同行する。円は、若い頃には亨とともに坑内に入り、亨の仕事を手伝ったものだ。亨にとっては、この五年間の炭層探しにあっても、輝とともに信頼の置ける助手であり続けた。これから行う発破作業や、その後に行うことになるであろう試掘のことを考えると、今日は一家全員で出かけるべきだと、亨が判断したのだ。もっとも、亨にしてみれば、これまで苦労を分かちあった伴侶にも、新炭層発見の現場に立ち合わせてやりたいというのが、一番の理由だったろう。
八号坑に着いたところで、亨が輝に指示した。
「安全灯を・・・」
輝が、安全灯の蓋を開き、鉤棒でガスの噴出孔近くにかざした。
ボッ!
昨夜と同じ勢いで青い炎が燃え上がった。
「今回は塞ぐ暇がなかったと見える・・・いや、諦めたかな」
星が亨に確認しながら発破を仕掛ける場所を指示し、輝と円がてきぱきと作業を進める。
「まったく・・・この三人だけでも相当な仕事ができるなぁ。小さな炭坑なら従業員は不要じゃないかね?」
星が笑いながら冗談を言う。皆、楽しくて仕方ないのだ。
「さあ、準備完了だ。始めるぞ」
全員が壁から離れ、ずっと後方の岩陰に身を隠して、ヘルメットをかぶり、顔を覆って耳を塞いだ。そして・・・
轟音と振動が彼らの周りをつつんだ。粉塵が巻き上がり、突風が彼らを一瞬壁に押し付け、はるか後方に向かって奔り過ぎた。しばし、舞い散った砂粒が、ヘルメットや服の上から彼らを地吹雪のように襲った。
静かになった。が、粉塵が舞い上がって、安全灯で照らしても、しばらくは周囲の様子は確認できない。彼らは、粉塵がおさまるのを待った。
「どうやら・・・おさまったな。行こう・・・首尾はどうかな」
四人は、八号坑の最奥に向かった。
安全灯をかかげて先頭を歩いていた輝が振り向いて叫んだ。
「父さん! 星さん! あれを・・・」
そこにあったのは、炭層を露出した壁面ではなかった。
彼らを迎えたのは、巨大な洞穴。
いたるところに炭層が走っている巨大なホールだった。
「おい! こりゃあ、まずいぞ!」
亨が洞穴を見て叫んだ。
「あ? いや・・・八号坑の先に他所の炭坑なんかないはずだが・・・じゃあ、なんで坑道があるんだ?」
「日下さん! これは坑道じゃない。天然の洞穴だよ。いやぁ・・・しかし、確かに大きな坑道のようだなぁ」
八号坑の先にあったもの。それは、天然の坑道ともいうべき巨大な洞穴だった。
四人は発破で開いた門をまたぎ、ゆっくりと宮殿のような洞穴に足を踏み入れた。
「あんた。あちこちに・・・あの青黒い帯はみんな炭層じゃないの?」
「そうだ。まるで龍が何匹も壁を走ってるみたいだな。夢を見てるみたいだ」
近くの炭層に輝がツルハシを振るった。
高い音がホールに響いた。
「見てください。余計な炭塵はほとんど出ないし、きれいに青光りしてる」
輝が、採れたばかりの石炭を星と亨に渡した。
「旧暁幌に劣らない・・・上質の瀝青炭だな。こいつはすごい」
「どのくらいの広さがあるんでしょうね・・・ここは」
「わからんが・・・とにかく、炭層をいくつかまとめて発見したようなものだよ。これは・・・本当にすごい」
ゴロゴロ・・・ゴロゴロ・・・
遠雷のような音が、時おり聞こえてくる。
「あぁ? トロッコ? やっぱり・・・ここはどこか他所の・・・」
「いや、違う・・・あれは・・・たぶん、水の音だ・・・そうか、ここには地下水脈があるに違いない」
「地下水脈?」
「そうだよ、日下さん。地下水があちこちで川のように流れを作っているに違いない。確か、この近くには暁幌湖があったな。どうやら、この大洞穴は、いい炭層に恵まれているだけでなく、豊富な水源も有しているということらしい。ここは確かに地下だが・・・この様子なら、露天掘り同然で存分に石炭を採ることができるぞ。これなら、たいした期間をかけずに暁幌も再開できるよ」
「なんてこった。五年間待って、蓋を開けてみたら、お袋さん・・・暁幌は、坑道も水場も万端ととのえて、わたしらを待っていてくれたっていうわけですね・・・」
感激のあまり、洞穴の入り口近くにたたずんでいた四人は、大発見の喜びも手伝ったのだろう、少し大胆になっていた。弁当と飲み水も持参している。発破は順調だったから、時間も十分にある。四人は、洞穴の奥に向かって小旅行を敢行するすることにした。どこか適当なところまで探検して、そこで昼食を採り、それから戻ろうというのである。もっとも、長年、地下で入り組んだ坑内を歩き回って探査を続けてきたのである。洞穴の広いところを無理せず進む分には、道に迷うような気遣いはない。
奥へ進めば進むほど、この大洞穴には驚かされるばかりだった。
その広さは、今日の小旅行くらいではつかみきれないほど広い。炭層もいたるところに走っている。
こぶりなホールのようになっているところで、彼らは昼食を採ることにした。
「星さん。この中に街を作ることだってできそうですよ。露天掘りとおっしゃいましたよね。だったら、ここに街を作っちまったほうが早い」
「ははは。確かに、君らは五年間坑内で暮らしてきたしね。それに、どうやら地下というのも健康には好いらしい。君らを見ればわかる」
昼食後、一息入れたところで、彼らは帰路に就くことにした。今日は、星も同行しているから、輝も道に迷うような経路はとっていない。来た道を順を追って引き返すまでのことだ。
広めのホールを進んでいるときのことだ。輝は、何かが高い天井の方から頭上に降ってくるような気配を感じた。が、一瞬のことでかわすことができなかった。
バサッ
何かが安全灯をかかげた輝の手をはたいたように感じた。
安全灯が地面に落ち、カラカラと音を立ててどこかに転がっていった。
あたりは、一瞬のうちに完全な暗闇になった。もう、何の気配も無い。
「輝! お前、俺たちを迷子にする気か!」
亨が叫んだ。
輝はすぐには答えなかった。
あれは何だ?
人じゃない。
でも、ぼくの手を・・・いや、安全灯を狙った。
何のため? ぼくらを迷子にするためだ。
何だ。あれは。
「何かが・・・いえ。大丈夫です。ちゃんと道はわかります」
輝が先頭に立ち、星と円が続き、亨が殿(しんがり)をつとめる形で、それぞれ前を行く者の服をつかんでゆっくりと進んだ。
読者の皆さんは、夜、山中を歩いたことはあるだろうか?
あるいは、濃い霧の中、林や山を歩いたことはあるだろうか?
見通しが悪いとき、山や森林では、目に頼ろうとすると道を間違える。そういうときは、目に頼ることをやめて、足に任せる。足に神経を集中させれば、案外と「道」をたどることができるものだ。もちろん、それは十分な経験を積んだ「足」あってのことだが。
小旅行が、ちょっとした冒険になってしまった。しかし、四人は絶望どころか、まったく悲観していなかった。ちょっと余計な時間がかかったが、八号坑まで戻れないなどということは毛ほども考えていなかったのである。しかし・・・
輝が足を止めた。
「どうした。道が違ったのか?」
亨が殿から声をかけた。
「いえ。道は合っているはずなんです」
「『はず』だと?」
「ここが・・・ここが八号のはずなんです」
「何だと」
「無いんです。入り口が・・・今朝、発破で開けたはずの門が!」
道に迷った?
いや、そうじゃない。
あの『誰か』だ。
妨害者がついに牙をむいたのだ。
閉じ込められたのだ。ぼくらは。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月28日
第五章:星男爵失踪事件
<星男爵失踪事件>
札幌の郊外、高名な鉱物学者、鉱山技師にして、北海道有数の実業家でもある華族、星直耀男爵の屋敷では、ちょっとした騒ぎが起きていた。
星男爵が先々週の土曜日に家を出てから戻らず、消息を絶ってしまったというのである。執事をはじめ、幾人かの使用人や書生が言うには
「男爵は三日程度の予定だとおっしゃってました」
「遅くとも週末には帰るとのことで、旅装も軽くしてお出かけになりました」
というのである。
ところが、その週末が来ても主人は帰らず、とうとう週が明けて二度目の月曜日になってしまった。遅れるとか、予定が延びるといったような知らせも届かず、不安になった執事が警察に一報したというわけだ。
そういえば、どちらにお出かけになるのかも言い置いて行かれなかった。今になって考えてみれば、そのこと自体、あの男爵様にしては奇妙なことだ。何か、危険なことに巻き込まれでもしていなければよいが・・・・
名士とはいえ、当主が一週間ほど出かけたまま帰らないというようなことだけであれば、そう珍しいことではない。ある日、忽然と姿を消したというならともかく、旅支度をして、一週間程度の旅になるかもしれないと言い置いていったのである。旅程が少しくらい延びることは、まま、あることだ。第一、それが華族様ということであれば、気まぐれな旅であったのかも知れない。警察も、最初に連絡を受けたときは、あまり深刻な事態が起きたとは考えなかった。
ただ、その当主というのが、あの「星直耀氏」であるということで、警察は、とにかく屋敷に捜査員を遣ることにしたのである。星男爵は、彼らには、華族というよりも、むしろ実業界の重鎮として知られていたからである。
高名な実業家というのは、時と場合によっては身の危険が迫る場合もあるのである。彼らは、常に、政治の動きと無縁で居るというわけにはいかないし、たとえ高潔な人物でも、競合者(ライバル)や政敵の誹謗中傷を信じた人物に命を狙われる危険がある。功成り名を遂げた人物に対する羨望や憧れが憎しみや嫉妬に、さらに不平等な社会への義憤に繋がってしまえば、そんな「正義感」気分に注ぎ込まれた誹謗中傷は、義挙とか天誅という衣を容易く纏うことができる。そんな暗殺事件や暗殺未遂事件というのは決して珍しいことではなかったのである。
「困ったものだ。星先生のような方が、供も連れずに単身でお出かけになるとは・・・で、どんなご様子だったかね」
「懐かしい、旧知のご友人を訪ねられるのではないかと思いましたが」
「なぜ、そう思ったのかね」
「最初のお手紙をお持ちしたときに、封筒をご覧になって涙ぐんでおられたようでした」
「手紙?」
捜査員は、執事が証言した手紙の存在に着目した。
男爵が旅行に出ることを決めたのは、その手紙を読んだことがきっかけになったようだった。しかも、手紙は、午前と午後の配達で二通届いたという。
「二通目のお手紙で、いったん出発を取り止めようとされた様でしたが、結局お出かけになりました」
「その手紙は残ってないのだね」
「男爵がお持ちになりました」
「で、どんな手紙だった?」
「一通目は普通の、きちんとした封書でした。二通目は、粗末な封書で、かなり古びた封筒だったように記憶しております」
「どこからの手紙だった? 差出人とかは覚えていないかね」
「存じません」
「君が運んだんだろう」
「お運びはいたしますが、主人宛の封書や葉書に、わたくしが目を通すことはございません」
「中を読んだろう、とは言ってない。封書なら、裏に差出人とか、表に消印とかあるだろう」
「ですから・・・そういったことは読まないようにしておりますので」
「読まないといっても、見えてしまうこともあるだろうに。何か、記憶してないのかね」
「見えても、見ないのです。ですから・・・封書の色とか風合いとかは記憶しているのですが、何が書いてあるかといったことは、読まないように心がけているのでして・・・」
涙ぐんでいたとか・・・主人の表情は盗み見て覚えているくせに・・・
捜査員の不審を読み取ったのか、執事が言った。
「主人の顔色や振る舞いから、お体の具合やお心の様子を拝察して、お身の周りのことを遺漏無くととのえるのが、わたくしどもの仕事でございます。しかしながら、主人宛の私信を盗み見るようなことは断じていたしません」
いずれにせよ、手紙の件は重要だった。
男爵は手紙を受け取って、おそらく旧知の友人か知人に会うために旅支度を命じた。
その後で、不審な手紙を受け取って、いったんは躊躇したらしい。
しかし、結局、出発した。
予定では三日程度、長くても一週間。単身でお忍び旅行といったかっこうだ。
その後、彼を知る何人かが、男爵を駅で見かけたらしいことまではわかったが、その後の足取りが全くつかめない、どうやら、男爵自身が、人目につかないよう行動していたらしい。
すでに、男爵が旅行に出てから十日が経った。男爵からは何の連絡も無い。何らかの事件に巻き込まれた可能性もある。脅迫や、不審な連絡はなかったので、営利誘拐といった可能性は低そうだ。
警察は、慎重に検討した結果、まず「失踪事件」として新聞にもこれを公表し、正式に捜索を開始することにした。また、道内の駅や公共施設などに、男爵の顔写真と情報提供を求めるビラを貼った。
しかしながら、有力な情報は寄せられず、星直耀男爵の行方は遥として知れず、実業界や学術会は、次第に不安を募らせていった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
札幌の郊外、高名な鉱物学者、鉱山技師にして、北海道有数の実業家でもある華族、星直耀男爵の屋敷では、ちょっとした騒ぎが起きていた。
星男爵が先々週の土曜日に家を出てから戻らず、消息を絶ってしまったというのである。執事をはじめ、幾人かの使用人や書生が言うには
「男爵は三日程度の予定だとおっしゃってました」
「遅くとも週末には帰るとのことで、旅装も軽くしてお出かけになりました」
というのである。
ところが、その週末が来ても主人は帰らず、とうとう週が明けて二度目の月曜日になってしまった。遅れるとか、予定が延びるといったような知らせも届かず、不安になった執事が警察に一報したというわけだ。
そういえば、どちらにお出かけになるのかも言い置いて行かれなかった。今になって考えてみれば、そのこと自体、あの男爵様にしては奇妙なことだ。何か、危険なことに巻き込まれでもしていなければよいが・・・・
名士とはいえ、当主が一週間ほど出かけたまま帰らないというようなことだけであれば、そう珍しいことではない。ある日、忽然と姿を消したというならともかく、旅支度をして、一週間程度の旅になるかもしれないと言い置いていったのである。旅程が少しくらい延びることは、まま、あることだ。第一、それが華族様ということであれば、気まぐれな旅であったのかも知れない。警察も、最初に連絡を受けたときは、あまり深刻な事態が起きたとは考えなかった。
ただ、その当主というのが、あの「星直耀氏」であるということで、警察は、とにかく屋敷に捜査員を遣ることにしたのである。星男爵は、彼らには、華族というよりも、むしろ実業界の重鎮として知られていたからである。
高名な実業家というのは、時と場合によっては身の危険が迫る場合もあるのである。彼らは、常に、政治の動きと無縁で居るというわけにはいかないし、たとえ高潔な人物でも、競合者(ライバル)や政敵の誹謗中傷を信じた人物に命を狙われる危険がある。功成り名を遂げた人物に対する羨望や憧れが憎しみや嫉妬に、さらに不平等な社会への義憤に繋がってしまえば、そんな「正義感」気分に注ぎ込まれた誹謗中傷は、義挙とか天誅という衣を容易く纏うことができる。そんな暗殺事件や暗殺未遂事件というのは決して珍しいことではなかったのである。
「困ったものだ。星先生のような方が、供も連れずに単身でお出かけになるとは・・・で、どんなご様子だったかね」
「懐かしい、旧知のご友人を訪ねられるのではないかと思いましたが」
「なぜ、そう思ったのかね」
「最初のお手紙をお持ちしたときに、封筒をご覧になって涙ぐんでおられたようでした」
「手紙?」
捜査員は、執事が証言した手紙の存在に着目した。
男爵が旅行に出ることを決めたのは、その手紙を読んだことがきっかけになったようだった。しかも、手紙は、午前と午後の配達で二通届いたという。
「二通目のお手紙で、いったん出発を取り止めようとされた様でしたが、結局お出かけになりました」
「その手紙は残ってないのだね」
「男爵がお持ちになりました」
「で、どんな手紙だった?」
「一通目は普通の、きちんとした封書でした。二通目は、粗末な封書で、かなり古びた封筒だったように記憶しております」
「どこからの手紙だった? 差出人とかは覚えていないかね」
「存じません」
「君が運んだんだろう」
「お運びはいたしますが、主人宛の封書や葉書に、わたくしが目を通すことはございません」
「中を読んだろう、とは言ってない。封書なら、裏に差出人とか、表に消印とかあるだろう」
「ですから・・・そういったことは読まないようにしておりますので」
「読まないといっても、見えてしまうこともあるだろうに。何か、記憶してないのかね」
「見えても、見ないのです。ですから・・・封書の色とか風合いとかは記憶しているのですが、何が書いてあるかといったことは、読まないように心がけているのでして・・・」
涙ぐんでいたとか・・・主人の表情は盗み見て覚えているくせに・・・
捜査員の不審を読み取ったのか、執事が言った。
「主人の顔色や振る舞いから、お体の具合やお心の様子を拝察して、お身の周りのことを遺漏無くととのえるのが、わたくしどもの仕事でございます。しかしながら、主人宛の私信を盗み見るようなことは断じていたしません」
いずれにせよ、手紙の件は重要だった。
男爵は手紙を受け取って、おそらく旧知の友人か知人に会うために旅支度を命じた。
その後で、不審な手紙を受け取って、いったんは躊躇したらしい。
しかし、結局、出発した。
予定では三日程度、長くても一週間。単身でお忍び旅行といったかっこうだ。
その後、彼を知る何人かが、男爵を駅で見かけたらしいことまではわかったが、その後の足取りが全くつかめない、どうやら、男爵自身が、人目につかないよう行動していたらしい。
すでに、男爵が旅行に出てから十日が経った。男爵からは何の連絡も無い。何らかの事件に巻き込まれた可能性もある。脅迫や、不審な連絡はなかったので、営利誘拐といった可能性は低そうだ。
警察は、慎重に検討した結果、まず「失踪事件」として新聞にもこれを公表し、正式に捜索を開始することにした。また、道内の駅や公共施設などに、男爵の顔写真と情報提供を求めるビラを貼った。
しかしながら、有力な情報は寄せられず、星直耀男爵の行方は遥として知れず、実業界や学術会は、次第に不安を募らせていった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年10月29日
第六章:瑛(あきら)の災難 その1
<瑛(あきら)の災難 その1>
夏の終わりの収穫祭である。
苫小牧の農場で行われる収穫祭は、一農場の主催だったが、いまでは町のちょっとしたイベントに育ってきている。
「収穫祭」というちょっとハイカラな響きもあるが、何より、農場の産物や、それらを使ったちょっと珍しい料理の出店や、夕刻に行われる歌合戦や演芸合戦が呼び物になっており、近隣の町村からも老若男女が訪れる。
ところが、今年の収穫祭では、とくに、若者たちにとっては奇妙なことが起きていた。
祭りは最高潮に達しようとしているというのに、あの月岡瑛(あきら)は無口で、時には不機嫌にさえ見えたのである。
おかしなこともあるものだ。
農場やこのあたりの人々は、およそ「不機嫌な月岡瑛」というものを見たことがない。もちろん「無口な瑛」というのも論外である。
月岡瑛という少年は、いつも陽気である。
陽気が歩いているというのが、月岡瑛なのだ。
彼はのべつ、仕事中でも、街を歩いているときでも、草っ原に寝転んで寛いでいるときでさえ、鼻歌をうたっているか、口笛を吹いているか、誰かとおしゃべりしているか、といって五月蝿いとか鬱陶しいというわけでもなく、ちょうど太陽が陽光というものを放出しながら、あちこちに陽だまりを置いてまわるように、歌やおしゃべりで、周りの人々の懐に陽気という気分を放り込んでまわっているような性質(たち)の少年なのだ。
瑛のおしゃべりというのが、また魅力的で、どこで聞き込んできたのか、このあたりの奇勝や史跡にまつわる昔語りや伝説の類を、それは見事な身振り手振りを交えながら、実に上手く語るのである。
つまり、瑛は、このあたりではちょっと知られた名歌手であり、名優であり、すぐれた舞手であり、祭りともなれば、主役として、率先垂範して近隣の少年少女たちを束ね、祭りを盛り上げるリーダーなのである。
それが、はじめのうちは、いつもどおり、元気いっぱいに祭りを仕切っていたのだが、昼を過ぎ、祭りがいよいよ佳境を迎えるという段になって、なんだか元気がなくなってきた。日が傾いて、歌合戦だのかくし芸だのと一番盛り上がってきたあたりで、ついに「無口で不機嫌な瑛」という、いまだかつて誰も見たことがない情況を呈してしまったのだ。
そして、あろうことか、歌合戦で、あの瑛が歌詞を忘れ、絶句してしまった。当然のことながら、瑛は一等賞はおろか入賞さえしなかった。ありえないことである。
「瑛はどうかしちまったんじゃないか? 上の空だったぞ」
「今日の月岡さん、変だわ」
「病気だな、これは。それも医者も薬も利かない病だ・・・へへぇ」
「ええーっ? で、誰だ、その病の元は」
「知らんよ。見当もつかん。だが・・・間違いないな、あれは・・・病だ」
訳知り顔の年配者が勝手な憶測を述べれば、辺りに居たいく人かの少女たちが騒ぐ。
一週間前「お前に会いたがってる娘っこがわんさと居る」と瑛が輝に言ったが、実のところ「言葉を交わしたがっている娘っこがわんさと居る」のは瑛のほうだった。
そう、その輝である。
瑛を上の空にさせているのは、どこかのお嬢さんではなく、輝なのだ。
「輝は『来る』と言った。来る、と言ったら来る。あいつはそういうやつだ。万一、来られなくなったとしたら・・・ちゃんと断りを入れてくるはずだ。断り無しに約束を違えるやつじゃない。じゃあ、何で来ないんだろ・・・」
「星さんが見えてた。仕事がらみだって言ってた。何か関係あるのかな、でも、何か用事ができたんなら、そう言ってよこすはずだ。じゃあ、何で何も言ってこないんだ」
「何か事故でもあったんだろうか。でも、あの親父さんやお袋さん、それに男爵様だって居るんだ。何かあったのしても誰かが・・・そうだ、男爵様はまだいらっしゃるんだろうか・・・それにしても、何で、誰も何も言ってよこさないんだろう」
「そういえば、あいつ、坑内に変な気配がするって言ってた。やっぱり何かあったんだろうか。それにしても、この一週間、そんな話も何も言ってこなかった。何で、何も・・・あああ・・・わからない。変だよ。とにかく・・・」
ぐるぐる、ぐるぐると「何で」「何で」が瑛の頭の中を経巡った。結局、行き着くところは、とにかく・・・
「明日、朱鳥坑に行ってみよう」
それしかない。そのくらいしかできることはないのである。
それしかないとわかると、瑛は少し元気を取り戻し、いつもの瑛になった。元来、考え続けることは、瑛の性には合わない。
明朝になったら朱鳥坑に行くことに決めた瑛は、祭りがはねた後の夕刻、海辺近くの小屋に、集まった若者たち、少年少女たちを集めて、いつもどおり怪談の口火を切った。
毎年、収穫祭がはねた後、祭りに集まった少年たちと少女たちがこの小屋に泊まりこんで、夜っぴて宴会を催すのが倣いになっている。ちょっと昔なら若衆組と娘組の、もっと昔なら歌垣みたいなものだ。いわば、夏祭りの場で許される「グループ交際」の元祖である。
今年は、百物語よろしく、怪談や不思議な体験談を順番に語ることになった。こうなると、瑛は、水を得た魚である。やがて、瑛の語り口に全員がつり込まれ、少女たちは「名優」月岡瑛の表情を頬を染めて見つめている。
遠く同じ調子で繰り返される波濤の音。海風にガタガタ音を立てる小屋の窓や扉。ほの明るいランプの灯りが、小屋が揺れるたびに皆の影を揺らす。時おり、海から走ってきた風が、あたりの木立や草むらをかき分けながら小屋にぶつかり、裏手の林に散ってゆく。今夜は風が強い。秋を前にして、海も荒れ始めたようだ。ランプに照らされた瑛の顔が、皆を見渡した。
「そう。こんな嵐の晩なんだよ。鬼火が立つのはね・・・」
この小屋がある入り江の断崖の上に古墳らしいものがある。その古墳に、嵐の晩に鬼火が立つというのだ。それも、時には幾筋もの青白い炎が古墳の上に列をなして立つことがある。
瑛は、このあたりの古老から聞き出した話を彼流にアレンジして巧みに語った。
古墳の鬼火の話は、このあたりでは知られた話で、他にも聞き知っている者は居たが、瑛のようにリアルには語れない。
「沖を積荷やお客を載せた船が通るとね、鬼火がひとつ・・・またひとつ・・と立って、この小さな入り江の上に、青い炎が灯台のように立つんだ。そして、舞い始める。青白い炎の乙女たちの姿で、舞いながらね・・・沖を行く船を誘うんだ」
皆は息をつめて瑛の語りを聞く。
「船は、鬼火の舞を灯台の明かりと勘違いするのかもしれない。あるいは・・・舵取りたちは、炎の乙女たちの舞に迷わされ、誘われて、この入り江に向かってくる。この入り江は、小さくて浅い。いたるところに岩礁もある。誰かが、船に気づいた。大変だ。あの船は、あの大きさじゃ座礁して沈んでしまう。何とか知らせなきゃ・・・で、必死に船に呼びかけるんだ・・・・」
「おおーいっ!」
突然、小屋の外で誰かの叫び声が聞こえた。
「きゃあーっ」「うわーっ」
小屋の若者たちが思わず叫び声をあげた。
「ちぇっ。誰だよ」
話の腰を折られた恰好で瑛がぼやいた。
若者たちが溜息をつく。・・・いいところだったのに。
「おーいっ! 危ないぞーっ! こっちじゃない」
「まわせーっと! まわせーっ!」
外で何か起きているらしい。だんだん人が増えてきたようだ。
本当に、何か大変なことが起きているらしいぞ。
瑛は、席を立って小屋の扉を開けた。
小屋に海風が吹き込む。
「何だぁ? 何があった?」
「船だ。でかい船が! こっちへ来るんだ」
小屋の前を走りぬけようとしていた男が叫んだ。
「何だって?」
瑛を先頭に、若者たちが小屋から飛び出した。
日暮れ前とはまったく違う、荒れ狂う海が目の前にある。
強い風にちぎられた雲の断片が激しく夜空を流れてゆく。
その雲の切れ間から月が覗く。
一瞬、その光に照らされて、巨大な船の影がすぐそこにそそり立った。
「あんなでかい船が・・・あいつら、岬の灯台を知らないのか?」
誰かが叫んだ。
瑛の背筋が凍った。
後ろだ。後ろを・・・
振り向いた瑛の目に、入り江の断崖が見えた。こっちは雲がはれている。月光に染まり、磨き上げられた鏡のような冷たい夜空を背景に、断崖の上。古墳。そして、鬼火。幾筋もの鬼火が、青い炎が立ち、風に身を任せながら舞っている。
鬼火。炎の舞。火の乙女。
「鬼火! あれ。鬼火!」
「火の乙女だ!」
「火だ。あそこ・・・鬼火!」
轟音が入り江にとどろいた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
夏の終わりの収穫祭である。
苫小牧の農場で行われる収穫祭は、一農場の主催だったが、いまでは町のちょっとしたイベントに育ってきている。
「収穫祭」というちょっとハイカラな響きもあるが、何より、農場の産物や、それらを使ったちょっと珍しい料理の出店や、夕刻に行われる歌合戦や演芸合戦が呼び物になっており、近隣の町村からも老若男女が訪れる。
ところが、今年の収穫祭では、とくに、若者たちにとっては奇妙なことが起きていた。
祭りは最高潮に達しようとしているというのに、あの月岡瑛(あきら)は無口で、時には不機嫌にさえ見えたのである。
おかしなこともあるものだ。
農場やこのあたりの人々は、およそ「不機嫌な月岡瑛」というものを見たことがない。もちろん「無口な瑛」というのも論外である。
月岡瑛という少年は、いつも陽気である。
陽気が歩いているというのが、月岡瑛なのだ。
彼はのべつ、仕事中でも、街を歩いているときでも、草っ原に寝転んで寛いでいるときでさえ、鼻歌をうたっているか、口笛を吹いているか、誰かとおしゃべりしているか、といって五月蝿いとか鬱陶しいというわけでもなく、ちょうど太陽が陽光というものを放出しながら、あちこちに陽だまりを置いてまわるように、歌やおしゃべりで、周りの人々の懐に陽気という気分を放り込んでまわっているような性質(たち)の少年なのだ。
瑛のおしゃべりというのが、また魅力的で、どこで聞き込んできたのか、このあたりの奇勝や史跡にまつわる昔語りや伝説の類を、それは見事な身振り手振りを交えながら、実に上手く語るのである。
つまり、瑛は、このあたりではちょっと知られた名歌手であり、名優であり、すぐれた舞手であり、祭りともなれば、主役として、率先垂範して近隣の少年少女たちを束ね、祭りを盛り上げるリーダーなのである。
それが、はじめのうちは、いつもどおり、元気いっぱいに祭りを仕切っていたのだが、昼を過ぎ、祭りがいよいよ佳境を迎えるという段になって、なんだか元気がなくなってきた。日が傾いて、歌合戦だのかくし芸だのと一番盛り上がってきたあたりで、ついに「無口で不機嫌な瑛」という、いまだかつて誰も見たことがない情況を呈してしまったのだ。
そして、あろうことか、歌合戦で、あの瑛が歌詞を忘れ、絶句してしまった。当然のことながら、瑛は一等賞はおろか入賞さえしなかった。ありえないことである。
「瑛はどうかしちまったんじゃないか? 上の空だったぞ」
「今日の月岡さん、変だわ」
「病気だな、これは。それも医者も薬も利かない病だ・・・へへぇ」
「ええーっ? で、誰だ、その病の元は」
「知らんよ。見当もつかん。だが・・・間違いないな、あれは・・・病だ」
訳知り顔の年配者が勝手な憶測を述べれば、辺りに居たいく人かの少女たちが騒ぐ。
一週間前「お前に会いたがってる娘っこがわんさと居る」と瑛が輝に言ったが、実のところ「言葉を交わしたがっている娘っこがわんさと居る」のは瑛のほうだった。
そう、その輝である。
瑛を上の空にさせているのは、どこかのお嬢さんではなく、輝なのだ。
「輝は『来る』と言った。来る、と言ったら来る。あいつはそういうやつだ。万一、来られなくなったとしたら・・・ちゃんと断りを入れてくるはずだ。断り無しに約束を違えるやつじゃない。じゃあ、何で来ないんだろ・・・」
「星さんが見えてた。仕事がらみだって言ってた。何か関係あるのかな、でも、何か用事ができたんなら、そう言ってよこすはずだ。じゃあ、何で何も言ってこないんだ」
「何か事故でもあったんだろうか。でも、あの親父さんやお袋さん、それに男爵様だって居るんだ。何かあったのしても誰かが・・・そうだ、男爵様はまだいらっしゃるんだろうか・・・それにしても、何で、誰も何も言ってよこさないんだろう」
「そういえば、あいつ、坑内に変な気配がするって言ってた。やっぱり何かあったんだろうか。それにしても、この一週間、そんな話も何も言ってこなかった。何で、何も・・・あああ・・・わからない。変だよ。とにかく・・・」
ぐるぐる、ぐるぐると「何で」「何で」が瑛の頭の中を経巡った。結局、行き着くところは、とにかく・・・
「明日、朱鳥坑に行ってみよう」
それしかない。そのくらいしかできることはないのである。
それしかないとわかると、瑛は少し元気を取り戻し、いつもの瑛になった。元来、考え続けることは、瑛の性には合わない。
明朝になったら朱鳥坑に行くことに決めた瑛は、祭りがはねた後の夕刻、海辺近くの小屋に、集まった若者たち、少年少女たちを集めて、いつもどおり怪談の口火を切った。
毎年、収穫祭がはねた後、祭りに集まった少年たちと少女たちがこの小屋に泊まりこんで、夜っぴて宴会を催すのが倣いになっている。ちょっと昔なら若衆組と娘組の、もっと昔なら歌垣みたいなものだ。いわば、夏祭りの場で許される「グループ交際」の元祖である。
今年は、百物語よろしく、怪談や不思議な体験談を順番に語ることになった。こうなると、瑛は、水を得た魚である。やがて、瑛の語り口に全員がつり込まれ、少女たちは「名優」月岡瑛の表情を頬を染めて見つめている。
遠く同じ調子で繰り返される波濤の音。海風にガタガタ音を立てる小屋の窓や扉。ほの明るいランプの灯りが、小屋が揺れるたびに皆の影を揺らす。時おり、海から走ってきた風が、あたりの木立や草むらをかき分けながら小屋にぶつかり、裏手の林に散ってゆく。今夜は風が強い。秋を前にして、海も荒れ始めたようだ。ランプに照らされた瑛の顔が、皆を見渡した。
「そう。こんな嵐の晩なんだよ。鬼火が立つのはね・・・」
この小屋がある入り江の断崖の上に古墳らしいものがある。その古墳に、嵐の晩に鬼火が立つというのだ。それも、時には幾筋もの青白い炎が古墳の上に列をなして立つことがある。
瑛は、このあたりの古老から聞き出した話を彼流にアレンジして巧みに語った。
古墳の鬼火の話は、このあたりでは知られた話で、他にも聞き知っている者は居たが、瑛のようにリアルには語れない。
「沖を積荷やお客を載せた船が通るとね、鬼火がひとつ・・・またひとつ・・と立って、この小さな入り江の上に、青い炎が灯台のように立つんだ。そして、舞い始める。青白い炎の乙女たちの姿で、舞いながらね・・・沖を行く船を誘うんだ」
皆は息をつめて瑛の語りを聞く。
「船は、鬼火の舞を灯台の明かりと勘違いするのかもしれない。あるいは・・・舵取りたちは、炎の乙女たちの舞に迷わされ、誘われて、この入り江に向かってくる。この入り江は、小さくて浅い。いたるところに岩礁もある。誰かが、船に気づいた。大変だ。あの船は、あの大きさじゃ座礁して沈んでしまう。何とか知らせなきゃ・・・で、必死に船に呼びかけるんだ・・・・」
「おおーいっ!」
突然、小屋の外で誰かの叫び声が聞こえた。
「きゃあーっ」「うわーっ」
小屋の若者たちが思わず叫び声をあげた。
「ちぇっ。誰だよ」
話の腰を折られた恰好で瑛がぼやいた。
若者たちが溜息をつく。・・・いいところだったのに。
「おーいっ! 危ないぞーっ! こっちじゃない」
「まわせーっと! まわせーっ!」
外で何か起きているらしい。だんだん人が増えてきたようだ。
本当に、何か大変なことが起きているらしいぞ。
瑛は、席を立って小屋の扉を開けた。
小屋に海風が吹き込む。
「何だぁ? 何があった?」
「船だ。でかい船が! こっちへ来るんだ」
小屋の前を走りぬけようとしていた男が叫んだ。
「何だって?」
瑛を先頭に、若者たちが小屋から飛び出した。
日暮れ前とはまったく違う、荒れ狂う海が目の前にある。
強い風にちぎられた雲の断片が激しく夜空を流れてゆく。
その雲の切れ間から月が覗く。
一瞬、その光に照らされて、巨大な船の影がすぐそこにそそり立った。
「あんなでかい船が・・・あいつら、岬の灯台を知らないのか?」
誰かが叫んだ。
瑛の背筋が凍った。
後ろだ。後ろを・・・
振り向いた瑛の目に、入り江の断崖が見えた。こっちは雲がはれている。月光に染まり、磨き上げられた鏡のような冷たい夜空を背景に、断崖の上。古墳。そして、鬼火。幾筋もの鬼火が、青い炎が立ち、風に身を任せながら舞っている。
鬼火。炎の舞。火の乙女。
「鬼火! あれ。鬼火!」
「火の乙女だ!」
「火だ。あそこ・・・鬼火!」
轟音が入り江にとどろいた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月01日
第六章:瑛(あきら)の災難 その2
<瑛の災難 その2>
「ああーっ! やっちまったぞーっ!」
船が岩礁に乗り上げたのだ。
ガリガリ! バリバリ!
波と風の音を押しのけて、人工物が壊れる音が海辺の人々の耳を刺す。
巨大な船腹が岩に擦れ、傾き、破れ、はらわたがこぼれ出していく。
「おい! 出せる船はあるか」
「とにかく、人を集めるんだ」
誰ともなく、難破船を助けるために動き始めた。
一瞬は「鬼火」に呆然とした瑛だったが、すぐに気を取り直し、年かさの少年たちを指揮して、皆で難破船の救助にあたった。
船は、すぐ目の前と言っていい。
何名かの船員たちが、波にもまれながら、早くも岸近くに泳ぎ着こうとしている。
船は大きく傾き、船上から積荷や船員たちが海に、あるものは落ち、あるものは飛び込む。
それらを、いつの間にか集まってきた町の人々が、小船を出したり、海に入って助け出そうとしている。
瑛は、泳ぎが得意で、自信もあったから、小船での救助は仲間たちに任せて、小船にたどり着けない者たちを、海に入って小船まで運んでいった。
傾いた巨大な貨物船が、風や波に弄ばれながら右に左にかしぎ、そのたびに船上や、破れた船腹から積荷がこぼれ出している。
そんな難破船を、ふと見上げた瑛の目に、何か白いものが映った。
一瞬、月光が照らす。
人だ。
船腹の隙間に、白い服が風にはためいたように見えた。
女性だ。
「おい! 貨客船だぞ。船客が乗ってたんだ!」
瑛は、小船の仲間に一声叫ぶと、難破船に向かって泳ぎ始めた。
「無茶するな! あっちは岩だらけで波が逆巻いてるんだぞ!」
「義を見てせざるは・・・何だっけ・・うわっぷ」
「瑛ぁっ! おいっ!」
「ええくそっ・・・俺は大丈夫だよっ・・・」
一瞬、波をかぶった瑛は、難破船をにらみながら勢いよく水を掻いて岩礁のほうに向かった。
白い服の女性が船腹から何とか下に降りようとしている。
でも、あのあたりは、さっき仲間が言ったとおり、岩礁があって下は岩だらけで、荒波が不規則に渦巻いている。下手に降りたら危ない。
月が雲間から覗くのと、突風が彼女を煽るのが同時だった。白い服が星のように煌き、一瞬、凧のように風に舞ったと思った途端、彼女は海に落下し、逆巻く波の大きなうねりが、まるでそれを待っていたかのように掴み取ったように見えた。
くそぉっ! 何とか・・・間に合ってくれよぉっ!
やっと難破船の近くにたどり着いた瑛は、波間に一瞬浮かんだ白いものを必死で掴む。
つかまえた!
腕だ。
瑛は、腕を掴んで、彼女の身体を手繰り寄せ、抱きとめる。
思ったより小柄だな。
「おいっ! 大丈夫か? おいっ! しっかり・・・」
月光が女性の顔を照らす。
女の子だ。
なんて白い。お月さんみたいな・・・
そのとき、船腹と岩礁にぶつかって巻き上げられた大きな波頭が彼らを激しく打った。
「しまった!」
波にもまれながら、白い少女をかばい、抱きしめながら耐える。
ガスン
いやな音が頭の中に響く。全身に痛みが走り、頭の中が熱くなる。
やっちまった・・・な。
岩場に打ちつけられた瑛の意識がうすらいでゆく。
少女を抱きしめたまま、残された力で、打ちつけられた岩場の上に這い上がり、そのまま仰向けに倒れた。
風や波、人々の声がだんだんと遠くなる。
静かだな。
目だけが、変に冴えていやがる。
すぐ横に、透きとおるように白い少女の顔が見えた。
胸元がゆっくり上がり、下がる。
よかった・・・まだ生きてる。
空を見る。
頭上に、次から次へと走り去る雲たちを切り裂いて、青白い月が見下ろしている。
岸のほうを見やる。
断崖の上。
青い鬼火。火の乙女が、まだ嗤いながら舞っている。
くっそぉっ!
「・・・おーい・・・おーい・・・」
遠くで・・・誰か・・・呼んでる。
そして、闇が訪れた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「ああーっ! やっちまったぞーっ!」
船が岩礁に乗り上げたのだ。
ガリガリ! バリバリ!
波と風の音を押しのけて、人工物が壊れる音が海辺の人々の耳を刺す。
巨大な船腹が岩に擦れ、傾き、破れ、はらわたがこぼれ出していく。
「おい! 出せる船はあるか」
「とにかく、人を集めるんだ」
誰ともなく、難破船を助けるために動き始めた。
一瞬は「鬼火」に呆然とした瑛だったが、すぐに気を取り直し、年かさの少年たちを指揮して、皆で難破船の救助にあたった。
船は、すぐ目の前と言っていい。
何名かの船員たちが、波にもまれながら、早くも岸近くに泳ぎ着こうとしている。
船は大きく傾き、船上から積荷や船員たちが海に、あるものは落ち、あるものは飛び込む。
それらを、いつの間にか集まってきた町の人々が、小船を出したり、海に入って助け出そうとしている。
瑛は、泳ぎが得意で、自信もあったから、小船での救助は仲間たちに任せて、小船にたどり着けない者たちを、海に入って小船まで運んでいった。
傾いた巨大な貨物船が、風や波に弄ばれながら右に左にかしぎ、そのたびに船上や、破れた船腹から積荷がこぼれ出している。
そんな難破船を、ふと見上げた瑛の目に、何か白いものが映った。
一瞬、月光が照らす。
人だ。
船腹の隙間に、白い服が風にはためいたように見えた。
女性だ。
「おい! 貨客船だぞ。船客が乗ってたんだ!」
瑛は、小船の仲間に一声叫ぶと、難破船に向かって泳ぎ始めた。
「無茶するな! あっちは岩だらけで波が逆巻いてるんだぞ!」
「義を見てせざるは・・・何だっけ・・うわっぷ」
「瑛ぁっ! おいっ!」
「ええくそっ・・・俺は大丈夫だよっ・・・」
一瞬、波をかぶった瑛は、難破船をにらみながら勢いよく水を掻いて岩礁のほうに向かった。
白い服の女性が船腹から何とか下に降りようとしている。
でも、あのあたりは、さっき仲間が言ったとおり、岩礁があって下は岩だらけで、荒波が不規則に渦巻いている。下手に降りたら危ない。
月が雲間から覗くのと、突風が彼女を煽るのが同時だった。白い服が星のように煌き、一瞬、凧のように風に舞ったと思った途端、彼女は海に落下し、逆巻く波の大きなうねりが、まるでそれを待っていたかのように掴み取ったように見えた。
くそぉっ! 何とか・・・間に合ってくれよぉっ!
やっと難破船の近くにたどり着いた瑛は、波間に一瞬浮かんだ白いものを必死で掴む。
つかまえた!
腕だ。
瑛は、腕を掴んで、彼女の身体を手繰り寄せ、抱きとめる。
思ったより小柄だな。
「おいっ! 大丈夫か? おいっ! しっかり・・・」
月光が女性の顔を照らす。
女の子だ。
なんて白い。お月さんみたいな・・・
そのとき、船腹と岩礁にぶつかって巻き上げられた大きな波頭が彼らを激しく打った。
「しまった!」
波にもまれながら、白い少女をかばい、抱きしめながら耐える。
ガスン
いやな音が頭の中に響く。全身に痛みが走り、頭の中が熱くなる。
やっちまった・・・な。
岩場に打ちつけられた瑛の意識がうすらいでゆく。
少女を抱きしめたまま、残された力で、打ちつけられた岩場の上に這い上がり、そのまま仰向けに倒れた。
風や波、人々の声がだんだんと遠くなる。
静かだな。
目だけが、変に冴えていやがる。
すぐ横に、透きとおるように白い少女の顔が見えた。
胸元がゆっくり上がり、下がる。
よかった・・・まだ生きてる。
空を見る。
頭上に、次から次へと走り去る雲たちを切り裂いて、青白い月が見下ろしている。
岸のほうを見やる。
断崖の上。
青い鬼火。火の乙女が、まだ嗤いながら舞っている。
くっそぉっ!
「・・・おーい・・・おーい・・・」
遠くで・・・誰か・・・呼んでる。
そして、闇が訪れた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月03日
第七章:黒水晶 その1
<第七章:黒水晶 その1>
「・・・おーい・・・おぉおい・・・」
誰かの声が聞こえる。
「・・・おおーい・・・おーい・・・」
遠くのほうで、誰かが呼んでる。
ざわざわ、ざわざわ・・・たくさんの人が、何か話し合ってる。
しゅうしゅう、がたんがたん、蒸気の音、機械の騒音。
それに・・・サイレンだ。いやな音。サイレンは嫌いだ。
「・・・無理だ・・・無理だよ」
「あきらめろってぇのか」
「でも、今、下に行くのは危険すぎる」
「だが、ああやって呼んでるんだ。生きてるんだぞ」
「今、下に行けば戻れない。犠牲が増えるだけだぞ」
「そうとは限らんだろうが」
「・・・おーい・・・・おおい・・・」
とうちゃん。
かあちゃん。
とうちゃんも、かあちゃんも『した』ってところにいるんだろうか
「・・・おーい・・・おぉい・・・お・・・い・・・」
とうちゃんと、かあちゃんが『した』で呼んでるんだろうか
「何してるんだ。お前ら!」
「相談してるんだ。どうするか」
「相談だと。あの声が聞こえないのか。呼んでるじゃないか。生きてるじゃないか」
「だから・・・」
「おい! 行くぞ。 昇降機(リフト)降ろせ!」
「無茶だ」
「ばかやろう。 おい! お前、それからお前、ついて来い」
「おう!」
「無茶だ。 やめろ。 今行ったら、お前らも戻れんぞ」
「行かんのなら黙ってろ! 昇降機! 降ろせ」
「おい! おおい! やめろよ! トオル! おーい!」
「・・・おーい・・・おおい・・・お・・・い・・・」
「おーい トオルぅー! やめろぉ! ・・・おーい・・・戻れぇー・・・トオルぅー・・・」
「・・・おおい・・・おぉぉぃ・・・ぉ・・・ぃ」
とうちゃん・・・かあちゃん・・・呼んでるんか・・・
トオル?・・・親父(おやじ)さん・・・親父さんが・・・呼んでるんか?
ああ。 眩しい。 どこだ・・・。
「オオ。 目が・・・気がつかれたのですね!」
ええっ? 眩しい! あぁ? あ・・・痛っ・・・いたた・・・。
「ああ。 動かないで。 そのまま・・・先生! 先生! ツキオカさんが!」
月岡さん? ここは・・・どこだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「・・・おーい・・・おぉおい・・・」
誰かの声が聞こえる。
「・・・おおーい・・・おーい・・・」
遠くのほうで、誰かが呼んでる。
ざわざわ、ざわざわ・・・たくさんの人が、何か話し合ってる。
しゅうしゅう、がたんがたん、蒸気の音、機械の騒音。
それに・・・サイレンだ。いやな音。サイレンは嫌いだ。
「・・・無理だ・・・無理だよ」
「あきらめろってぇのか」
「でも、今、下に行くのは危険すぎる」
「だが、ああやって呼んでるんだ。生きてるんだぞ」
「今、下に行けば戻れない。犠牲が増えるだけだぞ」
「そうとは限らんだろうが」
「・・・おーい・・・・おおい・・・」
とうちゃん。
かあちゃん。
とうちゃんも、かあちゃんも『した』ってところにいるんだろうか
「・・・おーい・・・おぉい・・・お・・・い・・・」
とうちゃんと、かあちゃんが『した』で呼んでるんだろうか
「何してるんだ。お前ら!」
「相談してるんだ。どうするか」
「相談だと。あの声が聞こえないのか。呼んでるじゃないか。生きてるじゃないか」
「だから・・・」
「おい! 行くぞ。 昇降機(リフト)降ろせ!」
「無茶だ」
「ばかやろう。 おい! お前、それからお前、ついて来い」
「おう!」
「無茶だ。 やめろ。 今行ったら、お前らも戻れんぞ」
「行かんのなら黙ってろ! 昇降機! 降ろせ」
「おい! おおい! やめろよ! トオル! おーい!」
「・・・おーい・・・おおい・・・お・・・い・・・」
「おーい トオルぅー! やめろぉ! ・・・おーい・・・戻れぇー・・・トオルぅー・・・」
「・・・おおい・・・おぉぉぃ・・・ぉ・・・ぃ」
とうちゃん・・・かあちゃん・・・呼んでるんか・・・
トオル?・・・親父(おやじ)さん・・・親父さんが・・・呼んでるんか?
ああ。 眩しい。 どこだ・・・。
「オオ。 目が・・・気がつかれたのですね!」
ええっ? 眩しい! あぁ? あ・・・痛っ・・・いたた・・・。
「ああ。 動かないで。 そのまま・・・先生! 先生! ツキオカさんが!」
月岡さん? ここは・・・どこだ。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月11日
第七章:黒水晶 その2
<第七章:黒水晶 その2>
まぶしい。
眩しさに耐えて、ゆっくりと、おそるおそる開けた目に、だんだんと月のように白い顔が浮かんだ。
眩しい。
瑛は、その顔をただしばらく見つめていた。やがて、お月様のように白い顔が、お日様のように微笑んだ。
「よかった。目が覚めたのですね」
「ああ? ああ・・・君は・・・」
そうだ、あの時、月光に照らされていた、あの少女の顔。
瑛は身体を起こそうとしたが、思うように起き上がれない。
「あ・・痛!」
「まだ、無理をしてはいけません。今、お医者様をお呼びしましたから」
寒い。が、手が暖かい。
少女の白い両手が瑛の手をやさしくくるんでいる。
瑛は、思わず手を引っ込めようとしたが、思うように動かなかった。
そんな瑛の手の動きに気づいたのか、少女は少し力をこめて瑛の手を握りなおした。そして、
「あなたは、わたくしの命の恩人です」
と言って、またお日様のような笑顔を見せた。
瑛は三日間寝込んでいたらしい。とすると今日は火曜日か。月曜に輝のところに行くつもりだったが、怪我をしてしまったのでは仕方がない。
全身打撲と脳震盪、それに肋骨を少し折っていたが、他には数箇所の擦り傷や切り傷があったが、大きな外傷はなく、内臓にも損傷はない。二三日安静にしていればよろしいということで、まずは一安心だ。
少女のほうは、瑛がかばったために、どこにも怪我はなく、溺れてしばらく気を失っただけだということだった。瑛と同じ病院に担ぎ込まれたが、すぐに体力は回復し、こん睡状態の瑛のそばにつききりだったのだ。
瑛は輝のことが気にはなったが、医者の言うとおり二三日病院で身体を休めて、土曜にでも朱鳥坑に様子を見に行くことにした。それに、病室には、願ってもない素敵な話し相手が居てくれるのだ。
少女は、欧州から来たと言う。
瑛は、以前にも欧州人を見かけたことはあったが、彼の知っている欧州人は、男も女も背が高く、体格がよくて、肌は同じように白かったが、月のようなつややかな肌ではなく、もっと素焼きの土人形のような感じだった。もっとも、この少女のような若い異国人は見かけたことがなかったが・・・。しかし、今までに見かけた欧州人と大きく異なるのは、髪の色と目の色だった。少女の髪は濃い栗色、瞳は茶で、きめ細かい肌とともに、どこか東洋的な香りを漂わせている。それに、おどろくべきことに、この欧州から来たと言う少女は、日本語を流暢に話した。
「ツキオカ・・・アキラさん、とおっしゃるのですね。月、丘、アキラは・・・あなたの場合は・・・光に照らされている・・ということか知らん。素敵な名前ですね」
「そりゃ・・・どうも。名前を褒められたのは初めてだよ。君は?」
「あ。ごめんなさい。わたくしの名前は『ソフィ』です。苗字は『ナプホルト』と言います」
「ナ・・・ナポート? ソフィ・・・さん?」
「ナプ、ホルトです。でも、どうかソフィと呼んでください」
「どんな意味なんですか?」
「『ナプホルト』は、先祖の故郷の言葉で『お日様とお月様』という意味になります」
「故郷ってどんなところ? 俺・・・ぼくは、欧州のことは知らないんだけど」
「欧州の東のほうの内陸です。ハンガリーと言って、大昔にアジアから馬に乗ってやって来た一族の末裔が住み着いたのだそうです。ですから、わたくしにも東洋の血が残っているかもしれませんね。今、住んでいるのはドイツです」
「へええ、なるほど。じゃ、名前のほう『ソフィ』は?」
「古い欧州の言葉で『知恵』のことです。父がくれた名前です」
「『知恵』かぁ・・・じゃ、『知恵さん』ですね」
少女がお日様のように笑った。
海で助けあげたときに、瑛は「女の子だ」と思ったし、実際、今、病室で話していても華奢な感じがする。それに、ソフィが着ている服は、あのとき着ていた白いふんわりしたドレス(実のところ寝巻きだったのだろうが)ではなく、濃紺のぴったりしたオーバースカートに大きな襟をつけた白いブラウスだったから、どこかの寄宿学校の生徒さんのようにも見える。でも、話しぶりは、どこかできちんと習い覚えた丁寧な日本語ということもあるのだろうが落ち着いているし、どうかすると学校の先生のような物腰を見せることがある。
よくよく話しを聞いてみると、ソフィは十七歳の、それも大学生だった。人類学、つまり言語学や考古学の研究員で、知人とともに学術調査を兼ねて旅行中だったと言う。学問の分野としては、まだ新しい。この時期、ドイツでは新しい学問や新しい芸術の運動が盛んで、彼女は、そんな新しい学術分野に身をおく気鋭の研究者の卵といったところだ。
ソフィが、とくに北海道を訪問地に選んだのは、ここに北方アジアの言葉、伝承、遺物などが豊富にあり、フィールドワークによって、そういった研究素材を記録収集するためだったのだが、近隣の昔話や遺跡の伝承を聞きまわっては仲間に話して聞かせる、彼女の命の恩人、瑛は、彼女の最初のフィールドワークの素材となったわけである。もちろん、瑛にとってもソフィは最高の聞き手ということだ。
ソフィは瑛の話を目を輝かせて聞き、そして質問した。瑛にとっては、自分の語る話がこんなふうにしっかりと受け止められるのは初めての経験だった。ソフィも、瑛の生き生きとした話しぶりや、質問に対する受け答えから、瑛がその生い立ちからたまたま無学であっただけで、実際は聡明で優れたフィールドワーカーであることがわかった。あの荒れた海で偶然出会った二人だったが、彼らは、お互いが、言葉や物語を紡いだり、織ったり、あるいはそれらを解いたりすることの喜びや素晴らしさを分かち合うことのできる得がたい同志だったことを知った。そんな二人が互いに惹かれあうのに、そんなに多くの時間は要さない。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
まぶしい。
眩しさに耐えて、ゆっくりと、おそるおそる開けた目に、だんだんと月のように白い顔が浮かんだ。
眩しい。
瑛は、その顔をただしばらく見つめていた。やがて、お月様のように白い顔が、お日様のように微笑んだ。
「よかった。目が覚めたのですね」
「ああ? ああ・・・君は・・・」
そうだ、あの時、月光に照らされていた、あの少女の顔。
瑛は身体を起こそうとしたが、思うように起き上がれない。
「あ・・痛!」
「まだ、無理をしてはいけません。今、お医者様をお呼びしましたから」
寒い。が、手が暖かい。
少女の白い両手が瑛の手をやさしくくるんでいる。
瑛は、思わず手を引っ込めようとしたが、思うように動かなかった。
そんな瑛の手の動きに気づいたのか、少女は少し力をこめて瑛の手を握りなおした。そして、
「あなたは、わたくしの命の恩人です」
と言って、またお日様のような笑顔を見せた。
瑛は三日間寝込んでいたらしい。とすると今日は火曜日か。月曜に輝のところに行くつもりだったが、怪我をしてしまったのでは仕方がない。
全身打撲と脳震盪、それに肋骨を少し折っていたが、他には数箇所の擦り傷や切り傷があったが、大きな外傷はなく、内臓にも損傷はない。二三日安静にしていればよろしいということで、まずは一安心だ。
少女のほうは、瑛がかばったために、どこにも怪我はなく、溺れてしばらく気を失っただけだということだった。瑛と同じ病院に担ぎ込まれたが、すぐに体力は回復し、こん睡状態の瑛のそばにつききりだったのだ。
瑛は輝のことが気にはなったが、医者の言うとおり二三日病院で身体を休めて、土曜にでも朱鳥坑に様子を見に行くことにした。それに、病室には、願ってもない素敵な話し相手が居てくれるのだ。
少女は、欧州から来たと言う。
瑛は、以前にも欧州人を見かけたことはあったが、彼の知っている欧州人は、男も女も背が高く、体格がよくて、肌は同じように白かったが、月のようなつややかな肌ではなく、もっと素焼きの土人形のような感じだった。もっとも、この少女のような若い異国人は見かけたことがなかったが・・・。しかし、今までに見かけた欧州人と大きく異なるのは、髪の色と目の色だった。少女の髪は濃い栗色、瞳は茶で、きめ細かい肌とともに、どこか東洋的な香りを漂わせている。それに、おどろくべきことに、この欧州から来たと言う少女は、日本語を流暢に話した。
「ツキオカ・・・アキラさん、とおっしゃるのですね。月、丘、アキラは・・・あなたの場合は・・・光に照らされている・・ということか知らん。素敵な名前ですね」
「そりゃ・・・どうも。名前を褒められたのは初めてだよ。君は?」
「あ。ごめんなさい。わたくしの名前は『ソフィ』です。苗字は『ナプホルト』と言います」
「ナ・・・ナポート? ソフィ・・・さん?」
「ナプ、ホルトです。でも、どうかソフィと呼んでください」
「どんな意味なんですか?」
「『ナプホルト』は、先祖の故郷の言葉で『お日様とお月様』という意味になります」
「故郷ってどんなところ? 俺・・・ぼくは、欧州のことは知らないんだけど」
「欧州の東のほうの内陸です。ハンガリーと言って、大昔にアジアから馬に乗ってやって来た一族の末裔が住み着いたのだそうです。ですから、わたくしにも東洋の血が残っているかもしれませんね。今、住んでいるのはドイツです」
「へええ、なるほど。じゃ、名前のほう『ソフィ』は?」
「古い欧州の言葉で『知恵』のことです。父がくれた名前です」
「『知恵』かぁ・・・じゃ、『知恵さん』ですね」
少女がお日様のように笑った。
海で助けあげたときに、瑛は「女の子だ」と思ったし、実際、今、病室で話していても華奢な感じがする。それに、ソフィが着ている服は、あのとき着ていた白いふんわりしたドレス(実のところ寝巻きだったのだろうが)ではなく、濃紺のぴったりしたオーバースカートに大きな襟をつけた白いブラウスだったから、どこかの寄宿学校の生徒さんのようにも見える。でも、話しぶりは、どこかできちんと習い覚えた丁寧な日本語ということもあるのだろうが落ち着いているし、どうかすると学校の先生のような物腰を見せることがある。
よくよく話しを聞いてみると、ソフィは十七歳の、それも大学生だった。人類学、つまり言語学や考古学の研究員で、知人とともに学術調査を兼ねて旅行中だったと言う。学問の分野としては、まだ新しい。この時期、ドイツでは新しい学問や新しい芸術の運動が盛んで、彼女は、そんな新しい学術分野に身をおく気鋭の研究者の卵といったところだ。
ソフィが、とくに北海道を訪問地に選んだのは、ここに北方アジアの言葉、伝承、遺物などが豊富にあり、フィールドワークによって、そういった研究素材を記録収集するためだったのだが、近隣の昔話や遺跡の伝承を聞きまわっては仲間に話して聞かせる、彼女の命の恩人、瑛は、彼女の最初のフィールドワークの素材となったわけである。もちろん、瑛にとってもソフィは最高の聞き手ということだ。
ソフィは瑛の話を目を輝かせて聞き、そして質問した。瑛にとっては、自分の語る話がこんなふうにしっかりと受け止められるのは初めての経験だった。ソフィも、瑛の生き生きとした話しぶりや、質問に対する受け答えから、瑛がその生い立ちからたまたま無学であっただけで、実際は聡明で優れたフィールドワーカーであることがわかった。あの荒れた海で偶然出会った二人だったが、彼らは、お互いが、言葉や物語を紡いだり、織ったり、あるいはそれらを解いたりすることの喜びや素晴らしさを分かち合うことのできる得がたい同志だったことを知った。そんな二人が互いに惹かれあうのに、そんなに多くの時間は要さない。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月13日
第七章:黒水晶 その3
<第七章:黒水晶 その3>
瑛は、もの心ついたときには炭坑夫の息子として炭坑町に育った。気づいたときには、ともに育った輝とともに大人たちに交じって坑内で働いていたし、暁幌閉山の後は農場で大地を相手に、額に汗して働き続けてきたのである。つまりは、根っからの労働者階級だったわけであるが、そんな瑛が、異国の、それも学術の世界にどっぷりと浸っている「インテリ」の少女と学芸の世界をはさんで意気投合するというのは、一見奇妙なことではある。
もっとも、彼は仲間の少年たちとは異なり、子供の頃から近隣の大人たちや古老から昔話を聞いたり、古い歌を習ったり、謎めいた遺跡や奇妙な形をした岩のことや、そのいわれを教わるのが大好きな「変わった」男の子だった。その人懐っこい様子からは想像がつかないが、元来が孤独で、想像の世界にひっそりと自分を羽ばたかせることのできるロマンチストなのである。彼が鼻歌を歌ったり、口笛を吹き鳴らしているとき、不思議な物語を仲間に語って聞かせているとき、彼は機嫌がいいというのではない。そんなとき、彼は周囲の現実世界を想像の世界に塗り替えて、その世界にひとり立っている自分の姿を見つめているのだ。多くの仲間たちが彼の声に聴き入ったり、彼の物語に酔っているときほど、彼自身は彼の孤独をじっと眺めている。そして、思考する。言葉ではなく、身体で。学がないから、難しい言葉は知らないから、言葉にならない感性で思考するのである。何を、何のために、という命題は無い。その思考は言葉ではないから。
だから、彼は哲学者ではない。強いて言えば芸術家である。もちろん、そんな言葉を彼は思うこともない。彼の現実は、坑夫あがりの農夫である。
瑛に比べれば、親友の輝のほうは、とうに枯れてしまったはずの暁幌の坑内に住んで、地下世界で父親とともに幾年も、まだ見ぬ炭層を探して歩いているロマンチストに見えるが、輝は実のところ、そのもの静かな風貌や言動からは想像がつかないが、鉄の意志を持ったリアリストなのである。考え、準備をし、目的と目標を立てて、いったん始めれば決して引き下がらない。
幼くして事故で両親を失った瑛は、現実世界では、運命をあるがままに受け入れ、なすがままに生きてきた。幼馴染の輝の一家に引き取られ、一緒に育ち、ともに炭坑で働き、閉山後は、近くの農場に働き口があったからそこで懸命に働いた。ただ、それだけのことである。そして、いつのまにか、身体を現実世界に馴染ませながら心を異界に泳がせることを自然に身に付けてしまったに過ぎない。ただ、どちらが瑛の本来であったか。少なくとも、今の瑛にとっては、想像の世界で己に向かって放つしかなかった思考を受け止め、言葉という手がかりを返してくれる新たな存在が現実世界に現れたのであるから、異界に遊んでいた自分こそが自身の本来だということになる。
このソフィと過ごした二日間は、瑛にとっての世界を、その広さも深さも幾倍にも大きなものにした。
たとえば、瑛の大好きな昔話や伝説には、アイヌの伝承にまつわるものが少なくない。アイヌの人々が北海道の先住者であることも、自分たちが維新以後、北海道に移殖してきた「和人」であることも、知識としては承知していた。しかし、それを、たとえば「民族」とか「差別」とかいった社会の問題として意識することはなかった。彼にとってアイヌという存在は、たとえば、星男爵のような華族様が居て、役人や学者先生が居て、自分たちのような坑夫や農夫が居るのと同じように、あたりまえに存在するいろいろな階層のひとつに過ぎなかった。
ところが、ソフィから欧州のことなどを聞くにつけ、自分を取り巻く現実世界が、それまで知っていた以上に生々しい厚みや深さを持っていると言うことを知ったのである。
ソフィはドイツという国に住んでいる。だから、彼女はドイツ国民であることになるわけだが、彼女はハンガリー人、あるいはマジャール人なのだそうだ。ドイツという国には、ドイツ人やマジャール人だけでなく、チェコ人とかポーランド人とかユダヤ人とかがたくさん住んでいて、ドイツ人の皇帝の元で暮らしているのだという。
彼女の父祖の国はハンガリーという国だが、今は「オーストリィ・ハンガリー帝国」という奇妙な名前の国である。その昔、ハンガリー王国という国もあったらしいが、そのハンガリー王国も、ハンガリー人は半分にも満たないのにハンガリー人の王様が治めていた。今の「オーストリィ・ハンガリー帝国」は、もともとドイツの国々を従えていたオーストリィという国があって、その皇帝がハンガリーの王様を兼ねているのだそうだ。しかも、当のドイツ人もハンガリー人も、それぞれ二割程度しか住んでいない。そもそも、ドイツ人の国がいくつもあって、その国々を従えてきたドイツの皇帝が二人居て、どちらの国もドイツ人が半分も居ない。瑛にとっては想像の外である。
とにかく、この二日間で、瑛の世界観というか、社会観はめざましく変化したのである。もっと知りたい、もっと考えたい、そして、もっと感じたい。そんな「意欲」を生まれて初めて持った、というより、自分がなにげなく吸収し、育んできた知識や感性を、身に付けたいという意識を持って初めて省みたのである。
瑛が、そんな新鮮な日々を楽しんでいた木曜日の昼下がり、瑛の病室に、背の高い異国の青年が現れた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
瑛は、もの心ついたときには炭坑夫の息子として炭坑町に育った。気づいたときには、ともに育った輝とともに大人たちに交じって坑内で働いていたし、暁幌閉山の後は農場で大地を相手に、額に汗して働き続けてきたのである。つまりは、根っからの労働者階級だったわけであるが、そんな瑛が、異国の、それも学術の世界にどっぷりと浸っている「インテリ」の少女と学芸の世界をはさんで意気投合するというのは、一見奇妙なことではある。
もっとも、彼は仲間の少年たちとは異なり、子供の頃から近隣の大人たちや古老から昔話を聞いたり、古い歌を習ったり、謎めいた遺跡や奇妙な形をした岩のことや、そのいわれを教わるのが大好きな「変わった」男の子だった。その人懐っこい様子からは想像がつかないが、元来が孤独で、想像の世界にひっそりと自分を羽ばたかせることのできるロマンチストなのである。彼が鼻歌を歌ったり、口笛を吹き鳴らしているとき、不思議な物語を仲間に語って聞かせているとき、彼は機嫌がいいというのではない。そんなとき、彼は周囲の現実世界を想像の世界に塗り替えて、その世界にひとり立っている自分の姿を見つめているのだ。多くの仲間たちが彼の声に聴き入ったり、彼の物語に酔っているときほど、彼自身は彼の孤独をじっと眺めている。そして、思考する。言葉ではなく、身体で。学がないから、難しい言葉は知らないから、言葉にならない感性で思考するのである。何を、何のために、という命題は無い。その思考は言葉ではないから。
だから、彼は哲学者ではない。強いて言えば芸術家である。もちろん、そんな言葉を彼は思うこともない。彼の現実は、坑夫あがりの農夫である。
瑛に比べれば、親友の輝のほうは、とうに枯れてしまったはずの暁幌の坑内に住んで、地下世界で父親とともに幾年も、まだ見ぬ炭層を探して歩いているロマンチストに見えるが、輝は実のところ、そのもの静かな風貌や言動からは想像がつかないが、鉄の意志を持ったリアリストなのである。考え、準備をし、目的と目標を立てて、いったん始めれば決して引き下がらない。
幼くして事故で両親を失った瑛は、現実世界では、運命をあるがままに受け入れ、なすがままに生きてきた。幼馴染の輝の一家に引き取られ、一緒に育ち、ともに炭坑で働き、閉山後は、近くの農場に働き口があったからそこで懸命に働いた。ただ、それだけのことである。そして、いつのまにか、身体を現実世界に馴染ませながら心を異界に泳がせることを自然に身に付けてしまったに過ぎない。ただ、どちらが瑛の本来であったか。少なくとも、今の瑛にとっては、想像の世界で己に向かって放つしかなかった思考を受け止め、言葉という手がかりを返してくれる新たな存在が現実世界に現れたのであるから、異界に遊んでいた自分こそが自身の本来だということになる。
このソフィと過ごした二日間は、瑛にとっての世界を、その広さも深さも幾倍にも大きなものにした。
たとえば、瑛の大好きな昔話や伝説には、アイヌの伝承にまつわるものが少なくない。アイヌの人々が北海道の先住者であることも、自分たちが維新以後、北海道に移殖してきた「和人」であることも、知識としては承知していた。しかし、それを、たとえば「民族」とか「差別」とかいった社会の問題として意識することはなかった。彼にとってアイヌという存在は、たとえば、星男爵のような華族様が居て、役人や学者先生が居て、自分たちのような坑夫や農夫が居るのと同じように、あたりまえに存在するいろいろな階層のひとつに過ぎなかった。
ところが、ソフィから欧州のことなどを聞くにつけ、自分を取り巻く現実世界が、それまで知っていた以上に生々しい厚みや深さを持っていると言うことを知ったのである。
ソフィはドイツという国に住んでいる。だから、彼女はドイツ国民であることになるわけだが、彼女はハンガリー人、あるいはマジャール人なのだそうだ。ドイツという国には、ドイツ人やマジャール人だけでなく、チェコ人とかポーランド人とかユダヤ人とかがたくさん住んでいて、ドイツ人の皇帝の元で暮らしているのだという。
彼女の父祖の国はハンガリーという国だが、今は「オーストリィ・ハンガリー帝国」という奇妙な名前の国である。その昔、ハンガリー王国という国もあったらしいが、そのハンガリー王国も、ハンガリー人は半分にも満たないのにハンガリー人の王様が治めていた。今の「オーストリィ・ハンガリー帝国」は、もともとドイツの国々を従えていたオーストリィという国があって、その皇帝がハンガリーの王様を兼ねているのだそうだ。しかも、当のドイツ人もハンガリー人も、それぞれ二割程度しか住んでいない。そもそも、ドイツ人の国がいくつもあって、その国々を従えてきたドイツの皇帝が二人居て、どちらの国もドイツ人が半分も居ない。瑛にとっては想像の外である。
とにかく、この二日間で、瑛の世界観というか、社会観はめざましく変化したのである。もっと知りたい、もっと考えたい、そして、もっと感じたい。そんな「意欲」を生まれて初めて持った、というより、自分がなにげなく吸収し、育んできた知識や感性を、身に付けたいという意識を持って初めて省みたのである。
瑛が、そんな新鮮な日々を楽しんでいた木曜日の昼下がり、瑛の病室に、背の高い異国の青年が現れた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月13日
第七章:黒水晶 その4
<第七章:黒水晶 その4>
その青年は、病室に入るなりソフィの名前を呼んで彼女を抱きしめ、彼女は彼女でうれしそうに青年の頬に接吻してみせたのである。瑛にしてみれば衝撃的な光景である。
彼らは、異国の言葉で挨拶らしい言葉を交わしている。もちろんドイツ語だが、瑛にはわからない。
そうだ。「知人と旅している」と言っていた。あの男が、その「知人」か?
あの様子、まるで夫婦じゃないか? それにしても・・・人前で。
明治の日本少年としては、仕方ない。頬にキスするくらいは、ちょっとした親しみの表明に過ぎないのだが、瑛の心中は穏やかであろうはずがない。心なしか、同じ異国の言葉でも、ソフィのそれが水玉を転がすように上品可憐に聞こえるのに、青年の言葉は冷たくとげとげしく聞こえる。
「アキラさん。紹介します。従兄弟のグスタフです。名前がグスタフで、苗字はライセンフェルト」
「ああ。君が・・・ツキオカ・アキラくん。ソフィの命の恩人だね」
青年が右手を差し出す。
ああ。従兄弟か・・・
少し安心した瑛は、窓辺に腰掛けていたが、一応立ち上がって、差し出された右手を握り返した。考えてみたら、生まれて初めて「握手」なるものをしたわけだ。
グスタフ=ライセンフェルトは、少しやせた体つきの背の高い黒髪の青年である。高い鼻に丸いめがねをかけて、肌は白いが、やや青白いといった印象がある。長めのくせのある髪を後ろに撫でつけてあるが、すこし前にも垂れていて、見るからに学究の徒といった感じもある。黒い上下をきっちりと着込んでいるが、白いシャツの襟元に少しラフな感じがあって、若さを感じさせる。この上に白衣を着せたら、若先生という感じで、さぞ似合うだろう。
グスタフもソフィほど流暢ではないが、日本語を話せる。彼はソフィの母方の従兄弟で、伯父にあたるソフィの父の下で学ぶ若い科学者とのことだった。ちなみに、ソフィの父、レオン=ナプホルト博士という人は、その研究分野は、物理学、鉱物学、地質学など多岐にわたる世界的に高名な科学者だということを、瑛は初めて聞かされた。ソフィの一家が父祖の地を離れ、ドイツに移り住んだのも、高名なナプホルト博士を、最先端の科学振興に熱心だったドイツ帝国政府が強く懇請したのを受けてのことだったらしい。
グスタフは、北海道で採取されたという黒い奇妙な石のことを調査するために、たまたま北方アジア民族の神話や伝承のフィールドワークを計画していたソフィに同行して、北海道に来たのだという。
「これなのだが・・・」
グスタフは、その奇妙な石を瑛に見せた。それは、ちょうど豆炭のような形と大きさだったが、表面は光沢があるほど密で硬質なものだった。
「北海道の、このあたりで採取されたということなのだが・・・知らないかね」
瑛は覚えがあった。それは、ごくまれに暁幌川岸で見つかることがある、このあたりで「黒水晶」と呼ばれている石かも知れない。もちろん水晶ではないが、見つかると吉兆とか言って、家宝のように隠されてしまう。めったに見つからないし、実物を見たことはない。もしかしたら、その「黒水晶」というやつかもしれない。
「ははぁん」
グスタフが目を細めた。
うすっ気味悪い表情をするヤツだな。
「それにしても、せっかく北海道に来たので、札幌に出向いてバロン星にお会いしたかったのに・・・先週から行方不明らしい」
グスタフが誰に言うともなく何気なく言った、その言葉に瑛は思わず立ち上がった。
星さんが行方不明?
「バ・・・バロンって、星男爵のこと?」
「どうしたの? そう、バロンは男爵のことよ」
「お、俺、先週、星男爵に会ってるんだ」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
その青年は、病室に入るなりソフィの名前を呼んで彼女を抱きしめ、彼女は彼女でうれしそうに青年の頬に接吻してみせたのである。瑛にしてみれば衝撃的な光景である。
彼らは、異国の言葉で挨拶らしい言葉を交わしている。もちろんドイツ語だが、瑛にはわからない。
そうだ。「知人と旅している」と言っていた。あの男が、その「知人」か?
あの様子、まるで夫婦じゃないか? それにしても・・・人前で。
明治の日本少年としては、仕方ない。頬にキスするくらいは、ちょっとした親しみの表明に過ぎないのだが、瑛の心中は穏やかであろうはずがない。心なしか、同じ異国の言葉でも、ソフィのそれが水玉を転がすように上品可憐に聞こえるのに、青年の言葉は冷たくとげとげしく聞こえる。
「アキラさん。紹介します。従兄弟のグスタフです。名前がグスタフで、苗字はライセンフェルト」
「ああ。君が・・・ツキオカ・アキラくん。ソフィの命の恩人だね」
青年が右手を差し出す。
ああ。従兄弟か・・・
少し安心した瑛は、窓辺に腰掛けていたが、一応立ち上がって、差し出された右手を握り返した。考えてみたら、生まれて初めて「握手」なるものをしたわけだ。
グスタフ=ライセンフェルトは、少しやせた体つきの背の高い黒髪の青年である。高い鼻に丸いめがねをかけて、肌は白いが、やや青白いといった印象がある。長めのくせのある髪を後ろに撫でつけてあるが、すこし前にも垂れていて、見るからに学究の徒といった感じもある。黒い上下をきっちりと着込んでいるが、白いシャツの襟元に少しラフな感じがあって、若さを感じさせる。この上に白衣を着せたら、若先生という感じで、さぞ似合うだろう。
グスタフもソフィほど流暢ではないが、日本語を話せる。彼はソフィの母方の従兄弟で、伯父にあたるソフィの父の下で学ぶ若い科学者とのことだった。ちなみに、ソフィの父、レオン=ナプホルト博士という人は、その研究分野は、物理学、鉱物学、地質学など多岐にわたる世界的に高名な科学者だということを、瑛は初めて聞かされた。ソフィの一家が父祖の地を離れ、ドイツに移り住んだのも、高名なナプホルト博士を、最先端の科学振興に熱心だったドイツ帝国政府が強く懇請したのを受けてのことだったらしい。
グスタフは、北海道で採取されたという黒い奇妙な石のことを調査するために、たまたま北方アジア民族の神話や伝承のフィールドワークを計画していたソフィに同行して、北海道に来たのだという。
「これなのだが・・・」
グスタフは、その奇妙な石を瑛に見せた。それは、ちょうど豆炭のような形と大きさだったが、表面は光沢があるほど密で硬質なものだった。
「北海道の、このあたりで採取されたということなのだが・・・知らないかね」
瑛は覚えがあった。それは、ごくまれに暁幌川岸で見つかることがある、このあたりで「黒水晶」と呼ばれている石かも知れない。もちろん水晶ではないが、見つかると吉兆とか言って、家宝のように隠されてしまう。めったに見つからないし、実物を見たことはない。もしかしたら、その「黒水晶」というやつかもしれない。
「ははぁん」
グスタフが目を細めた。
うすっ気味悪い表情をするヤツだな。
「それにしても、せっかく北海道に来たので、札幌に出向いてバロン星にお会いしたかったのに・・・先週から行方不明らしい」
グスタフが誰に言うともなく何気なく言った、その言葉に瑛は思わず立ち上がった。
星さんが行方不明?
「バ・・・バロンって、星男爵のこと?」
「どうしたの? そう、バロンは男爵のことよ」
「お、俺、先週、星男爵に会ってるんだ」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月17日
第八章:救出 その1
<救出 その1>
瑛の話を聞いたソフィとグスタフは、病院を通じてこのことを地元警察に通報した。
翌日、水曜日の午後に、札幌から来た捜査員たちが地元警察とともに瑛の病室を訪れるまで、瑛は、じりじりしながら待った。医師からは、少し早すぎるかもしれないが無理をしなければ、という条件で退院を許されている。本当のところ、すぐにも輝のところに行きたいところだったが、皆が「闇雲に動いてどうなるものでもない」と瑛をとどめた。話は、瑛の仲間や苫小牧近隣の暁幌にゆかりの人々の間にも伝わり、彼らが入れ替わり立ち代り病院を訪れて、星男爵や日下家の人たちの身を案じていたのである。
「すると・・・君が星男爵に会ったのは・・・日曜日、先々週の日曜日の午後遅く、友人の日下輝くんと一緒だった・・・と、場所は暁幌だね」
「朱鳥坑の野郎縦坑です」
「日下氏の家を訪問するところだったんだね」
「そうです。先週の日曜の祭りにもお誘いしたんですが、週末までは札幌にお戻りになるとおっしゃって・・・ですから・・・」
捜査員が瑛をさえぎって訊ねた。
「いったい、日下家を訪ねた理由・・・星男爵の用件というのは何だったのかね?」
「知りませんよ・・・・ただ・・・」
「ただ?」
「仕事がらみだっておっしゃってましたけど」
「仕事?」
「星さん・・・いえ、男爵といえば、このあたりでは暁幌の責任者だった方です。俺・・・ぼくは、仕事って言われて、何か炭坑の関係かなって思ったんですけど」
「炭坑・・・暁幌は五年前に閉山しているね」
「輝たちは、日下の家の人たちは坑内に住んで、ずっと新炭層を探してきたんですよ」
「ふうむ・・・実はね、私にも気になってることがあってね・・・星男爵ほどの名士であれば、そんな人が普通に札幌からどこかにお出でになるのであれば、人目について当然。誰かに見かけられて当たり前。挨拶を交わされる相手はいたるところに居るはずだよ。ところが・・・札幌駅で見かけた人が居るものの、どの列車で、どの方面にお出かけになったか・・・そのあたりになると、まったく目撃者が居ない。曖昧な目撃情報さえない。まるで、男爵自身が人目をはばかっているような印象を受ける・・・なるほど、新炭層か・・・かつての暁幌の繁栄を思えば、新炭層が発見されたのだとすると、秘密裡に行動された理由もわからないではない」
「そういえば」
「何だね」
「いえ・・・男爵じゃないんですが、輝のやつが・・・最近、坑内に変な気配がするって」
「ほう・・・これは・・・気になるな。君、手紙のことは何か聞いてないかね? 男爵か、その輝くんから」
「手紙?」
「いや。なんでもない。で、案内はできるかね」
「もちろんですよ。こっちは、そのためにあんたたちを待ってたんだ」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
瑛の話を聞いたソフィとグスタフは、病院を通じてこのことを地元警察に通報した。
翌日、水曜日の午後に、札幌から来た捜査員たちが地元警察とともに瑛の病室を訪れるまで、瑛は、じりじりしながら待った。医師からは、少し早すぎるかもしれないが無理をしなければ、という条件で退院を許されている。本当のところ、すぐにも輝のところに行きたいところだったが、皆が「闇雲に動いてどうなるものでもない」と瑛をとどめた。話は、瑛の仲間や苫小牧近隣の暁幌にゆかりの人々の間にも伝わり、彼らが入れ替わり立ち代り病院を訪れて、星男爵や日下家の人たちの身を案じていたのである。
「すると・・・君が星男爵に会ったのは・・・日曜日、先々週の日曜日の午後遅く、友人の日下輝くんと一緒だった・・・と、場所は暁幌だね」
「朱鳥坑の野郎縦坑です」
「日下氏の家を訪問するところだったんだね」
「そうです。先週の日曜の祭りにもお誘いしたんですが、週末までは札幌にお戻りになるとおっしゃって・・・ですから・・・」
捜査員が瑛をさえぎって訊ねた。
「いったい、日下家を訪ねた理由・・・星男爵の用件というのは何だったのかね?」
「知りませんよ・・・・ただ・・・」
「ただ?」
「仕事がらみだっておっしゃってましたけど」
「仕事?」
「星さん・・・いえ、男爵といえば、このあたりでは暁幌の責任者だった方です。俺・・・ぼくは、仕事って言われて、何か炭坑の関係かなって思ったんですけど」
「炭坑・・・暁幌は五年前に閉山しているね」
「輝たちは、日下の家の人たちは坑内に住んで、ずっと新炭層を探してきたんですよ」
「ふうむ・・・実はね、私にも気になってることがあってね・・・星男爵ほどの名士であれば、そんな人が普通に札幌からどこかにお出でになるのであれば、人目について当然。誰かに見かけられて当たり前。挨拶を交わされる相手はいたるところに居るはずだよ。ところが・・・札幌駅で見かけた人が居るものの、どの列車で、どの方面にお出かけになったか・・・そのあたりになると、まったく目撃者が居ない。曖昧な目撃情報さえない。まるで、男爵自身が人目をはばかっているような印象を受ける・・・なるほど、新炭層か・・・かつての暁幌の繁栄を思えば、新炭層が発見されたのだとすると、秘密裡に行動された理由もわからないではない」
「そういえば」
「何だね」
「いえ・・・男爵じゃないんですが、輝のやつが・・・最近、坑内に変な気配がするって」
「ほう・・・これは・・・気になるな。君、手紙のことは何か聞いてないかね? 男爵か、その輝くんから」
「手紙?」
「いや。なんでもない。で、案内はできるかね」
「もちろんですよ。こっちは、そのためにあんたたちを待ってたんだ」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月18日
第八章:救出 その2
<救出 その2>
札幌から来た捜査員と瑛たちは暁幌に移動し、警察は、そこで地元警官と有志数名からなる捜索隊を組織した。リーダーは捜査員、道案内は瑛である。
「わたしは、バロン(男爵)にお会いしたいと思って北海道に参りました。ですから、わたしたちも捜索に加わりたいのですが」
暁幌までソフィとともに彼らに同行したグスタフが捜査員に申し出たが、捜査員は丁重に断った。
「お申し出には感謝いたしますよ。ですが、我々としても外国からのお客様に万一のことがあっては問題になりますので。第一、うかがったところによれば、あなた方はドイツの高名な科学者の血縁であられるとのこと。なおさら、危険な場所にお連れするわけには参りません。どうか宿にてお待ちください。何かわかりましたら必ずお知らせしますから」
さて、捜索隊は地上、すなわち暁幌の丘陵地帯や暁幌川周辺を捜索するチームと、瑛とともに坑内に降りるチームとに別れることになった。地上隊は主に地元有志たち、地下隊は、捜査員以下、数名の警察官と暁幌炭坑で坑夫として働いていた幾人かの屈強な男たちに、道案内の瑛を加えた十名ほどである。
二週間前の夏の終わり、輝と星男爵が歩いた道筋を、彼らは朱鳥坑に向かって急いだ。北海道の秋は早く、短い。一雨ごとに秋は深まり、冬の足音が近づく。小雨の降る中を星男爵がたどったときには夏の終わりの涼しさを感じさせた朱鳥周辺は、たった二週間で冬の気配を感じさせる秋の冷たい風を遊ばせている。そんな風たちの一団が、瑛たちの首筋を撫でては走り去った。
「ここを降りるのかね・・・」
捜査員は、野郎縦坑の入り口に立ち、下を覗き込んだ。
「はい。昔は昇降機があったんですが、今は梯子です」
「この地下に住んでいるのか? その日下氏の家族は」
「ええ、この五年の間、ずっとです」
「ふぅ。想像がつかんよ。・・・ふむ、梯子一段にひとりずつ・・・だな」
「はい」
ひとつの梯子に複数がかかると危険なので、ひとつの梯子にひとりずつ順番に降りてゆくことになる。まず、案内役の瑛から降り始めた。
梯子を降り継いで数段目、瑛が踏み出した足に梯子が崩れ、音を立てて落ちていった。瑛は空足を踏んだようなかっこうで、あわてて梯子の上部にしがみついた。
「どうしたんだ!」
後に続いていた者が異変に気づいて声をかける。
「は・・・梯子が」
「梯子が? どうしたって?」
「崩れたんです。変です。こんなことは初めてです」
「下の様子がわかるか? 下を覗いてみてくれ」
捜査員が上から指示した。
瑛は、腰に下げていたランプをかざして下のほうに目を凝らした。
すぐ下の踊り場に梯子の残骸らしきものが見える。更に億を覗き込んでみると、どうやらそこから下には、梯子そのものが無いようだ。それに、かすかだが焦げ臭い臭いがする。
「梯子が・・・ここから下の梯子がありません。それに、焦げ臭い・・・燃やされたようです」
「何だって?」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
札幌から来た捜査員と瑛たちは暁幌に移動し、警察は、そこで地元警官と有志数名からなる捜索隊を組織した。リーダーは捜査員、道案内は瑛である。
「わたしは、バロン(男爵)にお会いしたいと思って北海道に参りました。ですから、わたしたちも捜索に加わりたいのですが」
暁幌までソフィとともに彼らに同行したグスタフが捜査員に申し出たが、捜査員は丁重に断った。
「お申し出には感謝いたしますよ。ですが、我々としても外国からのお客様に万一のことがあっては問題になりますので。第一、うかがったところによれば、あなた方はドイツの高名な科学者の血縁であられるとのこと。なおさら、危険な場所にお連れするわけには参りません。どうか宿にてお待ちください。何かわかりましたら必ずお知らせしますから」
さて、捜索隊は地上、すなわち暁幌の丘陵地帯や暁幌川周辺を捜索するチームと、瑛とともに坑内に降りるチームとに別れることになった。地上隊は主に地元有志たち、地下隊は、捜査員以下、数名の警察官と暁幌炭坑で坑夫として働いていた幾人かの屈強な男たちに、道案内の瑛を加えた十名ほどである。
二週間前の夏の終わり、輝と星男爵が歩いた道筋を、彼らは朱鳥坑に向かって急いだ。北海道の秋は早く、短い。一雨ごとに秋は深まり、冬の足音が近づく。小雨の降る中を星男爵がたどったときには夏の終わりの涼しさを感じさせた朱鳥周辺は、たった二週間で冬の気配を感じさせる秋の冷たい風を遊ばせている。そんな風たちの一団が、瑛たちの首筋を撫でては走り去った。
「ここを降りるのかね・・・」
捜査員は、野郎縦坑の入り口に立ち、下を覗き込んだ。
「はい。昔は昇降機があったんですが、今は梯子です」
「この地下に住んでいるのか? その日下氏の家族は」
「ええ、この五年の間、ずっとです」
「ふぅ。想像がつかんよ。・・・ふむ、梯子一段にひとりずつ・・・だな」
「はい」
ひとつの梯子に複数がかかると危険なので、ひとつの梯子にひとりずつ順番に降りてゆくことになる。まず、案内役の瑛から降り始めた。
梯子を降り継いで数段目、瑛が踏み出した足に梯子が崩れ、音を立てて落ちていった。瑛は空足を踏んだようなかっこうで、あわてて梯子の上部にしがみついた。
「どうしたんだ!」
後に続いていた者が異変に気づいて声をかける。
「は・・・梯子が」
「梯子が? どうしたって?」
「崩れたんです。変です。こんなことは初めてです」
「下の様子がわかるか? 下を覗いてみてくれ」
捜査員が上から指示した。
瑛は、腰に下げていたランプをかざして下のほうに目を凝らした。
すぐ下の踊り場に梯子の残骸らしきものが見える。更に億を覗き込んでみると、どうやらそこから下には、梯子そのものが無いようだ。それに、かすかだが焦げ臭い臭いがする。
「梯子が・・・ここから下の梯子がありません。それに、焦げ臭い・・・燃やされたようです」
「何だって?」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月18日
第八章:救出 その3
<救出 その3>
いったん坑外に戻った彼らは、万一に備えて用意してきたロープを使って降りることにした。時間はかかるが出直すわけにはいかない。状況から見て、その余裕は無かった。何者かの明確な悪意が確認されたのである。
全員の不安もさることながら、瑛は輝たちの安否がいよいよ心配になってきた。こんなことは予想だにしていなかったのだ。
それにしても、いったい、どこのどいつがこんなことを。
やっとの思いで、捜索隊全員が朱鳥坑に降り立った。燃やされた梯子の残骸があたりに散らばっている。
捜索隊は、瑛の案内で、まず日下家の小屋を目指した。彼らが星男爵とともに小屋に居れば、というような楽観的な観測は、もはや誰も持っていない。縦坑の梯子を燃やすような連中が居る以上、男爵も日下家の人々も、どこかに連れ去られたか、あるいは・・・
外はもう夕暮れだろう。だが、ここではそういう時間の感覚は消失しているし、誰もが一刻も早く男爵たちを見つけ出したかったから、今何時(なんどき)かなどということは考えもしなかった。
日下家の小屋。
扉に鍵はかかっていない。当然だろう。そんなものは必要なかった・・・はずだ。
中の様子は、よく片付けられていて、人が争ったような形跡は無い。食器の類も片付いている。男爵の衣類などが奥の部屋にきちんと下げてある。鞄や身の周りの小物もテーブルの上にきちんと揃えて置かれている。小屋の周辺にも乱れた足跡や不審な痕跡は見当たらない。どうやら、小屋に何者かが乱入したとか、ここで皆が連れ去られたというわけではなさそうだ。
捜査員が、壁に日めくりを見つけた。先週の月曜日のままだ。
「先週の月曜までは、何事も無くここに居た・・・ということかな」
ツルハシが無いことに瑛が気づいた。
「いつもそこに置いてあったツルハシがありません。それから・・・ロープ、他にも装備やなんかが無くなってるようです。あ・・・安全灯も・・・ああ? ダイナマイトが・・・ってことは・・・」
捜査員がひとりごつようにつぶやいた。
「盗まれたんじゃないとしたら・・・そうか、どこかで作業するために・・・たとえば発破とか、皆で出かけたんじゃないかな。先週の月曜に」
「発破・・・事故に遭った可能性もありますか?」
誰かが、捜査員に聞くともなく応える。
「新炭層の発掘作業・・・か」
瑛がたまらず怒鳴った。
「でも、あの燃やされた梯子。誰かが作業中のみんなを・・・」
「我々の捜索を妨害するためだとしたら・・・動機はわかるが、この手の妨害者にしてはやりかたが稚拙に過ぎるよ」
「どういう意味ですか?」
「玄人のやり方ではないということだよ」
「玄人? ・・・って」
「盗賊とか、新炭層がからんでいるなら、たとえば競合者に雇われた悪漢だとか・・・そういった手合いなら、もっと周到に証拠を隠したり、そう・・・たとえば、縦坑の梯子を途中から焼くようなことをしてもロープがあれば降りられるだろう? それに悪意の証拠が残る。計画的な犯行ならそんなことはしない。梯子を焼くなんて手ぬるい方法じゃなく、たとえば縦坑の入り口自体を塞いでしまうとか、途中の坑道を事故に見せかけて本当に発破をかけてしまうとか、そのくらいはするものだよ。『玄人』ならね」
「じゃ、あなたは、どんなやつが・・・」
「わからん。とにかく、ちぐはぐなんだ。そう、たとえば異常者だとかが、目的ははっきりしないまま『とにかくこいつらをやっつけてしまえ』と・・・相手ははっきりしているし、捜索は妨害したいが、やり方はいきあたりばったり・・・」
瑛はぞっとした。捜査の専門家である警官がわからないというのだ。「異常者」という言葉が頭にこびりつく。
輝たちは、そんなわけのわからない人間に見込まれたっていうのか?
人間? 本当に人間の仕業か?
人間の常識でははかれない理由で、時には残酷な仕打ちでも悪戯気分でやってのける。そのくせ「悪戯」「悪ふざけ」だから、やり口はいい加減で拙い。目的もいい加減だから、いつでも止めるし、いつでも始める。何の脈絡もなしに。
たとえば、暁幌の精みたいなものが、静かになった坑内をうろつく人間たち・・・輝たちのことだ・・・をうっとうしいと感じたとしたら。その上、新たに変な人間が加わって・・・星男爵・・・ついにはそっと隠していた宝物・・・炭層のことを精はそう思っていたかも知れない・・・を見つけて、あろうことか爆薬で暴こうとした・・・だから、この際・・・やっつけてしまえ・・・
「人間・・・でしょうか?」
「ああ?」
瑛の口をついて出た言葉があまりに唐突だったので、捜査員が顔をあげた。そのとき、
「あそこ・・・火? 火じゃないか?」
誰かが、坑道の奥のほうにかすかな明るみを見つけて叫んだ。
明るみが揺れて、奥のほうへ消えてゆく。
「火だ。火だぞ」
「動いてる」
「奥だ。おい、誰か居るぞ」
「奥へ・・・逃げていくぞ」
小屋の周りで思案していた全員がいっせいに坑道の奥に目を凝らした。
「追うぞ!」
捜査員の動きは速かった。彼は、それまで沈思していたのとは別人のような迅速さで地面を蹴った。捜索隊の全員がそれに続く。
火。
鬼火。
火の乙女。
瑛も一緒に走った。あの断崖の上に舞う「火の乙女」の記憶が彼の頭をよぎった。
「あれは、あの火は、人の火じゃない」
瑛は直感的にそう思った。いや、確信した。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
いったん坑外に戻った彼らは、万一に備えて用意してきたロープを使って降りることにした。時間はかかるが出直すわけにはいかない。状況から見て、その余裕は無かった。何者かの明確な悪意が確認されたのである。
全員の不安もさることながら、瑛は輝たちの安否がいよいよ心配になってきた。こんなことは予想だにしていなかったのだ。
それにしても、いったい、どこのどいつがこんなことを。
やっとの思いで、捜索隊全員が朱鳥坑に降り立った。燃やされた梯子の残骸があたりに散らばっている。
捜索隊は、瑛の案内で、まず日下家の小屋を目指した。彼らが星男爵とともに小屋に居れば、というような楽観的な観測は、もはや誰も持っていない。縦坑の梯子を燃やすような連中が居る以上、男爵も日下家の人々も、どこかに連れ去られたか、あるいは・・・
外はもう夕暮れだろう。だが、ここではそういう時間の感覚は消失しているし、誰もが一刻も早く男爵たちを見つけ出したかったから、今何時(なんどき)かなどということは考えもしなかった。
日下家の小屋。
扉に鍵はかかっていない。当然だろう。そんなものは必要なかった・・・はずだ。
中の様子は、よく片付けられていて、人が争ったような形跡は無い。食器の類も片付いている。男爵の衣類などが奥の部屋にきちんと下げてある。鞄や身の周りの小物もテーブルの上にきちんと揃えて置かれている。小屋の周辺にも乱れた足跡や不審な痕跡は見当たらない。どうやら、小屋に何者かが乱入したとか、ここで皆が連れ去られたというわけではなさそうだ。
捜査員が、壁に日めくりを見つけた。先週の月曜日のままだ。
「先週の月曜までは、何事も無くここに居た・・・ということかな」
ツルハシが無いことに瑛が気づいた。
「いつもそこに置いてあったツルハシがありません。それから・・・ロープ、他にも装備やなんかが無くなってるようです。あ・・・安全灯も・・・ああ? ダイナマイトが・・・ってことは・・・」
捜査員がひとりごつようにつぶやいた。
「盗まれたんじゃないとしたら・・・そうか、どこかで作業するために・・・たとえば発破とか、皆で出かけたんじゃないかな。先週の月曜に」
「発破・・・事故に遭った可能性もありますか?」
誰かが、捜査員に聞くともなく応える。
「新炭層の発掘作業・・・か」
瑛がたまらず怒鳴った。
「でも、あの燃やされた梯子。誰かが作業中のみんなを・・・」
「我々の捜索を妨害するためだとしたら・・・動機はわかるが、この手の妨害者にしてはやりかたが稚拙に過ぎるよ」
「どういう意味ですか?」
「玄人のやり方ではないということだよ」
「玄人? ・・・って」
「盗賊とか、新炭層がからんでいるなら、たとえば競合者に雇われた悪漢だとか・・・そういった手合いなら、もっと周到に証拠を隠したり、そう・・・たとえば、縦坑の梯子を途中から焼くようなことをしてもロープがあれば降りられるだろう? それに悪意の証拠が残る。計画的な犯行ならそんなことはしない。梯子を焼くなんて手ぬるい方法じゃなく、たとえば縦坑の入り口自体を塞いでしまうとか、途中の坑道を事故に見せかけて本当に発破をかけてしまうとか、そのくらいはするものだよ。『玄人』ならね」
「じゃ、あなたは、どんなやつが・・・」
「わからん。とにかく、ちぐはぐなんだ。そう、たとえば異常者だとかが、目的ははっきりしないまま『とにかくこいつらをやっつけてしまえ』と・・・相手ははっきりしているし、捜索は妨害したいが、やり方はいきあたりばったり・・・」
瑛はぞっとした。捜査の専門家である警官がわからないというのだ。「異常者」という言葉が頭にこびりつく。
輝たちは、そんなわけのわからない人間に見込まれたっていうのか?
人間? 本当に人間の仕業か?
人間の常識でははかれない理由で、時には残酷な仕打ちでも悪戯気分でやってのける。そのくせ「悪戯」「悪ふざけ」だから、やり口はいい加減で拙い。目的もいい加減だから、いつでも止めるし、いつでも始める。何の脈絡もなしに。
たとえば、暁幌の精みたいなものが、静かになった坑内をうろつく人間たち・・・輝たちのことだ・・・をうっとうしいと感じたとしたら。その上、新たに変な人間が加わって・・・星男爵・・・ついにはそっと隠していた宝物・・・炭層のことを精はそう思っていたかも知れない・・・を見つけて、あろうことか爆薬で暴こうとした・・・だから、この際・・・やっつけてしまえ・・・
「人間・・・でしょうか?」
「ああ?」
瑛の口をついて出た言葉があまりに唐突だったので、捜査員が顔をあげた。そのとき、
「あそこ・・・火? 火じゃないか?」
誰かが、坑道の奥のほうにかすかな明るみを見つけて叫んだ。
明るみが揺れて、奥のほうへ消えてゆく。
「火だ。火だぞ」
「動いてる」
「奥だ。おい、誰か居るぞ」
「奥へ・・・逃げていくぞ」
小屋の周りで思案していた全員がいっせいに坑道の奥に目を凝らした。
「追うぞ!」
捜査員の動きは速かった。彼は、それまで沈思していたのとは別人のような迅速さで地面を蹴った。捜索隊の全員がそれに続く。
火。
鬼火。
火の乙女。
瑛も一緒に走った。あの断崖の上に舞う「火の乙女」の記憶が彼の頭をよぎった。
「あれは、あの火は、人の火じゃない」
瑛は直感的にそう思った。いや、確信した。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月18日
第八章:救出 その4
<救出 その4>
瑛は先頭を走っている捜査員の横に並んで叫んだ。
「あれは人じゃない。人外の・・・ものです! 追っても無駄だ」
捜査員は無視した。
しばらくすると火が見えなくなった。
「どこへ行った」
「坑内は入り組んでるんです。闇雲に追っかけたら危ない。それに、あれは人じゃな・・・」
「あそこだっ!」
分かれ道の奥に一瞬火が見えた。
全員が、それに誘われるように走り出す。
「からかわれてるんですよ。なんで・・・わからないんだ・・・」
瑛の絶叫を無視して全員が駆ける。
また見失う。そして、また遠くから火が誘う。皆がいっせいに駆け出す。
瑛も叫びながら皆についてゆくしかなかった。
そして、一行はどこかの坑道の奥まで誘(いざな)われた。
火が消えた。全員が息を切らして、しばらく呆然とたたずむ。もう火は現れない。
「おい・・・ここは?」
捜査員が我に返って瑛に尋ねた。
「ここは・・・八号・・・かな。でも・・・こんな・・・」
「八号?」
「試掘坑のひとつです。俺のカンが合ってれば、ここは八号試掘坑のはずです。でも・・・」
「でも・・・どうか・・したか?」
捜査員も、他の者たちも、まだ息がととのわない。さすがに瑛は若い。
瑛は、たびたび日下家を訪れて、たまには輝たちの坑内探査に同行することもあったから、だいたいの中(あた)りをつけることはできる。
「こんなに荒れてはいなかったはずです」
皆が落ち着いてきた。静かだ。
「荒れてる、というと?」
「最近、発破をかけてますよ、ここは」
あたりを眺めていた年かさの元坑夫が答えた。
「なるほど。ここが現場だった可能性があるのか・・・」
「ここから、どう行ったら・・・」
「静かに!」
捜査員が皆の発言を制した。
静かだ。静かだが・・・どこかで、かすかに人の気配がする。
捜査員が瑛を手招き、瓦礫の山のほうを指した。
瑛はランプをかざしながら、捜査員とともに、少し奥の瓦礫がうず高くなっているところを慎重にゆっくりと上っていった。身を伏せ、ランプをその奥に向ける。白っぽいものが目に入った。
「あれ・・・人では」
「人だ。人だぞ」
「うーん」
今度は、はっきりしたうめき声が聞こえた。
「人だ! 男爵? 日下さん?」
呼びかけた捜査員に白い人影が応えた。
「誰? だれですか?」
「捜索隊だ。助けに来たぞ。君は?」
「くさか・・・てらす」
「輝! おい、輝。俺だよ、瑛だよ」
「あ・・あきら。助かった。ぼくより、星さんと・・・母さんを・・・」
捜査員が輝に訊ねた。
「君! 他の人たちは?」
「なんとか、無事です。男爵と母が・・・相当弱ってるので、お願いします」
ランプを奥に向けると、他の三人が横たわっているのが見えた。
捜査員が後ろを振り返って叫んだ。
「居たぞ。全員生きてる」
八号試掘坑に歓声があがった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
瑛は先頭を走っている捜査員の横に並んで叫んだ。
「あれは人じゃない。人外の・・・ものです! 追っても無駄だ」
捜査員は無視した。
しばらくすると火が見えなくなった。
「どこへ行った」
「坑内は入り組んでるんです。闇雲に追っかけたら危ない。それに、あれは人じゃな・・・」
「あそこだっ!」
分かれ道の奥に一瞬火が見えた。
全員が、それに誘われるように走り出す。
「からかわれてるんですよ。なんで・・・わからないんだ・・・」
瑛の絶叫を無視して全員が駆ける。
また見失う。そして、また遠くから火が誘う。皆がいっせいに駆け出す。
瑛も叫びながら皆についてゆくしかなかった。
そして、一行はどこかの坑道の奥まで誘(いざな)われた。
火が消えた。全員が息を切らして、しばらく呆然とたたずむ。もう火は現れない。
「おい・・・ここは?」
捜査員が我に返って瑛に尋ねた。
「ここは・・・八号・・・かな。でも・・・こんな・・・」
「八号?」
「試掘坑のひとつです。俺のカンが合ってれば、ここは八号試掘坑のはずです。でも・・・」
「でも・・・どうか・・したか?」
捜査員も、他の者たちも、まだ息がととのわない。さすがに瑛は若い。
瑛は、たびたび日下家を訪れて、たまには輝たちの坑内探査に同行することもあったから、だいたいの中(あた)りをつけることはできる。
「こんなに荒れてはいなかったはずです」
皆が落ち着いてきた。静かだ。
「荒れてる、というと?」
「最近、発破をかけてますよ、ここは」
あたりを眺めていた年かさの元坑夫が答えた。
「なるほど。ここが現場だった可能性があるのか・・・」
「ここから、どう行ったら・・・」
「静かに!」
捜査員が皆の発言を制した。
静かだ。静かだが・・・どこかで、かすかに人の気配がする。
捜査員が瑛を手招き、瓦礫の山のほうを指した。
瑛はランプをかざしながら、捜査員とともに、少し奥の瓦礫がうず高くなっているところを慎重にゆっくりと上っていった。身を伏せ、ランプをその奥に向ける。白っぽいものが目に入った。
「あれ・・・人では」
「人だ。人だぞ」
「うーん」
今度は、はっきりしたうめき声が聞こえた。
「人だ! 男爵? 日下さん?」
呼びかけた捜査員に白い人影が応えた。
「誰? だれですか?」
「捜索隊だ。助けに来たぞ。君は?」
「くさか・・・てらす」
「輝! おい、輝。俺だよ、瑛だよ」
「あ・・あきら。助かった。ぼくより、星さんと・・・母さんを・・・」
捜査員が輝に訊ねた。
「君! 他の人たちは?」
「なんとか、無事です。男爵と母が・・・相当弱ってるので、お願いします」
ランプを奥に向けると、他の三人が横たわっているのが見えた。
捜査員が後ろを振り返って叫んだ。
「居たぞ。全員生きてる」
八号試掘坑に歓声があがった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月26日
第九章:地下都市 その1
<地下都市 その1>
岩崎刑事は、園田北海道庁長官から直々にお褒めの言葉をいただいたそうである。さらに破格の昇進で警部殿になった。そのニュースを聞いて、瑛は、あの捜査員が「岩崎」というのだと初めて知った。名前も何も聞かないまま一緒に走り回っていたのである。
いくら星男爵が北海道有数の名士であるからといって、それだけで、そんな破格の処遇を受けることはない。失踪した男爵の救出というニュースは、同時に、前代未聞の地底の大洞穴、それも無尽蔵と思えるほどの豊かな石炭層の発見というニュースでもあったからである。
新世紀を迎えて間もない日本の産業界、政界にとっても、そして「一等国」なるものを目指す気運に同調していた多くの日本人にとっても、それは血沸き肉踊る大事件だったのである。
というのも、つい十年ほど前に、この国は清国を相手に御維新以来最初の大きな対外戦争をやってのけた。「眠れる獅子」と列強がひそかに恐れていた大国中の大国を相手に戦争を仕掛け、あろうことか勝ってしまったのである。いわゆる明治二十七八年戦役というやつである。富国強兵に邁進してきた努力が実を結び、いよいよ「一等国」が夢ではなく、目標として見えてきた。ところが、そんな沸き返る日本人の頭に冷や水を浴びせかけるような事態が生じた。満州地域を狙っていたロシアが降って湧いたような日本の侵出を警戒し、ドイツやフランスを誘って日清の戦後処理に干渉してきたのだ。二億円ものお金と十五万もの兵力を動員した戦争の後である。その上、欧州列強三国と単独で争うだけの力量があるはずもない。日本は三国の干渉を受け入れざるを得なかったのである。爾来、ロシアはこの国の仮想敵国となった。北海道は、その最前線となる。そして、この十年ほどの間に、日本は英国を味方につけ、新世紀となって早々、ついに日英同盟を締結。ロシアよ、今に見ていろ。一矢報いてやらずにはおくものか。いつ、ロシアと戦争をおっぱじめるのか。日本の新世紀は、そんな気分が時代を覆っていたのだ。
そこに、暁幌の復活、それも未曾有の大洞穴と無尽蔵の石炭という夢物語のようなニュースが飛び込んできたのである。
「二十世紀はわが日本の時代になる」
誰もが、そう思った。
そんなわけで「名探偵岩崎刑事」と「星男爵の冒険」の物語は、多くの日本人や北海道民にとって、そこいらの小説や講談に勝るとも劣らない胸のすくニュースとなって、国中を駆け巡ったのである。
「それにしても、未だにこの事件は謎だらけですよ。解決したとはとても言えない。私は男爵を発見できたという、ただそれだけです。それも月岡君、君の案内のお陰でだよ。まったく、過大評価も甚だしい」
久しぶりに、星男爵邸に関係者、星男爵、亨、輝、瑛、そしてソフィとグスタフが集まっている。そんなときに、その岩崎警部殿が来訪して、話の輪に加わった。
星男爵は、数日の療養の後、新暁幌炭鉱再開のためにすぐに動いた。もっとも、ニュースのお陰で、星が動かなくても、暁幌の旧株主たちはもとより、国中から投資を申し出る者が星のもとを訪れたから、資金調達については問題なく進みそうだった。
それよりも、日下亨が言った「ここに街を作ったら」という言葉。星は、それを本当に実現できるのではないかと考えたのである。今までに無い大規模な炭鉱開発になる。その計画を立案し、一刻も早く実現にこぎつけるために、彼は、当座、集められるだけの資金と人材を駆使して、あの大洞穴の調査を急ピッチで行った。この調査には、当然、岩崎警部率いる捜査隊も同行した。洞穴内部にまだ悪漢どもが潜んでいるかもしれなかったからである。
「謎と言えば、私のほうもわからないことが沢山出てきたよ」
洞穴内の調査と捜査の結果、いくつか新しい発見があった。
まず、洞穴は、一箇月近くにわたる調査をもってしてもその全貌が確認できないほど広いということ。ただ、南側の端は、どうやら苫小牧の手前近くまでで行き止まりのようだ。もっとも、人が入れないような細い穴はまだまだ南に向かって延びている。それらの調査を通じて、あちらこちらに人の手が加えられた痕跡が見られた。洞穴全体はおおむね自然の造作によるものと思われたが、ところどころ人がととのえたとしか思えない箇所がある。比較的最近の痕跡もあったが、多くはおそろしく古いもののように思われる。星の目をもってしても、それらがととのえられた時代や、状況については判断が難しかった。
そんな中、あの古墳(と言っても、古い遺跡を正体がわからないまま「古墳」と称しているだけなのだが)がある入り江の断崖の頂上付近に、この大洞穴につながっているのではないかと思われる小さな穴がたくさんあることがわかった。調べてみると、ちょうど間欠泉のように、石炭ガスが勢いよく噴き出すことがある。あの「鬼火」現象は、そのガスに引火したものである可能性が高い。
「私は、あの鬼火は、自然に引火したものではなく、誰かが意図的に点火したのではないかと考えています。牛の角なんかに松明を着けて、偽の灯台を見せる。船の積荷を狙う賊が使う手です。あれと同じですよ、多分」
「人でしょうか?」
瑛は、いまだに、洞穴の中で捜索隊を誘(いざな)ったのは「人外のものだ」と信じているのだ。
岩崎警部は、小首を傾げてゆっくりと答えた。
「私は、人間だと思うよ。まぁ、警察は人間が相手でないと困るんだがね」
捜索中は猟犬のような厳しさと俊敏さを見せる岩崎だったが、こうして考えているときや話しているときは、おっとりとした優しさで応える。
なかなかの好人物らしいな、と星は思った。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
岩崎刑事は、園田北海道庁長官から直々にお褒めの言葉をいただいたそうである。さらに破格の昇進で警部殿になった。そのニュースを聞いて、瑛は、あの捜査員が「岩崎」というのだと初めて知った。名前も何も聞かないまま一緒に走り回っていたのである。
いくら星男爵が北海道有数の名士であるからといって、それだけで、そんな破格の処遇を受けることはない。失踪した男爵の救出というニュースは、同時に、前代未聞の地底の大洞穴、それも無尽蔵と思えるほどの豊かな石炭層の発見というニュースでもあったからである。
新世紀を迎えて間もない日本の産業界、政界にとっても、そして「一等国」なるものを目指す気運に同調していた多くの日本人にとっても、それは血沸き肉踊る大事件だったのである。
というのも、つい十年ほど前に、この国は清国を相手に御維新以来最初の大きな対外戦争をやってのけた。「眠れる獅子」と列強がひそかに恐れていた大国中の大国を相手に戦争を仕掛け、あろうことか勝ってしまったのである。いわゆる明治二十七八年戦役というやつである。富国強兵に邁進してきた努力が実を結び、いよいよ「一等国」が夢ではなく、目標として見えてきた。ところが、そんな沸き返る日本人の頭に冷や水を浴びせかけるような事態が生じた。満州地域を狙っていたロシアが降って湧いたような日本の侵出を警戒し、ドイツやフランスを誘って日清の戦後処理に干渉してきたのだ。二億円ものお金と十五万もの兵力を動員した戦争の後である。その上、欧州列強三国と単独で争うだけの力量があるはずもない。日本は三国の干渉を受け入れざるを得なかったのである。爾来、ロシアはこの国の仮想敵国となった。北海道は、その最前線となる。そして、この十年ほどの間に、日本は英国を味方につけ、新世紀となって早々、ついに日英同盟を締結。ロシアよ、今に見ていろ。一矢報いてやらずにはおくものか。いつ、ロシアと戦争をおっぱじめるのか。日本の新世紀は、そんな気分が時代を覆っていたのだ。
そこに、暁幌の復活、それも未曾有の大洞穴と無尽蔵の石炭という夢物語のようなニュースが飛び込んできたのである。
「二十世紀はわが日本の時代になる」
誰もが、そう思った。
そんなわけで「名探偵岩崎刑事」と「星男爵の冒険」の物語は、多くの日本人や北海道民にとって、そこいらの小説や講談に勝るとも劣らない胸のすくニュースとなって、国中を駆け巡ったのである。
「それにしても、未だにこの事件は謎だらけですよ。解決したとはとても言えない。私は男爵を発見できたという、ただそれだけです。それも月岡君、君の案内のお陰でだよ。まったく、過大評価も甚だしい」
久しぶりに、星男爵邸に関係者、星男爵、亨、輝、瑛、そしてソフィとグスタフが集まっている。そんなときに、その岩崎警部殿が来訪して、話の輪に加わった。
星男爵は、数日の療養の後、新暁幌炭鉱再開のためにすぐに動いた。もっとも、ニュースのお陰で、星が動かなくても、暁幌の旧株主たちはもとより、国中から投資を申し出る者が星のもとを訪れたから、資金調達については問題なく進みそうだった。
それよりも、日下亨が言った「ここに街を作ったら」という言葉。星は、それを本当に実現できるのではないかと考えたのである。今までに無い大規模な炭鉱開発になる。その計画を立案し、一刻も早く実現にこぎつけるために、彼は、当座、集められるだけの資金と人材を駆使して、あの大洞穴の調査を急ピッチで行った。この調査には、当然、岩崎警部率いる捜査隊も同行した。洞穴内部にまだ悪漢どもが潜んでいるかもしれなかったからである。
「謎と言えば、私のほうもわからないことが沢山出てきたよ」
洞穴内の調査と捜査の結果、いくつか新しい発見があった。
まず、洞穴は、一箇月近くにわたる調査をもってしてもその全貌が確認できないほど広いということ。ただ、南側の端は、どうやら苫小牧の手前近くまでで行き止まりのようだ。もっとも、人が入れないような細い穴はまだまだ南に向かって延びている。それらの調査を通じて、あちらこちらに人の手が加えられた痕跡が見られた。洞穴全体はおおむね自然の造作によるものと思われたが、ところどころ人がととのえたとしか思えない箇所がある。比較的最近の痕跡もあったが、多くはおそろしく古いもののように思われる。星の目をもってしても、それらがととのえられた時代や、状況については判断が難しかった。
そんな中、あの古墳(と言っても、古い遺跡を正体がわからないまま「古墳」と称しているだけなのだが)がある入り江の断崖の頂上付近に、この大洞穴につながっているのではないかと思われる小さな穴がたくさんあることがわかった。調べてみると、ちょうど間欠泉のように、石炭ガスが勢いよく噴き出すことがある。あの「鬼火」現象は、そのガスに引火したものである可能性が高い。
「私は、あの鬼火は、自然に引火したものではなく、誰かが意図的に点火したのではないかと考えています。牛の角なんかに松明を着けて、偽の灯台を見せる。船の積荷を狙う賊が使う手です。あれと同じですよ、多分」
「人でしょうか?」
瑛は、いまだに、洞穴の中で捜索隊を誘(いざな)ったのは「人外のものだ」と信じているのだ。
岩崎警部は、小首を傾げてゆっくりと答えた。
「私は、人間だと思うよ。まぁ、警察は人間が相手でないと困るんだがね」
捜索中は猟犬のような厳しさと俊敏さを見せる岩崎だったが、こうして考えているときや話しているときは、おっとりとした優しさで応える。
なかなかの好人物らしいな、と星は思った。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月26日
第九章:地下都市 その2
<地下都市 その2>
「謎を整理してみるかね?」
「そうですね。まず、手紙です。二通目は、あきらかに男爵を暁幌に行かせまいとする意図から投函されたものです」
「だが、私でも気付くくらい、拙い仕掛けだった」
「そうです。次は、確か・・・頭上から石が投げ落とされた。殺意はともかく、怪我くらいはさせるつもりがあったと考えていいでしょう。ただの脅しじゃない。それから・・・」
「八号試掘坑でガスの穴を塞いだやつが居ます」
輝が言った。
「そして、発破のあとに瓦礫を積みなおして、洞穴を発見した君たちを迷わせた」
「その前に・・・洞穴の中で、僕が持っていたランプを叩き落とした・・・あれは・・・人ではありませんでした。頭上から来たんです」
「だから・・・やっぱり人じゃないんだ」
「結論は急がないでいいでしょう。人間は、姿を眩ます為に、いろいろと工夫するものだよ」
「そして、燃やされた梯子、ですね」
ソフィが、不満そうな顔をした瑛の目を見ながら、なだめるように言った。
「敵は、君らを閉じ込めてから梯子を燃やして、我々の捜索を妨害しようとしたのかもしれないが・・・」
「かも知れないって?」
「月岡君、あのときも言ったとおり、あれじゃ妨害にはならない。せいぜい警告だよ。ただし、敵がイカれてなければの話だがね」
「それに、おかしなことが、もうひとつあります」
「そう。輝君が言うとおり、私や日下さんたちを助けてくれた者が居た」
「そうでしたね、男爵。あなたがたが閉じ込められてから、乏しいながら飲み水と食料をそっと運んできた者が居ますね」
「その人のおかげで、僕らは、皆さんや瑛が来てくれるまで生きながらえることができたんです。恩人と言ってもいい」
「妨害者も、その恩人も、同じ・・・やつかもしれないじゃないか。人間の常識で判断できる相手とは思えないんだ、俺は・・・」
「まあ、待ちたまえ。整理すると・・・『彼ら』は、一応、彼らということにしておくよ。彼らは、暁幌に人が入り込むことを嫌っていた。だが、その妨害行為は稚拙で素人の仕事だ。君らを洞穴に閉じ込めた行為はもっとも過激なものだったが・・・食料を運んだ者が居るということは殺意までは持っていなかったとも考えられる。あくまで、暁幌に入り込ませないこと、発見した洞穴から出て行ってほしいということ。それから、あの『鬼火』だが、彼らの仕業である可能性もあるということ。目的は、おそらく船の積荷だ」
「岩崎さん。すると、あなたは、船の積荷を奪うことを稼業にしているような盗賊が暁幌の坑内に潜んでいたとお考えなんですね」
「今のところは、です。ただ、何となくですが、しっくり来ない。辻褄は合っていると思うのですが・・・」
「引き続き、警察の皆さんはお付き合いくださるのでしょうね」
「勿論ですよ。聞けば、洞穴内に街を建設なさるとか。街には警察が必要です。それに、まだ敵の正体もつかめていない。しっかりした警護隊を率いて、私がその地下の街に常駐することになるでしょう」
「安心しました。ところで・・・そろそろ、その、あなたの遠縁の方がいらっしゃる時分だが・・・」
執事がやって来て、男爵に来客を告げた。
「福澤様とおっしゃる方がお見えです」
「ああ、彼ですよ。時間通りだ」
「お通ししなさい」
「やあ、皆さん。よう、警部殿。星男爵でいらっしゃいますね。はじめまして」
長身で眉目秀麗な男が、元気のよい足取りで部屋に入ってきた。そして、まっすぐに星のほうに歩み寄って、握手を求めた。
「福澤と申します。福澤桃介です」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「謎を整理してみるかね?」
「そうですね。まず、手紙です。二通目は、あきらかに男爵を暁幌に行かせまいとする意図から投函されたものです」
「だが、私でも気付くくらい、拙い仕掛けだった」
「そうです。次は、確か・・・頭上から石が投げ落とされた。殺意はともかく、怪我くらいはさせるつもりがあったと考えていいでしょう。ただの脅しじゃない。それから・・・」
「八号試掘坑でガスの穴を塞いだやつが居ます」
輝が言った。
「そして、発破のあとに瓦礫を積みなおして、洞穴を発見した君たちを迷わせた」
「その前に・・・洞穴の中で、僕が持っていたランプを叩き落とした・・・あれは・・・人ではありませんでした。頭上から来たんです」
「だから・・・やっぱり人じゃないんだ」
「結論は急がないでいいでしょう。人間は、姿を眩ます為に、いろいろと工夫するものだよ」
「そして、燃やされた梯子、ですね」
ソフィが、不満そうな顔をした瑛の目を見ながら、なだめるように言った。
「敵は、君らを閉じ込めてから梯子を燃やして、我々の捜索を妨害しようとしたのかもしれないが・・・」
「かも知れないって?」
「月岡君、あのときも言ったとおり、あれじゃ妨害にはならない。せいぜい警告だよ。ただし、敵がイカれてなければの話だがね」
「それに、おかしなことが、もうひとつあります」
「そう。輝君が言うとおり、私や日下さんたちを助けてくれた者が居た」
「そうでしたね、男爵。あなたがたが閉じ込められてから、乏しいながら飲み水と食料をそっと運んできた者が居ますね」
「その人のおかげで、僕らは、皆さんや瑛が来てくれるまで生きながらえることができたんです。恩人と言ってもいい」
「妨害者も、その恩人も、同じ・・・やつかもしれないじゃないか。人間の常識で判断できる相手とは思えないんだ、俺は・・・」
「まあ、待ちたまえ。整理すると・・・『彼ら』は、一応、彼らということにしておくよ。彼らは、暁幌に人が入り込むことを嫌っていた。だが、その妨害行為は稚拙で素人の仕事だ。君らを洞穴に閉じ込めた行為はもっとも過激なものだったが・・・食料を運んだ者が居るということは殺意までは持っていなかったとも考えられる。あくまで、暁幌に入り込ませないこと、発見した洞穴から出て行ってほしいということ。それから、あの『鬼火』だが、彼らの仕業である可能性もあるということ。目的は、おそらく船の積荷だ」
「岩崎さん。すると、あなたは、船の積荷を奪うことを稼業にしているような盗賊が暁幌の坑内に潜んでいたとお考えなんですね」
「今のところは、です。ただ、何となくですが、しっくり来ない。辻褄は合っていると思うのですが・・・」
「引き続き、警察の皆さんはお付き合いくださるのでしょうね」
「勿論ですよ。聞けば、洞穴内に街を建設なさるとか。街には警察が必要です。それに、まだ敵の正体もつかめていない。しっかりした警護隊を率いて、私がその地下の街に常駐することになるでしょう」
「安心しました。ところで・・・そろそろ、その、あなたの遠縁の方がいらっしゃる時分だが・・・」
執事がやって来て、男爵に来客を告げた。
「福澤様とおっしゃる方がお見えです」
「ああ、彼ですよ。時間通りだ」
「お通ししなさい」
「やあ、皆さん。よう、警部殿。星男爵でいらっしゃいますね。はじめまして」
長身で眉目秀麗な男が、元気のよい足取りで部屋に入ってきた。そして、まっすぐに星のほうに歩み寄って、握手を求めた。
「福澤と申します。福澤桃介です」
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年11月26日
第九章:地下都市 その3
「福澤さん・・・というと北炭の福澤さん? あの福澤翁の、たしかお嬢様と結婚されて、養子になられた」
「よくご存知で、光栄です。もっとも、先年、胸を病んで辞職しました」
「ほう。では、今は?」
「療養中にわずかばかりの貯えを元手に株を始めましてね。それが大当たりで・・・北炭時代よりもおおいに儲けましたよ」
胸を張って元気よく早口で話す。話しながら、ときおり、男爵の肩越しに窓の外に視線を泳がせ、遠い目をすることがある。
この男、頭の回転はすこぶる速いらしい。ただ、一見、軽妙洒脱な好青年だが、どこか暗い、怒りのような鋭さを持っている。虚勢ではない。虚勢ではないが、何か、自分の本来ではないところで威を見せねばならないもどかしさのようなものがある。自分の居場所が見つからないまま、その才を十分に発揮できずに、苛々しているのだな。悪い男ではないが、好人物でもない。
「金は使うためにある。小さな金なら、己を飾るために使いますがね。何十万という金です。大きな金は何か役に立つものに投資すべきでしょう。こう言っては何ですが、相場で儲けた、いわば『虚』が生んだ金です。これを『実』に変えなければ儲けた意味が無い」
「つまり、炭鉱に投資したい、とおっしゃるのですね」
「月並みな発想だと思われるかもしれませんね。あるいは、固い投資先。いまどき炭鉱に投資するというだけなら、芸はありませんね。間違いない投資先ですからね。しかし、星男爵、私は、あなたなら新暁幌炭鉱を、これまでに例の無い、まったく新しい事業にしてしまうのではないかと思っているんですよ。・・・地下都市を建設されると聞きましたよ」
「都市、というのは大げさかもしれません」
「いや、都市であるべきでしょう。地下に大都市を創る。面白い」
「投資は歓迎します。ただ、計画には・・・」
「口出しはしません。私は、見たいんですよ。まったく新しい、類例の無い事業をね。あなたなら、きっとやる。そして、学ばせていただきますよ。いずれ、私も、類例の無い新しいことをやってのけたいのでね」
面白い男だな、と星は思った。
「あらためて、歓迎しますよ。株主になっていただきましょう」
「もちろん、儲けさせていただきますからね」
儲けか。もう一皮剥ければたいした男になるな。儲けを捨てる気になったとき、この男は大きな仕事を成し遂げることになるのだろう。
類例の無いこと。
星は、地下の大洞穴に街を建設し、そこを新暁幌の中心にすることを考えている。この段階で、すでに類例が無いとも言えるのだが、星は、更にさまざまなことを考えていた。
その、もっとも重要な項目は動力源である。地上の設備であれば、炭鉱自体が産出する豊富な石炭を使って、蒸気機関でさまざまな設備を働かせればよい。しかし、地下で石炭を燃やせば、空気を清浄に保つことが難しい。そこで、星が考えたのは電気だった。すなわち、洞穴内の豊富な地下水脈を利用して、地下で水力発電を行う。巨大な設備を動かすにはおおがかりなダムが必要になるが、何箇所か流れが適した水脈を選んで、小規模な発電設備を設置すれば、全体としてはかなりの電力を地下の街に供給できる。さらに、電気であれば、地上に石炭を利用した火力発電設備を建設して、もっと大量の電力を地下に送電することもできる。これらの電力を徹底的に活用した街と採炭設備を構想していたのである。街の灯りや昇降機の動力だけではない、トロッコや機材の運搬も、蒸気機関車ではなく、電力で動く機関車を、各家庭で必要となる煮炊きや湯を沸かすための火も電熱器を、すなわち、地下の電気都市である。
やがて、計画は練られ、洞穴内の大きな地底湖のほとりに、新暁幌炭鉱の中心街となる新暁幌市の建設が着工された。そして、建設途上ながら、電力設備が徐々にととのい、半年を経ずして、地下には数千人の坑夫が住む街が誕生し、石炭を満載したおびただしい数のトロッコが地上に運び出された。
二十世紀の未来電気都市 新暁幌炭鉱
稼動を始めた新暁幌炭鉱には、日本中から見学者が押しかけた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
「よくご存知で、光栄です。もっとも、先年、胸を病んで辞職しました」
「ほう。では、今は?」
「療養中にわずかばかりの貯えを元手に株を始めましてね。それが大当たりで・・・北炭時代よりもおおいに儲けましたよ」
胸を張って元気よく早口で話す。話しながら、ときおり、男爵の肩越しに窓の外に視線を泳がせ、遠い目をすることがある。
この男、頭の回転はすこぶる速いらしい。ただ、一見、軽妙洒脱な好青年だが、どこか暗い、怒りのような鋭さを持っている。虚勢ではない。虚勢ではないが、何か、自分の本来ではないところで威を見せねばならないもどかしさのようなものがある。自分の居場所が見つからないまま、その才を十分に発揮できずに、苛々しているのだな。悪い男ではないが、好人物でもない。
「金は使うためにある。小さな金なら、己を飾るために使いますがね。何十万という金です。大きな金は何か役に立つものに投資すべきでしょう。こう言っては何ですが、相場で儲けた、いわば『虚』が生んだ金です。これを『実』に変えなければ儲けた意味が無い」
「つまり、炭鉱に投資したい、とおっしゃるのですね」
「月並みな発想だと思われるかもしれませんね。あるいは、固い投資先。いまどき炭鉱に投資するというだけなら、芸はありませんね。間違いない投資先ですからね。しかし、星男爵、私は、あなたなら新暁幌炭鉱を、これまでに例の無い、まったく新しい事業にしてしまうのではないかと思っているんですよ。・・・地下都市を建設されると聞きましたよ」
「都市、というのは大げさかもしれません」
「いや、都市であるべきでしょう。地下に大都市を創る。面白い」
「投資は歓迎します。ただ、計画には・・・」
「口出しはしません。私は、見たいんですよ。まったく新しい、類例の無い事業をね。あなたなら、きっとやる。そして、学ばせていただきますよ。いずれ、私も、類例の無い新しいことをやってのけたいのでね」
面白い男だな、と星は思った。
「あらためて、歓迎しますよ。株主になっていただきましょう」
「もちろん、儲けさせていただきますからね」
儲けか。もう一皮剥ければたいした男になるな。儲けを捨てる気になったとき、この男は大きな仕事を成し遂げることになるのだろう。
類例の無いこと。
星は、地下の大洞穴に街を建設し、そこを新暁幌の中心にすることを考えている。この段階で、すでに類例が無いとも言えるのだが、星は、更にさまざまなことを考えていた。
その、もっとも重要な項目は動力源である。地上の設備であれば、炭鉱自体が産出する豊富な石炭を使って、蒸気機関でさまざまな設備を働かせればよい。しかし、地下で石炭を燃やせば、空気を清浄に保つことが難しい。そこで、星が考えたのは電気だった。すなわち、洞穴内の豊富な地下水脈を利用して、地下で水力発電を行う。巨大な設備を動かすにはおおがかりなダムが必要になるが、何箇所か流れが適した水脈を選んで、小規模な発電設備を設置すれば、全体としてはかなりの電力を地下の街に供給できる。さらに、電気であれば、地上に石炭を利用した火力発電設備を建設して、もっと大量の電力を地下に送電することもできる。これらの電力を徹底的に活用した街と採炭設備を構想していたのである。街の灯りや昇降機の動力だけではない、トロッコや機材の運搬も、蒸気機関車ではなく、電力で動く機関車を、各家庭で必要となる煮炊きや湯を沸かすための火も電熱器を、すなわち、地下の電気都市である。
やがて、計画は練られ、洞穴内の大きな地底湖のほとりに、新暁幌炭鉱の中心街となる新暁幌市の建設が着工された。そして、建設途上ながら、電力設備が徐々にととのい、半年を経ずして、地下には数千人の坑夫が住む街が誕生し、石炭を満載したおびただしい数のトロッコが地上に運び出された。
二十世紀の未来電気都市 新暁幌炭鉱
稼動を始めた新暁幌炭鉱には、日本中から見学者が押しかけた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年12月02日
第十章:二十世紀の楽園 新暁幌市 その1
<二十世紀の楽園(パラダイス) 新暁幌市 その1>
初夏である。
もっとも、地底湖のほとりに広がる新暁幌市は年中気温も湿度も安定しているから、実のところ季節感には乏しい。地上から運ばれてくる農産物や海産物、そして地上から訪れる人々の服装が、かろうじて、この街の暮らしに季節の彩を与えてくれる。
この春に、新暁幌炭鉱が最初の石炭を積み出してから数ヶ月で、この地下都市の人口は日々増え続け、今や一万五千人である。年の暮れには三万人になっているだろうという予測もあるほど、街はどんどん広がっているのである。
新暁幌炭鉱の地下都市計画が立案され、建設が始まったのが去年の初冬だった。日下家は、早々に住まいをこの地底湖のほとりに移し、そこをベースにして街が建設された。
二十世紀の未来都市。電気都市である。
近代的で快適な住宅がどんどん建てられ、まず、集まってきたのは旧暁幌で働いていた坑夫たちである。もちろん、あの月岡瑛もその最初の一陣に加わった。
かつて、地上の暁幌では、坑夫たちは、谷間の主要坑を囲む小山や丘陵の中腹に並べて建てられた質素な長屋で暮らしていた。経営層や事務職員は坑に近い山麓に住居をあてがわれていたが、肝心の坑夫たちは丘の中腹の長屋から日々、谷底の坑まで降り、仕事が終われば家まで登るという日々を送っていたのである。いつの頃からか、長屋が斜面に並んでいる様子がハモニカに似ているというので、ハモニカ長屋などと呼ばれていたものだ。
しかし、同じ炭鉱と言っても、ここ、新暁幌はまるで別世界だった。
大洞穴発見後、炭鉱を再開するための資金はもちろん、星が提案し企画した「未来の電気都市」構想実現のための資金もすぐに集まった。
「新世紀」「未来」「電気」
新暁幌は、新時代を求め、未来を信じる多くの人々がイメージする楽園(パラダイス)の条件をすっかり満たしていた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
初夏である。
もっとも、地底湖のほとりに広がる新暁幌市は年中気温も湿度も安定しているから、実のところ季節感には乏しい。地上から運ばれてくる農産物や海産物、そして地上から訪れる人々の服装が、かろうじて、この街の暮らしに季節の彩を与えてくれる。
この春に、新暁幌炭鉱が最初の石炭を積み出してから数ヶ月で、この地下都市の人口は日々増え続け、今や一万五千人である。年の暮れには三万人になっているだろうという予測もあるほど、街はどんどん広がっているのである。
新暁幌炭鉱の地下都市計画が立案され、建設が始まったのが去年の初冬だった。日下家は、早々に住まいをこの地底湖のほとりに移し、そこをベースにして街が建設された。
二十世紀の未来都市。電気都市である。
近代的で快適な住宅がどんどん建てられ、まず、集まってきたのは旧暁幌で働いていた坑夫たちである。もちろん、あの月岡瑛もその最初の一陣に加わった。
かつて、地上の暁幌では、坑夫たちは、谷間の主要坑を囲む小山や丘陵の中腹に並べて建てられた質素な長屋で暮らしていた。経営層や事務職員は坑に近い山麓に住居をあてがわれていたが、肝心の坑夫たちは丘の中腹の長屋から日々、谷底の坑まで降り、仕事が終われば家まで登るという日々を送っていたのである。いつの頃からか、長屋が斜面に並んでいる様子がハモニカに似ているというので、ハモニカ長屋などと呼ばれていたものだ。
しかし、同じ炭鉱と言っても、ここ、新暁幌はまるで別世界だった。
大洞穴発見後、炭鉱を再開するための資金はもちろん、星が提案し企画した「未来の電気都市」構想実現のための資金もすぐに集まった。
「新世紀」「未来」「電気」
新暁幌は、新時代を求め、未来を信じる多くの人々がイメージする楽園(パラダイス)の条件をすっかり満たしていた。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
2006年12月02日
第十章:二十世紀の楽園 新暁幌市 その2
<第十章:二十世紀の楽園(パラダイス) 新暁幌市 その2>
星と日下亨は、大洞穴と新炭層の発見者として新暁幌の大株主となる権利を得て、星男爵は経営と事業企画、暁幌市、暁幌炭鉱の全体設計を、日下亨は星の計画に沿った実際の採炭作業の総指揮を執ることとなった。
輝は、星直属で、まだ全体像が明らかになっていない暁幌大洞穴の探査と炭層マップ作成を行う探査チームを率いる。そこには、瑛をはじめとする若くて研究意欲の盛んな坑夫とともに、ベテランの坑夫が参加した。
採炭作業は、実質露天掘りだから、もはや昔のように深い坑を縦横に掘って、暑苦しい狭い坑内で危険な作業をする必要は無い。それに、採炭現場まで引き込まれた電気によって、採掘作業自体も驚くほど楽で安全なものになった。安全だけでなく、合理化され効率を高められた採炭作業は、新暁幌の坑夫たちに十分な休日や余暇を与えることさえできた。つい一昔(ひとむかし)前には、爆発災害や、待遇改善を求める坑夫たちの暴動騒ぎまであった「炭坑」労働とはまるで異なる労働環境がここには生まれ始めていた。
新暁幌炭鉱は、他の多くの炭鉱とは異なる、まったく新しい炭鉱の姿、労働者の楽園(ユートピア)の事例(ケーススタディ)を提示する実験場でもあるのだ。
炭鉱そのものだけではない、新暁幌市という都市自体が未来劇場なのである。
暁幌市は、ちょうど地上の暁幌湖と同じような位置にある地底湖の周囲に展開している、地下数百メートルに建設された地下都市である。
地底湖周辺の都心部は巨大なホールのようになっており、湖の上に広がる丸天井は、はるか頭上数十メートル。湖のほとりからゆったりとした斜面を持つ広い丘陵がひろがっており、この丘陵いったいに居住区が広がり、都心となる。炭層はあるが、採炭作業は、この都心部と地底湖を中心に四方に延びる大きな洞穴の奥で行われている。その行き止まりがどのくらいあるか、どこまで炭層が広がっているかは、まだ見極められていない。
地下水脈が流れている数箇所に発電設備が据え付けられており、暁幌市の生活電源はこれで十分にまかなわれている。そして、地上には巨大な発電所が建設された。そのエネルギー源はここ暁幌で採掘される石炭だ。発電所からは、大洞穴内部に展開する採掘現場、洞穴内のすべての照明、そして新暁幌市と地上をつなぎ苫小牧の港まで敷設された電軌鉄道に電力を供給している。電軌鉄道は、新暁幌炭鉱で採掘された石炭や多くの乗客たちを日夜運んでいる。
新暁幌市は地下にあるが、その豊富な電力によっていたるところに照明設備がととのえられ、まるで不夜城のようだ。光だけでなく、地上との換気や、生活を快適にするためのあらゆる設備がととのっていた。地底湖は湧き水で、新暁幌市民の飲み水や生活用水は、ここからまかなわれる。これらの給水も排水も電気式のポンプで制御され、排水は地上に汲み出されてから処理される。新暁幌は完全な上下水設備をも完備しているのだ。
未来都市。大自然の奇跡と人類の奇跡の街。新暁幌市には、日本国内だけでなく、諸外国からも視察者や見学者がひきも切らず訪れた。
さて、あのソフィ=ナプホルト嬢はというと、そのまま暁幌に滞在し、当初の目的どおり、アイヌの伝承や言語、周辺の遺跡や地誌の収集と研究を続けていた。休日には瑛の案内で、かつて彼が話を聞きまわった古老たちを訪問しては伝承や昔語りの聞き取りをしたり、収集した資料を瑛と一緒に整理したり、ときには議論したり、そして瑛が炭坑の仕事で忙しい平日は、星男爵の紹介で札幌の大学や、各地の学校、図書館などを訪れ、資料の調査や収集をしたりと忙しく楽しい日々を送っている。
グスタフ=ライセンフェルト青年は、もともと物理学、鉱物学の研究者であり、あの高名なレオン=ナプホルト博士の助手をつとめてきたほどの俊英である上に、最先端の欧州の技術情報もふんだんに持っていたから、星男爵のよき助手となって、新暁幌の開発や設計を助けた。ただ、彼は、このあたりで「黒水晶」と呼ばれる不思議な鉱物の調査が元々の目的であるから、時間をとってはひとりで北海道各地に出向いて、あちこちの鉱物や地質の調査に余念が無かった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.
星と日下亨は、大洞穴と新炭層の発見者として新暁幌の大株主となる権利を得て、星男爵は経営と事業企画、暁幌市、暁幌炭鉱の全体設計を、日下亨は星の計画に沿った実際の採炭作業の総指揮を執ることとなった。
輝は、星直属で、まだ全体像が明らかになっていない暁幌大洞穴の探査と炭層マップ作成を行う探査チームを率いる。そこには、瑛をはじめとする若くて研究意欲の盛んな坑夫とともに、ベテランの坑夫が参加した。
採炭作業は、実質露天掘りだから、もはや昔のように深い坑を縦横に掘って、暑苦しい狭い坑内で危険な作業をする必要は無い。それに、採炭現場まで引き込まれた電気によって、採掘作業自体も驚くほど楽で安全なものになった。安全だけでなく、合理化され効率を高められた採炭作業は、新暁幌の坑夫たちに十分な休日や余暇を与えることさえできた。つい一昔(ひとむかし)前には、爆発災害や、待遇改善を求める坑夫たちの暴動騒ぎまであった「炭坑」労働とはまるで異なる労働環境がここには生まれ始めていた。
新暁幌炭鉱は、他の多くの炭鉱とは異なる、まったく新しい炭鉱の姿、労働者の楽園(ユートピア)の事例(ケーススタディ)を提示する実験場でもあるのだ。
炭鉱そのものだけではない、新暁幌市という都市自体が未来劇場なのである。
暁幌市は、ちょうど地上の暁幌湖と同じような位置にある地底湖の周囲に展開している、地下数百メートルに建設された地下都市である。
地底湖周辺の都心部は巨大なホールのようになっており、湖の上に広がる丸天井は、はるか頭上数十メートル。湖のほとりからゆったりとした斜面を持つ広い丘陵がひろがっており、この丘陵いったいに居住区が広がり、都心となる。炭層はあるが、採炭作業は、この都心部と地底湖を中心に四方に延びる大きな洞穴の奥で行われている。その行き止まりがどのくらいあるか、どこまで炭層が広がっているかは、まだ見極められていない。
地下水脈が流れている数箇所に発電設備が据え付けられており、暁幌市の生活電源はこれで十分にまかなわれている。そして、地上には巨大な発電所が建設された。そのエネルギー源はここ暁幌で採掘される石炭だ。発電所からは、大洞穴内部に展開する採掘現場、洞穴内のすべての照明、そして新暁幌市と地上をつなぎ苫小牧の港まで敷設された電軌鉄道に電力を供給している。電軌鉄道は、新暁幌炭鉱で採掘された石炭や多くの乗客たちを日夜運んでいる。
新暁幌市は地下にあるが、その豊富な電力によっていたるところに照明設備がととのえられ、まるで不夜城のようだ。光だけでなく、地上との換気や、生活を快適にするためのあらゆる設備がととのっていた。地底湖は湧き水で、新暁幌市民の飲み水や生活用水は、ここからまかなわれる。これらの給水も排水も電気式のポンプで制御され、排水は地上に汲み出されてから処理される。新暁幌は完全な上下水設備をも完備しているのだ。
未来都市。大自然の奇跡と人類の奇跡の街。新暁幌市には、日本国内だけでなく、諸外国からも視察者や見学者がひきも切らず訪れた。
さて、あのソフィ=ナプホルト嬢はというと、そのまま暁幌に滞在し、当初の目的どおり、アイヌの伝承や言語、周辺の遺跡や地誌の収集と研究を続けていた。休日には瑛の案内で、かつて彼が話を聞きまわった古老たちを訪問しては伝承や昔語りの聞き取りをしたり、収集した資料を瑛と一緒に整理したり、ときには議論したり、そして瑛が炭坑の仕事で忙しい平日は、星男爵の紹介で札幌の大学や、各地の学校、図書館などを訪れ、資料の調査や収集をしたりと忙しく楽しい日々を送っている。
グスタフ=ライセンフェルト青年は、もともと物理学、鉱物学の研究者であり、あの高名なレオン=ナプホルト博士の助手をつとめてきたほどの俊英である上に、最先端の欧州の技術情報もふんだんに持っていたから、星男爵のよき助手となって、新暁幌の開発や設計を助けた。ただ、彼は、このあたりで「黒水晶」と呼ばれる不思議な鉱物の調査が元々の目的であるから、時間をとってはひとりで北海道各地に出向いて、あちこちの鉱物や地質の調査に余念が無かった。
Copyright (c) 2006 Ando, Tadashi & Fuyuno, Yuki All rights reserved.